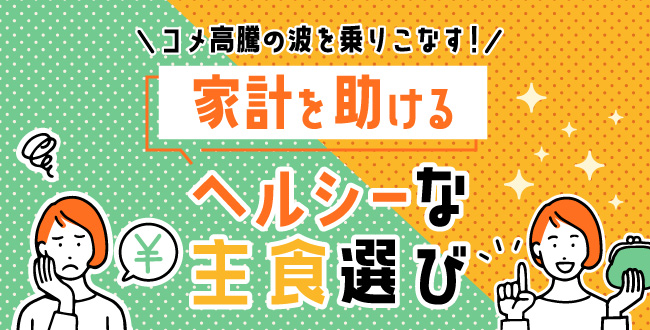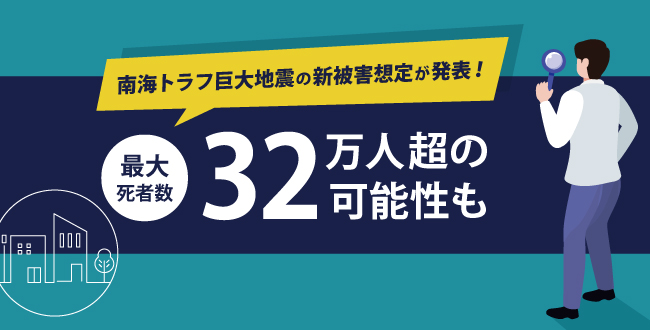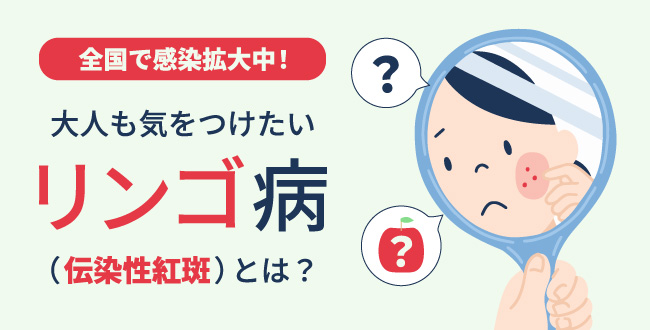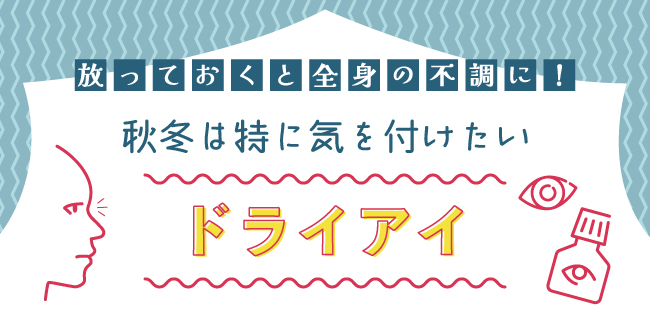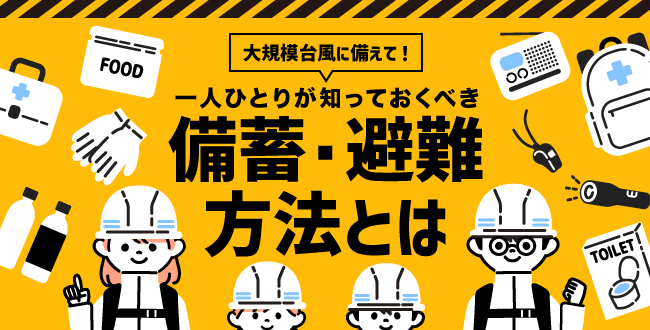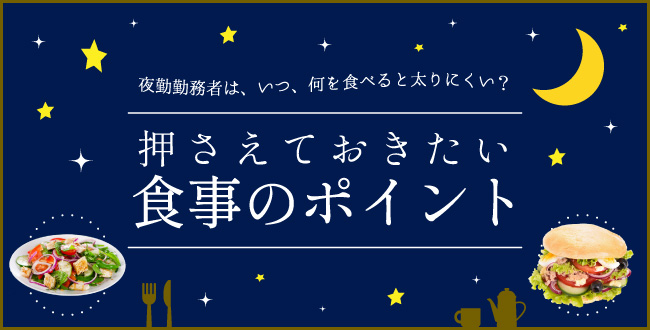子どもに多い感染症のひとつ、RSウイルス感染症。
毎年秋から冬にかけて流行の波がやってきますが、近年は季節に関係なく発生することもあり、保育園・幼稚園での集団生活をきっかけに広がるケースが増えています。
重症化しやすく、「お子さんが入院した……」なんて話を耳にしたことがある方も多いでしょう。
感染力が非常に高く、子どもだけでなく家庭内で蔓延し、家族全員がダウンすることも珍しくありません。
実はRSウイルスは、2歳までにほぼ100%の子どもが一度は感染すると言われています。
RSウイルスは200種類以上ある風邪のウイルスの一種。そのため、初期症状は鼻水や軽い咳、発熱など、一般的な風邪と見分けがつきにくいのが特徴です。
このウイルスが有名なのは、特に1歳未満の子どもに感染すると重症化のおそれがあるためです。
乳幼児の肺炎の約50%はRSウイルスによるものとも言われています。
新生児や乳幼児がいて、兄弟姉妹が保育園に通っている場合は要注意です。
いわゆる「保育園の洗礼」とも言われますが、集団生活で感染を防ぐのは簡単ではありません。
そこで、重症化を防ぐ行動と家庭でできる感染対策を、保健師目線でお伝えします。
自宅でできる感染対策
RSウイルスは飛沫感染と接触感染の両方で広がります。
接触感染はドアノブ・おもちゃ・食器などを介しても起こるため、次の対策が効果的です。
・ 使用後のおもちゃはアルコールまたは次亜塩素酸ナトリウムで消毒
・ 家族間でもタオルは共有しない
・ 食器・コップは別々にする
・ 子どもの残したごはんは食べない(口移しも避ける)
・ おむつ替えや抱っこをしたあとは顔や手を洗う
・ 感染リスクが考えられるときは、マスクをつけて授乳(母乳はあげてOK)
・ 鼻水をふき取ったらすぐに手を洗う
・ 保育園から帰宅後はなるべくすぐに着替えや入浴する
・ 十分な睡眠で免疫力を維持する
妊娠中の方はワクチン接種の検討も
妊娠期間中にRSウイルスワクチンを接種することで、母体から胎児へ抗体が移行し、生後しばらくは感染予防効果が期待できます(接種時期や適応は医師と要相談)。
大切なのは、感染後に慌てず正しく対処すること
どれだけ対策をしても感染することはあります。
家庭内での二次感染を最小限にし、重症化を見逃さないことが重要です。
医療機関への受診については、機嫌がよく、食事、水分が接種できていれば様子見で構いませんが、下記の症状がある場合は受診を検討しましょう。
医療機関を受診する目安
・ ヒューヒューといった呼吸音が続く(喘鳴)
・ 呼吸困難により顔色が青白い、唇の色が青紫色になる
・ せき込んで嘔吐し、食事や水分がとれない
受診すべきか迷ったときは……
こども医療電話相談「#8000」に発信することで地域の相談窓口につながります。
開設時間は地域ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
相談窓口開設時間は地域によって異なるため、以下のサイトから確認しましょう。
「#8000」対応時間外であれば、大人も利用可&開設時間が長い、救急安心センター「#7119」も活用しましょう。
ポイント
緊急連絡先は冷蔵庫や電話機近くなど、すぐ目に入る場所に貼っておくと安心です。パニック時に番号を思い出せなくてもすぐに対応できます。
厚生労働省・日本小児科学会監修の「こどもの救急」サイトでは、症状を選ぶだけで受診の目安を判断できます。ぜひブックマークしておきましょう。
RSウイルスは、保育園や幼稚園をきっかけに家庭内で広がりやすい感染症です。
「早く気づく」「家庭で広げない」ことが、重症化予防の第一歩。
万が一感染しても、家庭での感染対策によって症状の悪化や家族への拡大を防ぐことができます。
今日からできる小さな工夫で、家族みんなの健康を守りましょう!
<参考>
厚生労働省「RSウイルス感染症」