南海トラフ巨大地震の新被害想定が発表!最大死者数32万人超の可能性も
- 2025/5/23
- 災害
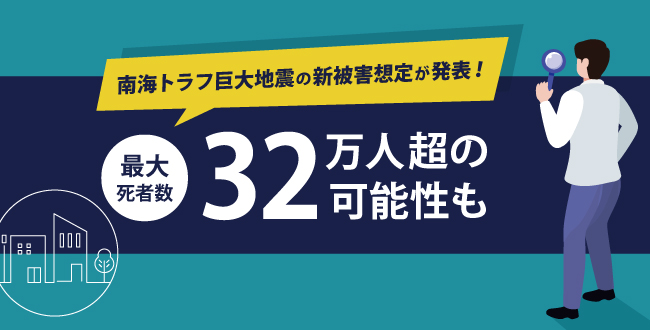
政府の地震調査委員会と内閣府は2025年3月、南海トラフ巨大地震に関する新たな被害想定を発表しました。
今回の想定は、最新の科学的知見と過去の災害から得られた教訓をもとに、地震発生時の津波、火災、建物倒壊、さらにライフラインや交通網の寸断による二次被害までを含めた包括的な評価となっています。
新想定では最悪の場合、死者数は最大で32万人を超える可能性があるとされ、従来の想定よりも深刻な結果が示されました。
特に、沿岸部の津波による被害が甚大であり、地域によっては地震発生からわずか5〜10分で津波が到達すると予測されています。
高知県や和歌山県、静岡県などの太平洋沿岸地域では特に危険度が高く、迅速な避難行動と地域ごとの対策強化が急がれています。
被害は物理的被害にとどまらず【災害関連死にも注意】
今回の新想定では、直接的な死者数に加え、「災害関連死」のリスクも強調されています。
これは、避難生活の長期化や医療の遅れ、精神的ストレスなどにより、地震や津波による直接的な被害を免れた人々が、その後に命を落とすケースを指します。
能登半島地震では、直接死者数より災害関連死者数が上回り、大きく注目されています。
過去の災害でも多く見られたこの災害関連死について、政府は今後の南海トラフ地震では最大約10万人にのぼる可能性があるとしています。
特に、高齢者や持病を持つ人、医療機器を使用している人にとって、避難所での生活環境は命に関わる問題です。
こうした背景をふまえ、国や自治体には「命を守るだけでなく、その後の命も守る」対策が求められています。
備えで被害は半減できる
内閣府は、こうした被害は「備え次第で減らすことができる」と強調しています。
事前の備えや地域コミュニティによる防災訓練、情報伝達体制の整備などにより、死者数や経済的被害を大幅に抑えられる可能性があるとしています。
特に、個人や家庭での「自助」の意識と行動が、地域全体の安全を左右すると言われています。
行政備蓄だけでは足りない【「自助」の備えがカギ】
災害時には行政からの支援や備蓄物資が提供されますが、南海トラフ地震のような広域大災害では物流の停止や物資の不足が深刻化することが予想されています。
実際に、大規模災害発生直後は行政の支援がすぐには届かず、「最初の3日間は自力で乗り切る」ことが前提となります。
今回の想定でも、避難者は最大で2600万人を超えるとされ、行政が備える物資だけでは到底まかないきれない現実が浮かび上がっています。
そのため、家庭や事業所単位での備蓄や準備が不可欠であり、「自助」の意識が一人ひとりに強く求められています。
個人でできる防災対策【チェックリスト】
以下は、災害に備えて今すぐ始められる個人・家庭の防災対策です。
日常に取り入れて、いざというときに備えておきましょう。
■ 日常の備え
• 非常用持ち出し袋を準備(飲料水、保存食、常備薬、懐中電灯、モバイルバッテリー、マスク、簡易トイレなど)
• 家庭内の備蓄を最低3日分、できれば1週間分用意(特に水・食料・衛生用品)
• 家具の転倒・落下防止対策(L字金具や滑り止めマットの使用)
• 室内の安全点検(寝室や通路にガラスや倒れやすいものを置かない)
• スリッパ・懐中電灯を枕元に常備
• 防災アプリのインストール、防災無線のチェック
■ 家族・地域との連携
• 家族で避難場所・避難経路を話し合い、地図で共有
• 集合場所・連絡手段を決めておく(停電・通信障害時を想定)
• 防災訓練や地域の防災イベントに参加
• 高齢者や障害のある家族の避難支援方法を確認
■ 建物・生活環境の見直し
• 自宅やマンションの耐震診断・耐震補強
• 津波浸水区域に居住している場合は、避難先の高台を事前確認
• ハザードマップの入手・確認(自治体HPや防災センター等で閲覧可)
職場でできる防災対策【チェックリスト】
職場での防災対策も重要です。
衛生委員会等の場で話し合うことをおすすめします。
• 防災計画とマニュアルの作成・周知
• 避難経路の確保と定期的な確認、避難訓練
• 安否確認システムの導入と運用
• 事業継続計画(BCP)の策定
• 防災用品、火災報知器の点検・更新
• 従業員への防災意識啓発活動
防災は特別なことではなく、日々の暮らしの延長線上にあるものです。
南海トラフ巨大地震は「いつか来る」ではなく「いつ来てもおかしくない」災害とされています。
国や自治体の対策だけでなく、一人ひとりの備えが被害を減らす鍵を握っています。
今、私たちにできる対策を行動に移すことが、未来の命と暮らしを守る第一歩です。
<参考>
内閣府「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」
非常災害対策本部「令和6年能登半島地震による被害状況等について」




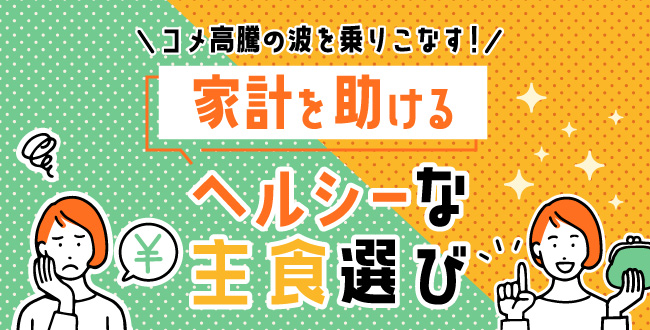

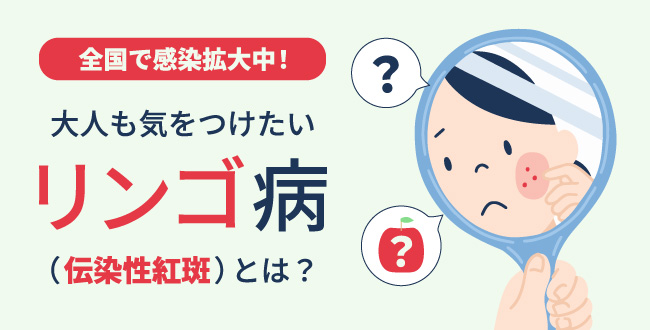
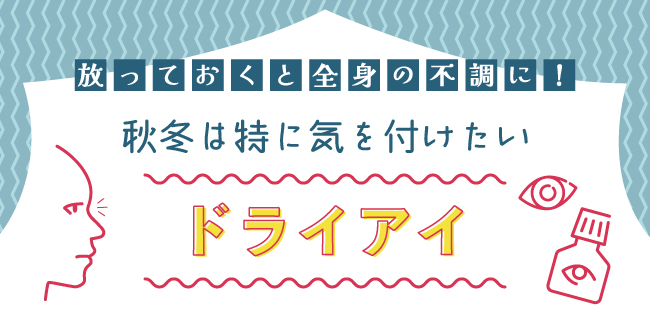
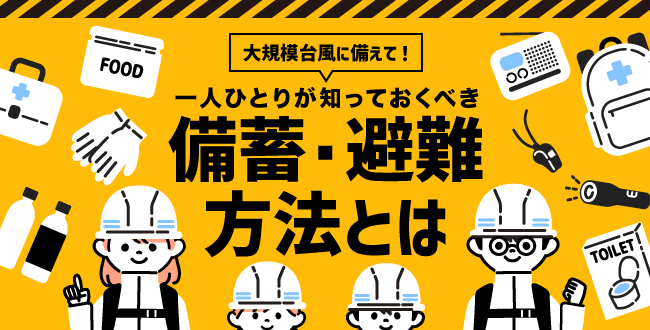
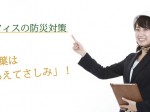

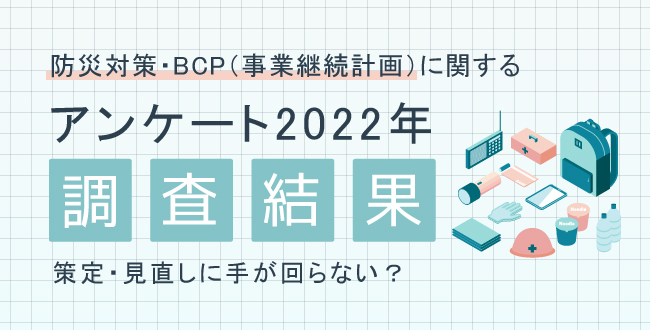
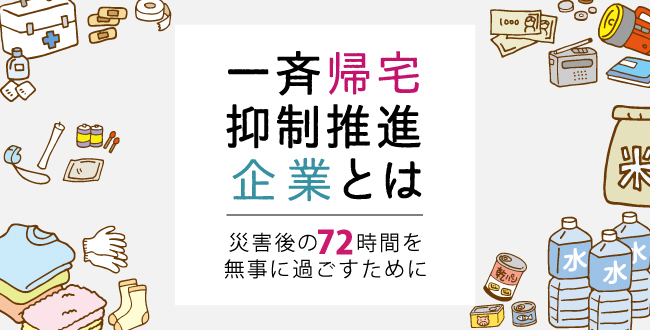
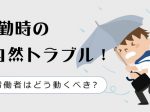





唐澤さん公益通報サムネ.jpg)

