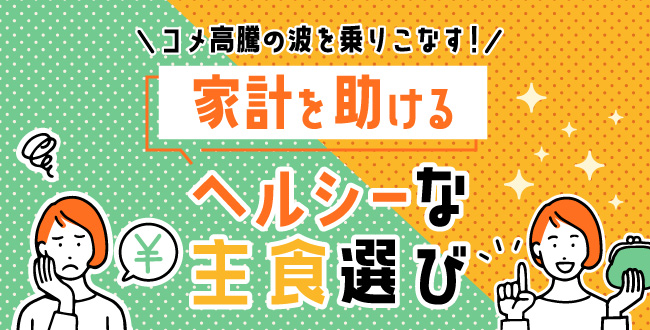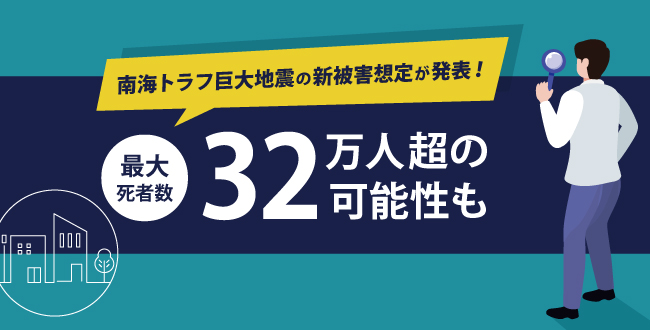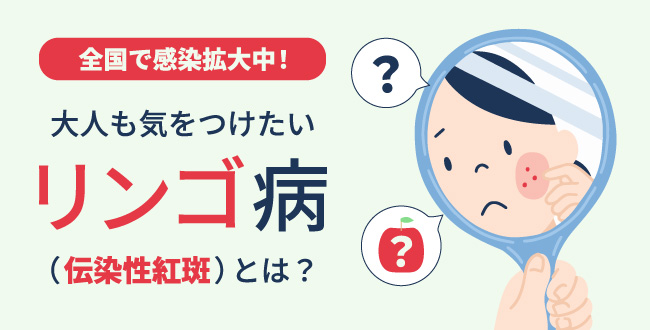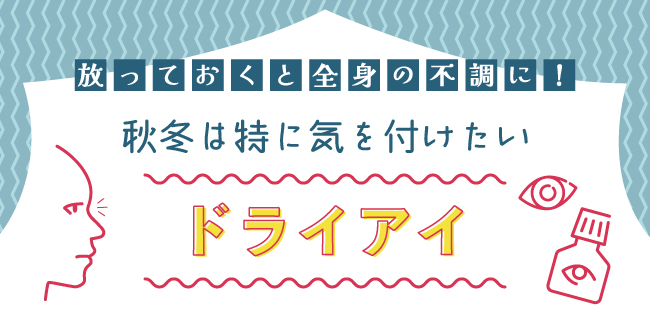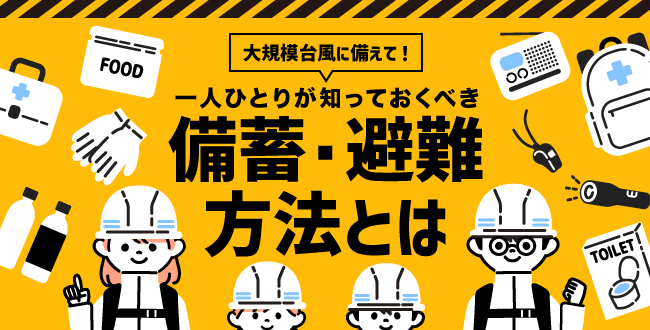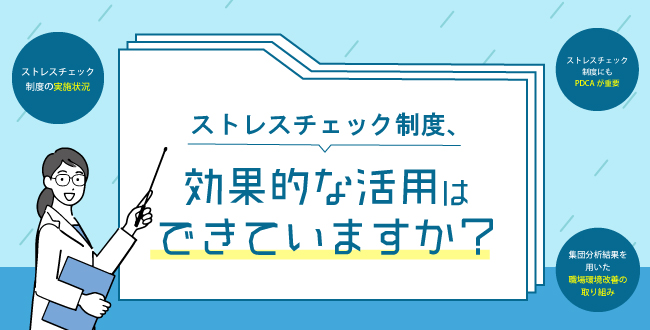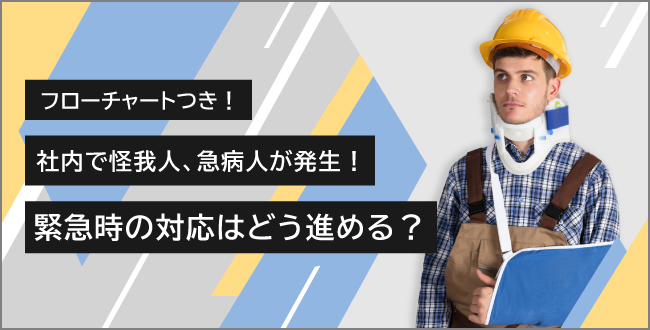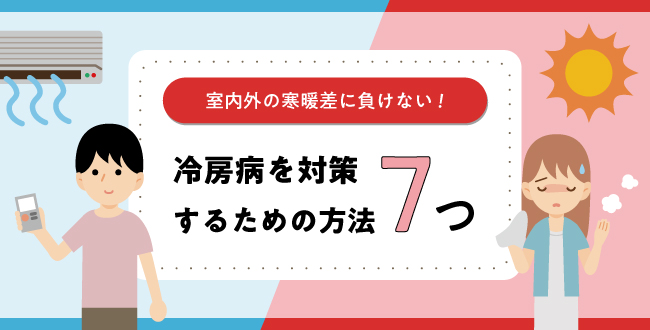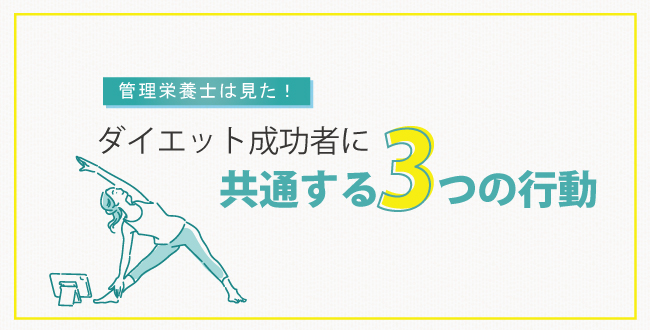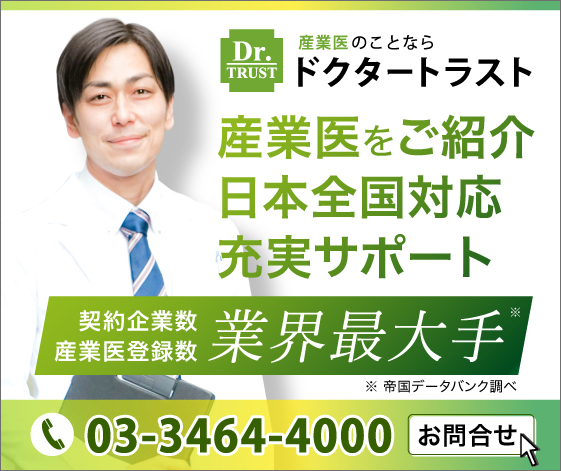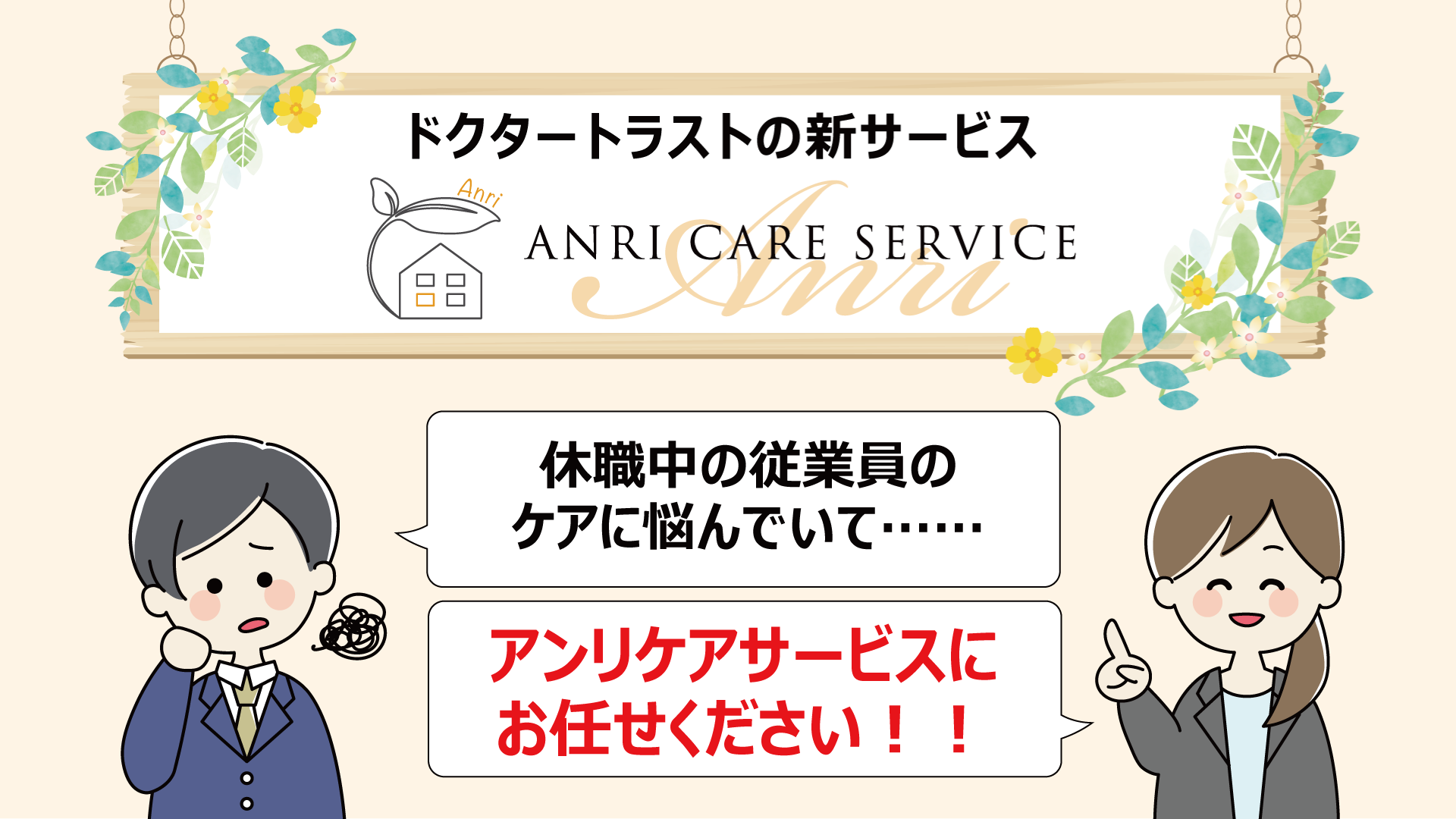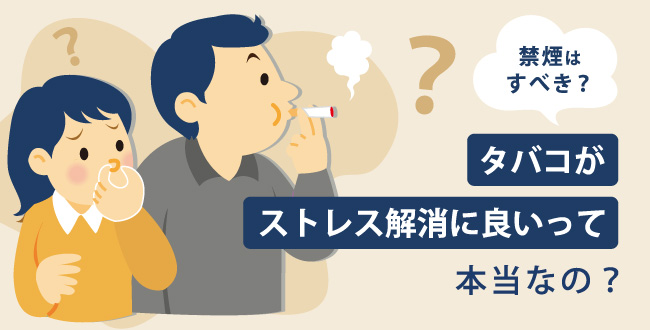- Home
- ドクタートラストニュース, 新入社員, 春
- 新生活、最高のスタートを!~自律神経を味方にする具体的な方法~
新生活、最高のスタートを!~自律神経を味方にする具体的な方法~
- 2025/3/25
- ドクタートラストニュース, 新入社員, 春

春は進学、就職、異動など新しい生活が始まる希望に満ちた季節です。
一方では、環境の変化による緊張やストレスを感じやすい時期でもあります。
気が抜けない日々が続くと心身のバランスを保つことが難しくなってしまいます。
春は自律神経が乱れやすい季節
節目となる春は、実は寒暖差が一番大きい季節といわれており、2024年3~5月の東京の平均気温の差は10.4℃でした。
三寒四温(3日間寒い日が続いた後に4日間暖かい日が続く)という言葉があるように、春は気温差が激しいのです。
自律神経は1日の寒暖差が7℃を超えてしまうと、自力で体温調節しきれなくなります。
春は気候面からも心身に様々な影響を与えます。
環境の変化による疲れは避けがたいものですが、寒暖差による自律神経の乱れはセルフケアによって整えることができます。
また、今や国民病といわれている花粉症も自律神経の乱れにより症状が悪化する場合があるので、少しでも新生活の疲れを軽減し、理想的なスタートを切れるように意識してみましょう。
そもそも自律神経はどのような役割を担っているのか
自律神経は、脳と各臓器をつなぐ役割があり、呼吸をする、体温を調節する、汗をかくなどの無意識の行動を調整している神経です。
また自律神経は、交感神経と副交感神経の2つに分かれています。
交感神経は、日中に活発に働き、アクセル全開モードにしてくれる神経です。
副交感神経は身体を休めるとき優位になり、ブレーキモードと例えることができます。
普段はうまくバランスをとっている交感神経と副交感神経ですが、急激な気温や気圧の変化で調節がうまくできなかったり、長期間ストレスがかかり続け、常に交感神経が優位になったりすると両者のバランスが崩れて心身に影響を及ぼします。
自律神経が乱れているサイン
以下のような兆候があれば、自律神経が乱れている可能性があります。
・ だるさ、疲れやすさがある
・ 不眠、寝れない
・ 頭痛、めまい、立ちくらみ
・ 耳鳴り
・ 喉が詰まる、息苦しい
・ 肩、首、背中、腰などのこり、痛み
・ 汗が出ない、または多汗、冷や汗
・ 不安、イライラする、恐怖感、悲哀感、集中力の低下
・ 手足のしびれ、痛み、冷え、ほてり
・ 吐き気、腰痛、便秘、下痢、食欲がない
・ 動悸、胸が苦しい
・ 口の渇き、味覚の障害
・ 目の疲れ、痛み
自律神経を整える方法
自律神経は日常生活の一工夫で整えることができます。
難しく考えずに、まずは気軽に試してみましょう。
適度な運動
中之条研究という、群馬県の中之条町の65歳以上の住民5,000人を対象に、20年以上にわたって行われた研究によると、うつ病と診断された人には、1日4,000歩未満しか歩いていないこと、中強度の運動をほぼまったくしていないという特徴があったようです。
そのため、4,000歩、早歩き5分以上を心がけると、うつ病予防に効果的といわれています。
また、それ以上歩くと身体面の健康を促進することも他の研究で明らかになっています。
さらに、幸せホルモンのセロトニンは運動開始5分後から分泌され20~30分でピークとされるので、できれば1回の運動で20分くらいは体を動かすのがおすすめです。
ある程度の身体活動により健康効果が得られますので、まずは家の周りやオフィス周りをお散歩してみるのはいかがでしょうか。
リラックス
リラックス行動をとると、副交感神経が優位になります。
また、副交感神経を優位にすると質の良い睡眠にもつながり一石二鳥です。
・ ストレッチ
・ 熱すぎないお湯で入浴
・ きつすぎない有酸素運動
・ ヒーリングミュージックを聴く
・ 人に話す
慣れない環境や状況に身を置くと、知らず知らずのうちに心身に負荷がかかっていることが多いです。
定期的に心身の状態を振り返り、自分にあったセルフケア方法を探索し、より良い新生活を送れるように心身を整えましょう。
<参考>
・ 気象庁「東京(東京都)2024年(月ごとの値)主な要素」
・ 厚生労働省「ヘルスケアラボ 冷え」
・ 青栁幸利ほか「高齢者における日常的な身体活動と心身の健康:中之条研究」(『保健師ジャーナル』65巻12号、2009年12月発行)