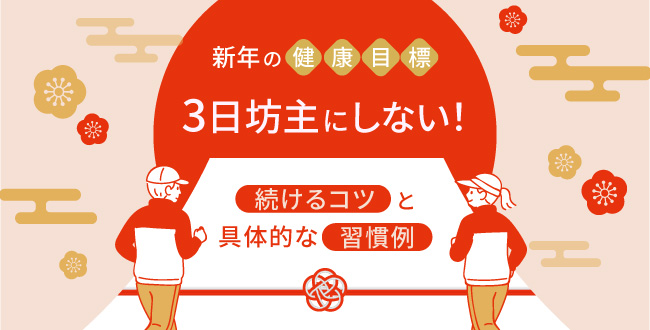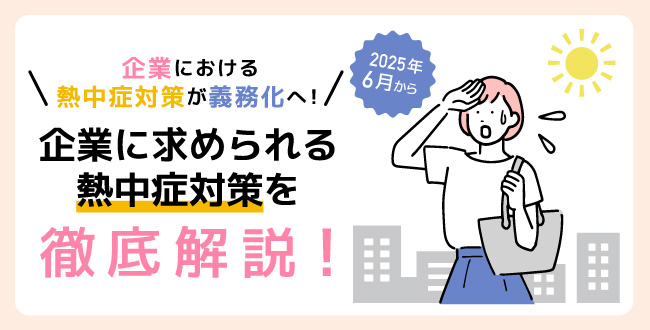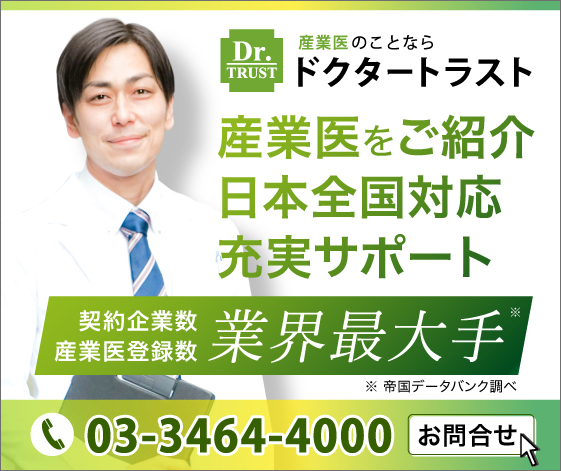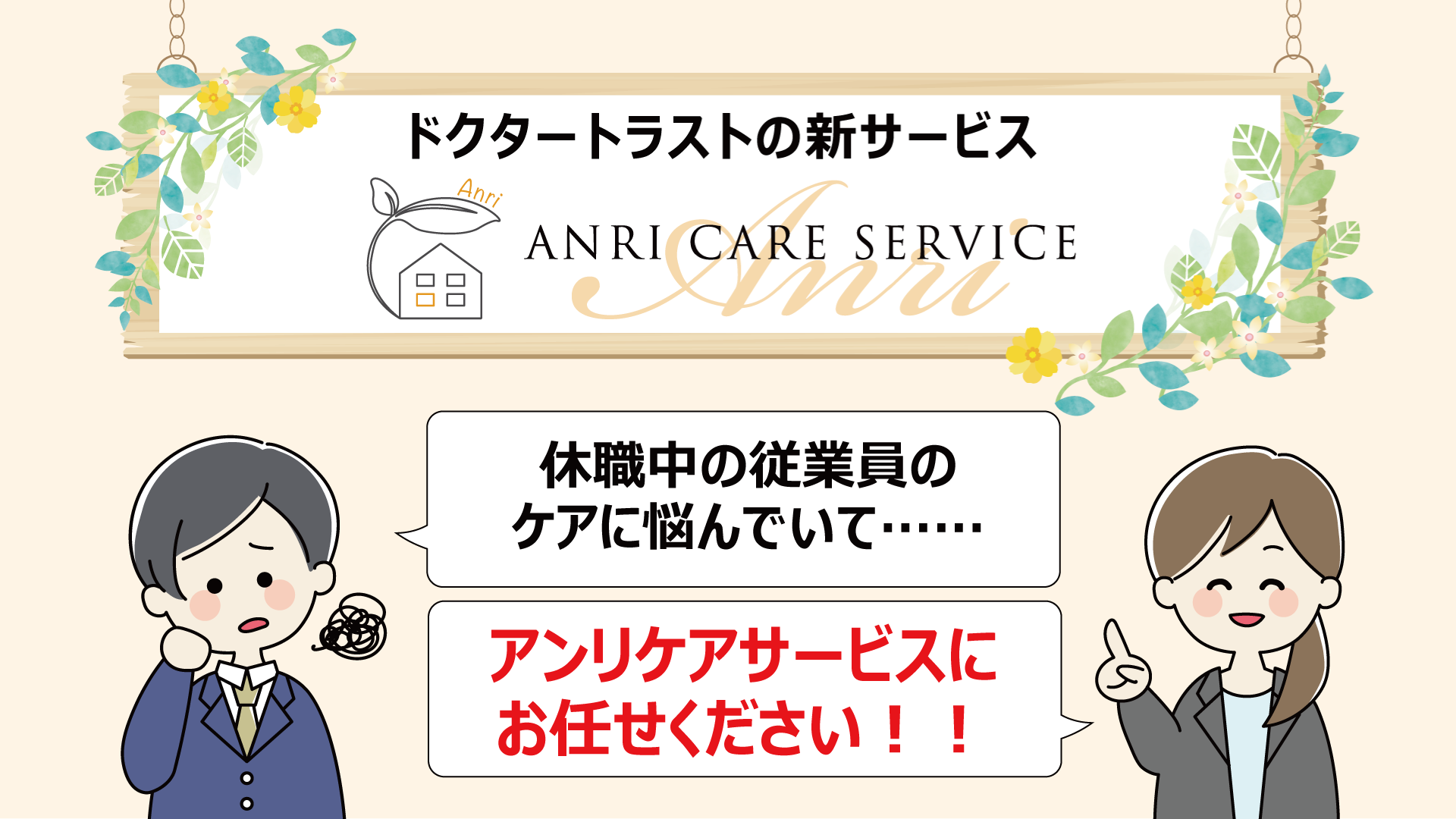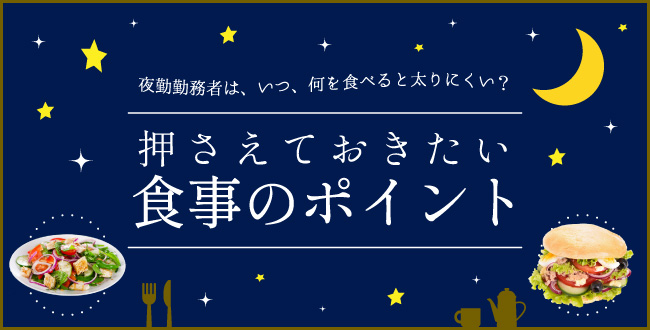- Home
- ドクタートラストニュース, 働き方改革, 法改正
- 働き方が変わる2025年春と秋―育児と仕事の両立をもっと柔軟に―
働き方が変わる2025年春と秋―育児と仕事の両立をもっと柔軟に―
- 2025/9/24
- ドクタートラストニュース, 働き方改革, 法改正
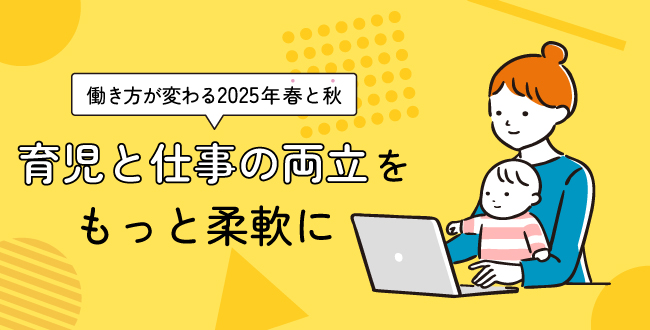
2025年4月・10月に「育児・介護休業法」が大きく改正された・改正されることをご存じですか?
今回の改正は、従業員が「働きながら育児できる環境を整えること」を企業により一層求める内容となっています。
企業の規模に関わらず義務化される対応も多く、「知らなかった」では済まされないポイントも。本コラムでは、改正の概要と対応のヒントをわかりやすくご紹介します。
何が変わった?変わる?―2025年改正のポイント
今回の育児・介護休業法などの改正は、働きながら子育てをする人のニーズをふまえた「柔軟な働き方」の実現が中心です。大きく変わる点は以下のとおりです。
① 子の看護休暇→「子の看護等休暇」に(2025年4月〜)
従来の「子の看護休暇」は、取得理由が子の病気・けがや予防接種、健康診断に限定されていましたが、今回の改正で、以下も対象になりました。
・ 感染症に伴う学級閉鎖など
・ 入園(入学)式、卒園式
また、対象となる子の範囲も「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」へと拡大し、より実態に合った制度になりました。
② 残業免除の対象拡大(2025年4月〜)
所定外労働の制限を請求可能となる労働者の範囲が、「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」へ拡大されました。
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークなどを追加(2025年4月〜)
3歳に満たない子を養育する労働者に対して、育児短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置の選択肢の1つにテレワークが追加されました。
これにより、短時間勤務制度の代替措置は以下のとおりです。
・ 育児休業に関する制度に準ずる措置
・ フレックスタイム制
・ 始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
・ 保育施設の設置・運営など
・ テレワーク
④ 育児休業などの取得状況の公表義務適用の拡大(2025年4月〜)
これまでは、「常時雇用する労働者数1,001人以上の企業」が対象であった毎年1回の男性の育児休業などの取得状況の公表が「常時雇用する労働者数301人以上の企業」に対象が拡大されました。
⑤ 柔軟な働き方の制度導入が義務に(2025年10月〜)
3歳未満の子どもを育てる従業員に対して、以下5つの選択肢から2つ以上の制度を選択し導入することが企業に義務付けられます。
・ 始業時刻などの変更
・ テレワーク制度(10日以上/月)
・ 保育施設の設置運営など
・ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
・ 短時間勤務制度
そして労働者は企業が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
今回の改正では従業員のライフスタイルに応じた「選べる制度」の整備が求められているのです。
⑥ 制度利用の”意向確認”が必須に(2025年10月〜)
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産などを申し出た時と労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、従業員へ企業側から「どのように働きたいか」の意向確認を行うことが義務化される予定です。
聴取される内容は以下のとおりです。
・ 勤務時間帯(始業および就業の時刻)
・ 勤務地(就業の場所)
・ 両立支援制度などの利用期間
・ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直しなど)
単に制度を用意するだけでなく、個別に周知や本人のニーズを把握し、それに合う支援を行うことが必要です。
意向確認のタイミングや方法(面談、書面など)は企業ごとに決められますが、定期的な確認が推奨されており、「一度聞いて終わり」では済まない点に注意が必要です。
現場ではどう対応すれば?〜衛生管理者・人事の立場からできること
法改正の理解は大切ですが、「それを職場でどう運用するか」が最も大事なポイントです。ここでは、産業保健スタッフや衛生管理者が特に意識しておきたい視点をご紹介します。
情報共有は「わかりやすく・全員に」
制度の対象となる人はもちろん、上司や同僚など、まわりの人にも制度の内容を知ってもらうことが、利用しやすい職場づくりには欠かせません。
イントラネットでの掲示や社内研修など、形式を問わず「誰にでも伝わること」が重要です。
本人の「遠慮」を見逃さない
制度があっても、「周囲に迷惑をかけるから使いにくい…」と感じてしまう方は少なくありません。
育児との両立は”気持ちの折り合い”も含まれます。医療職や衛生管理者が相談窓口として関わることも、心理的安全性の確保につながります。
柔軟な制度を「名ばかり」にしない
テレワークやフレックス制度は、業務の性質によって使える・使えないがありますが、「使えない理由」だけで判断するのではなく、どう工夫すれば導入できるかを前向きに検討する姿勢が求められます。
たとえば「午前中だけ在宅、午後は出勤」など、部分的な活用でも十分な支援になります。
子育てしやすい職場は、誰にとっても働きやすい
今回の法改正は、子育てをしている一部の人だけの問題ではありません。
「急な呼び出しで帰ってしまうのが気まずい」「フレックス勤務だと評価されにくい」などの”見えないハードル”を取り除くチャンスでもあります。
子育てや介護、病気の治療、ライフステージの変化――誰にでも訪れる”両立の壁”に備えて、今回の法改正をきっかけに職場全体の働き方を見直すことが求められています。
<参考>
厚生労働省「育児・介護休業法について」