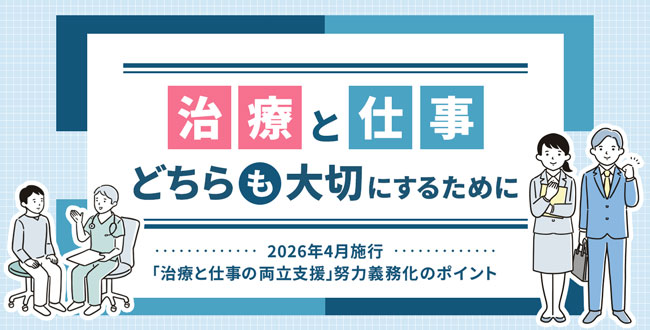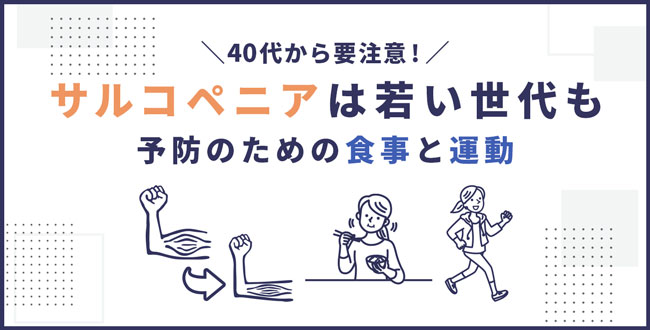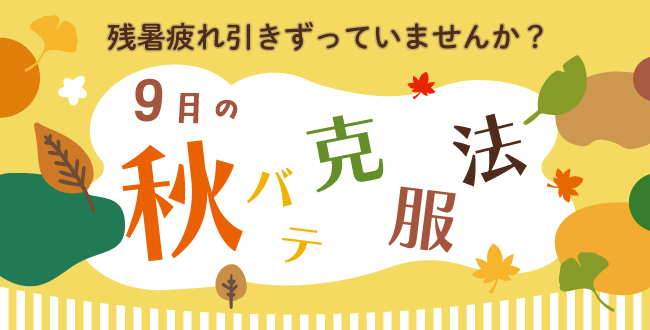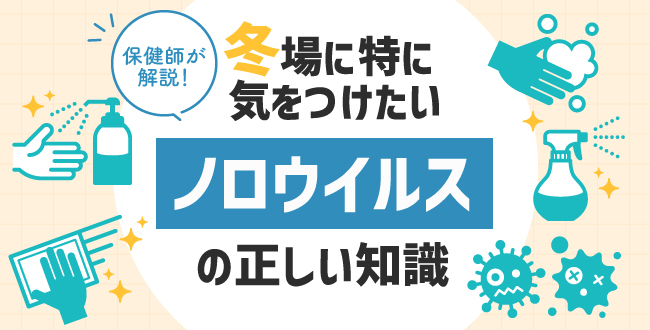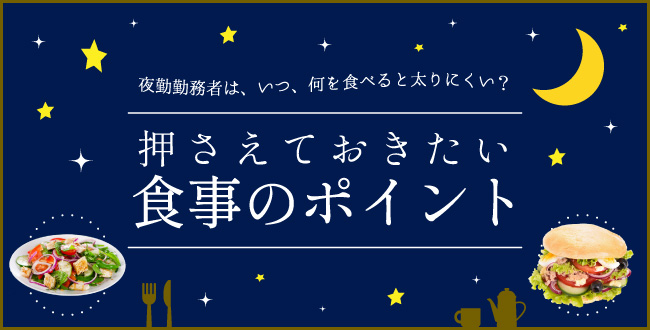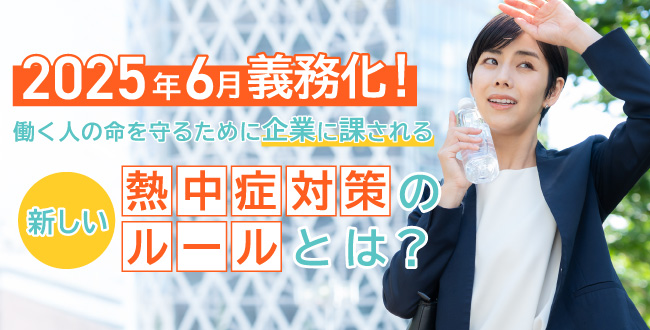
「暑い」を通り越して「危ない」、そんな言葉がぴったりな日も多い日本の夏。炎天下の屋外はもちろんですが、状況によっては屋内でも油断できません。熱中症は他人事ではなくなってきています。
そして2025年6月から、改正労働安全衛生規則により「熱中症対策」が企業にとって義務化されることになりました。今回は熱中症について、企業が備えるべき熱中症対策について解説します。
熱中症とは?
熱中症とは、高温多湿な環境で体温調節がうまくいかなくなり、体内に熱がこもった状態のことをいいます。
身体は汗をかいたり皮膚から熱を放出したりして体温を一定に保っていますが、暑さが過酷になってくるとこの機能が追い付かなくなり、体内の熱がうまく逃げずに蓄積されてしまいます。
症状は重症度によって変化します。
| 重症度 | 症状の特徴 | 症状 | 手当 |
| I度(軽度) | 熱失神、熱けいれん 初期のサイン(自覚しにくいこともあり) | 顔面蒼白、脱水 吐き気、めまい、立ちくらみ 急性筋肉痛、こむら返り | 冷所で安静 身体を冷やす 水分と塩分の補給 見守り |
| II度(中等度) | 熱疲労 身体の異常がはっきり出てくる | 頭痛、吐き気、嘔吐 気分不良、虚脱感 意識がぼんやりする 返答がおかしい | 医療機関での診察が必要 |
| III度(重度) | 熱射病 命に関わる危険な状態 | 意識障害、肝・腎機能障害 血液凝固異常 まったく汗をかかない 呼吸・脈が速い、けいれん | 入院治療(場合によっては集中治療)が必要 |
熱中症の特徴は下記3つです。
誰でもかかる
高齢者や子どもが特にかかりやすいですが、それ以外の年代の方でも発症します。
屋外作業はもちろん、空調のきいていない室内や社内でも起こるため、場所や年齢関係なくリスクがあります。
環境に左右されやすい
気温だけでなく、湿度や風の有無、服装、作業内容によっても熱中症のリスクは大きく変わります。
特に湿度が高いと汗がうまく蒸発せず、体温調整が効かなくなり、危険度が一気に上昇します。
急に重症化することがある
初期症状を放置すると、短時間で意識障害やけいれん、意識不明に陥るケースもあります。自覚症状が少ないまま進行することもあるため、周囲が異変に気付いて早めに対応することが大切です。
なぜ今、企業の熱中症対策が義務化されるのか?
近年、真夏日や猛暑日が続くのが当たり前になり、職場での熱中症リスクも年々高まってきています。
特に工場や屋外作業の現場では、命に係わることも少なくありません。
厚生労働省の令和5年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は1,106人(前年比279人・34%増)に達しており、うち死亡者は31人(前年比1人・3.3%増)となっています。
業種別でみると建設業、次いで製造業で多く発生しているようです。
死亡災害になった事例の多くで、暑さ指数(WBGT)を把握しておらず、熱中症予防のための労働衛生教育も行われていないことがわかりました。
労働安全衛生法および労働安全衛生規則では、事業者に対し「高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」としており、熱中症対策の義務付けは以前からされていました。
しかし、重症化する原因の多くが、「初期症状の見逃し」「対応の遅れ」であることが厚生労働省の分析で明らかになりました。
法令上、熱中症による健康障害の疑いのある者の早期発見や重症化を防ぐための対応については定めがなかったため、今回労働安全衛生規則が見直されることとなりました。
熱中症対策の具体的な義務化の内容・自分でできる熱中症対策
企業に義務付けられる熱中症対策
今回の労働安全衛生規則の改正により、第612条が新設されました。
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報 告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
出所:労働安全衛生規則
これにより、熱中症にかかるおそれのある作業を行う際には、企業に以下の3つの熱中症対策が義務付けられます。
1. 報告体制の整備
熱中症の自覚症状のある従業員や熱中症のおそれのある従業員を見つけた者が報告するための仕組み作りが求められます。
報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めるように推奨されています。
2. 実施手順の作成
熱中症のおそれのある従業員を把握した際に迅速に判断できるように、実施手順を事業場ごとにあらかじめ作成する必要があります。現場の実情にあった内容にしましょう。
(1) 事業場における緊急連絡網、緊急連絡先の連絡先および所在地など
(2) 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の手順の作成、および関係作業者への周知
3. 関係者への周知
上記1、2に関して、あらかじめ関係者(全従業員)に周知し、機能するようにしておく必要があります。
周知の仕方は朝礼やミーティング、会議室や休憩所などのわかりやすい場所への掲示、メールやイントラネットでの周知になります。
なお、義務化の対象となる「熱中症にかかるおそれのある作業」は具体的に「暑さ指数(WBGT)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業となります。
暑さ指数は環境省熱中症予防情報サイトで確認ができます。メール配信サービスもあるので簡単に情報を得ることも可能です。
対象となる事業場でなかったとしても、熱中症の疑いのある従業員の対応をあらかじめ決めておくことで、対応に困ることを低減することができるでしょう。
この企業の熱中症対策は、罰則付の義務規定となります。前述の1~3の対応を怠った場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。企業の安全配慮義務の一環として、必要な対策をしっかり講じましょう。
個人でできる熱中症対策
・ 水分をこまめにとる(のどが渇く前に):基本の水分摂取は水やお茶で対応しましょう。炎天下での作業やスポーツの場合は、経口補水液が有効です。
・ 体調の変化に気を付ける:「ちょっと気持ち悪い」「ボーっとする」「汗が異常に出て止まらない」などの異変を感じた時はすぐに日陰や涼しい場所に移動し休みましょう。重症化を防ぐために非常に重要です。
・ 暑い時間帯の外出や運動を避ける
・ 通気性の良い服や冷間グッズを活用:綿や麻の素材は吸汗・速乾性に優れます。最近ではファン付きウェアを導入する企業も多く、これがないと作業ができないといわれることも。首元を冷やす冷却タオルやネッククーラー、日傘や帽子なども活用しましょう。
・ エアコンを適切に使う:室温が28度を超えるなら冷房を使用しましょう。使用を我慢して熱中症を発症、病院を受診したり、入院したりという結果になると、仕事を休まないといけない、電気代よりもはるかに医療費がかかってしまうこともあります。また最悪の場合、脳や神経系、臓器に後遺症が残ることもあります。
・ 周囲にも声をかける:自分だけではなく、家族や同僚など周囲の体調にもお互いに気を配りましょう。体調が悪そうな人を見かけたら、声をかけ日陰や涼しい場所へ誘導しましょう。
熱中症セミナーのご案内
「産業保健新聞」運営元のドクタートラストでは、「企業での対策が義務化に!熱中症対策セミナー」を提供しています。
熱中症対策は企業側の取り組みだけでなく、従業員一人ひとりが知識を持ち、対策をすることが非常に重要です。
セミナーは、熱中症の基本からセルフケア、緊急時の対応まで広く網羅できる内容となっているので、社員研修などでぜひ活用ください。
詳細は以下特設サイトをご覧ください!
<参考>
・ 厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」
・ 厚生労働省「職場における熱中症予防情報」
・ 厚生労働省「令和5年『職場における熱中症による死傷災害の発生状況』(確定値)を公表します」
・ 厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」
・ 厚生労働省「第174回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)」
・ e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」
・ e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」