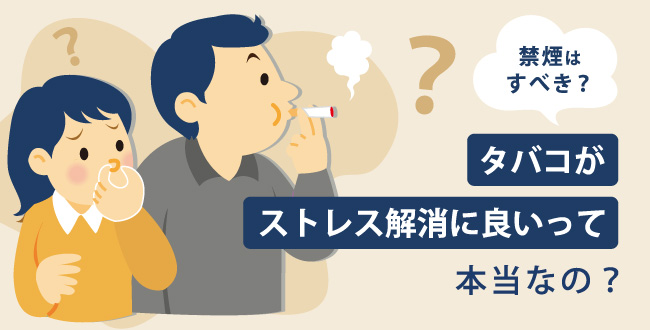新年度を迎えるにあたり、新しい職場や異動、転職をする方も多いと思います。
新しい生活を楽しみに思う気持ちもあれば、逆にうまくやっていけるかなと不安になることもありますよね。
経験したことのないことやわからないことも多く、周囲に質問しなければならない場面も多くなります。
その際に「こんな質問して良いのかな」「みんな忙しそうで話しかけにくい、申し訳ない」といった心配が出てくることもあるでしょう。
新しい環境や生活に馴染めず、仕事などのストレスも増大すると、そのことがきっかけとなり、不安や憂鬱な状態となり日常生活に支障が出る場合があります。
そのような状態を避けるために、積極的なメンタルヘルスケアが不可欠となります。
今回は新たな環境のストレスに対してのケアについて紹介します。
新しい環境にストレスを感じる原因と症状
厚生労働省が2024年10月に公表した「新規学卒就職者の離職状況」をみると、就職後1年以内の離職率は例年約10%、3年以内で約30%となっています。
退職する理由は人それぞれあるため、一概にはいえませんが、早期の退職につながるのは何らかのストレスを感じている方が多いのではないでしょうか。
新しい環境にストレスを感じる原因は以下になります。
・ 不確実性:期待されているかわからない、仕事の進め方がわからないなど
・ プレッシャー:早く仕事に慣れて成果を出さなければならないという焦り、失敗したら評価が低くなるのではないかという不安など
・ 過去のやり方とのギャップ:以前の職場環境・仕事のルールや文化が違う、自分の経験やスキルが活かせないなど
・ 人間関係:上司や同僚の性格がまだ掴めていない、相談相手がいない、飲み会やランチなどの社交的な場面で気をつかいすぎて疲れるなど
・ 環境の変化:通勤時間の変化、生活リズムの変化など
そしてストレスが過度にかかると、日常生活で以下のような症状が出てくることがあります。
・ イライラする
・ 涙もろい
・ 不安
・ 暴飲暴食する
・ 食欲が減る
・ 身なりに関心がなくなった、化粧をしなくなった
・ やる気が出ない
・ 仕事に行きたくない
・ 集中力が低下 など
セルフケア
個人差はありますが、新しい職場に馴染む、仕事に慣れるためにかかる時間は3~6か月程度といわれています。
そのため、最初はいつもよりストレスを感じてしまうこともあります。
いつも以上に心身の疲労回復のために、自分を労わる時間が必要です。
自分に合った対処方法を見つけ実践しましょう。
睡眠時間をしっかり確保する
睡眠時間が短くなると、メンタルヘルス不調を引き起こしやすくなるので、できる限り睡眠時間は毎日しっかり確保できるようにしましょう。
また、平日睡眠不足だからといって、休日に寝だめすると体内時計が乱れてしまい、社会的時差ボケが起こります。休日明けに倦怠感や日中眠気が出ることもあるので、休日の睡眠は平日より2時間以上ずれないように注意しましょう。
以前私が執筆した睡眠に関する記事があるので、ぜひ参考にしてください。
ストレス発散できる趣味などをつくる
仕事の性質と反対の活動はストレス発散に効果的といわれています。デスクワーク中心の仕事の方はアクティブな活動、身体を動かす仕事の方は室内での活動がおすすめです。
アクティブな活動:スポーツ全般、キャンプ、登山、ハイキングなど
室内での活動:読書、映画鑑賞、料理、手芸など
業務時間外は仕事のことを考えすぎないようにする
業務終了後も仕事のことを考えてしまうこともあると思います。
悶々(もんもん)と悩み続けると悩みに支配されてしまうので、ある程度時間を決めて考えるように意識付けしましょう。
また、頭の中で考え続けてしまうと脳のエネルギーを思った以上に使うため疲れてしまいます。
今考えていることや不安なこと、悩みなど紙に書きだしましょう。
誰かに聞いてもらうのでも良いです。
アウトプットすることで脳がすっきりするので、悩みは外に出しましょう。
毎日少しでも日記を書くのもオススメです。
新しい環境に慣れるように努力する
なんでも受け身でいるのではなく、自分からも率先して関係づくりに努める必要があります。
円滑なコミュニケーションが後の仕事のやりやすさにもつながってくるはずです。
自分から積極的に挨拶をするだけでも好印象を与えます。
仕事で関わる人の名前と顔を覚えるのも重要です。
わからないことをそのままにせず、勇気をもって質問しましょう。
時間が経てば経つほど質問しづらくなり、業務に支障が出る可能性もあります。
転職した方だと前職との違いに戸惑うこともあると思いますが、まずはその職場でのやり方を観察し柔軟に対応することも重要です。
ラインケア(上司や人事)
新卒者や転職者、異動者などを迎える側の上司や人事も、新しい環境に早く慣れてもらうためにサポートすることが重要です。
1on1を取り入れる
1対1で定期的に面談をする「1on1」はラインケアの最もポピュラーな手法の一つですが、非常に有効です。
上司と部下が1対1でコミュニケーションをとることができる場を定期的に作りましょう。1on1は評価するためではなく、部下が上司への悩みや仕事の状況などを伝えることが目的となっています。
業務の進捗状況だけではなく、体調面の確認も実施しましょう。
メンター制度
新卒者に対してメンター制度を導入している会社もあります。メンターとは新卒者や若手社員(メンティー)のサポートをする先輩社員のことを指します。メンターは仕事の指導役というより、精神面でのサポートをする役割が大きいです。
メンティー側はもちろんのこと、メンター側も地震のキャリア形成を考えるきっかけになったり、成長の機会になったりと双方にメリットがあります。
相談しやすい環境づくり
産業医や保健師など専門家によるサポート体制の構築も重要です。また外部の相談窓口を設置し周知することも効果的です。
相談先の選択肢がいくつかある方が、従業員にも安心感を与えます。
<参考>
・ 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」
・ 厚生労働省「こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」





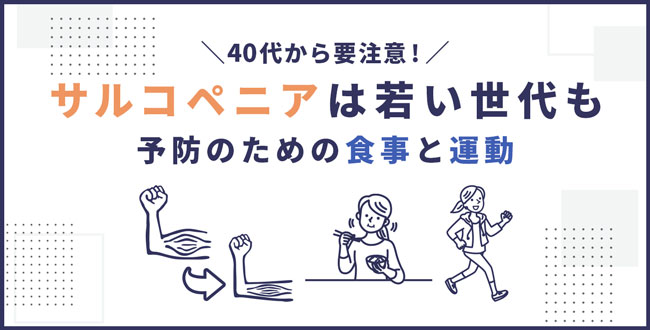
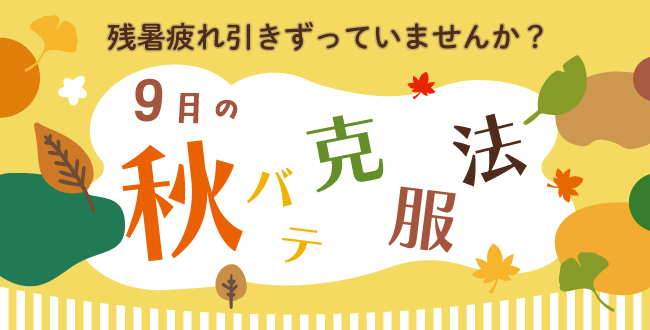

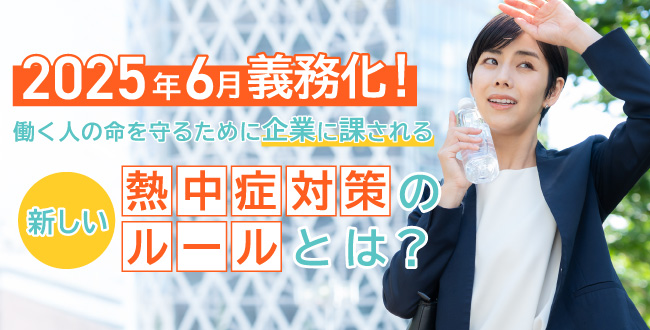








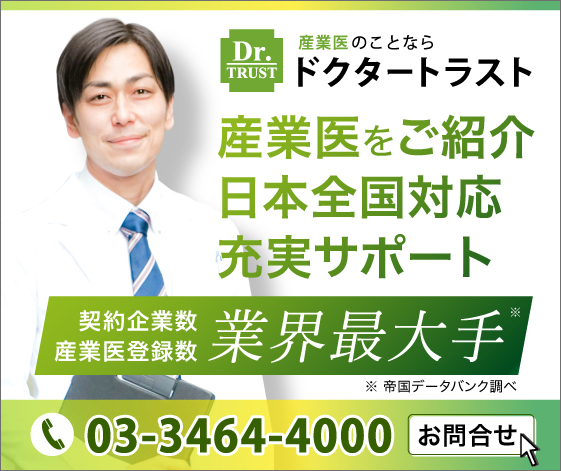


唐澤さん公益通報サムネ.jpg)