
暑い夏がやってくると冷たいビールやチューハイがおいしく感じられますよね。ビアガーデンやバーベキュー、お祭りなど屋外でお酒を楽しむ機会も増えてきます。
しかし、暑さとアルコールの組み合わせは身体に大きな負担をかけることもあります。飲酒による脱水や熱中症、飲みすぎによる体調不良などを引き起こす可能性があります。
今回はお酒の正しい付き合い方について解説します。
暑さとアルコールが重なると、なぜ危険なのか
夏はお酒が美味しく感じる季節ですが、暑さとアルコールの組み合わせは、私たちの身体にダブルの負担になってしまう場合があります。
夏場は他の季節よりも多く汗をかきます。これは体温調整のために必要な反応ですが、それによって水分や塩分が失われやすくなります。アルコールは利尿作用があるため、身体の水分が排出されやすくなります。
またお酒の分解にも水分が使われているため、お酒を飲めば飲むほど脱水のリスクが高まってしまいます。
加えて、アルコールには中枢神経を抑制する作用があり、運動機能や認知能力、判断能力などが鈍ることがあり、体調不良のサインにも気づきにくくなります。
発汗に脱水状態が続くと熱中症のリスクが高まるうえに、血中のアルコール濃度が上昇し、急性アルコール中毒のリスクが高まることもあります。
現場で実際に起きている飲みトラブル
東京消防庁の調査によると、急性アルコール中毒での救急搬送者数は2019年に18,000人を超えました。
新型コロナ感染症の影響で以降搬送者数は減りましたが、2023年は13,906人とまた増加傾向になっています。そして忘年会シーズンの12月と真夏の7月に搬送者数は多くなっています。
また、東京消防庁の「救急搬送データからみる日常生活事故の実態(令和5年)」で、19歳~64歳の事故事例において「ころぶ」事故は飲酒後の転倒が最も多くなっています。
そして重大なものになると飲酒運転による交通事故もあげられます。
飲酒後すぐに運転する(酒酔い運転)ことはもちろんですが、酔ってはいないが体内にアルコールが残っている状態で運転する「酒気帯び運転」も行政処分や罰則の対象です。
「自分は酔っていないから大丈夫」と思っていても、検査で「呼気中アルコール濃度0.15㎎/L以上」のアルコールが検出されるとアウトです。
酒酔い運転・酒気帯び運転になる人に車を貸すことや同乗すること、店側が酒類を提供することも運転者と同様に罰則が科せられることもあります。
会社における運転業務のアルコールチェックが義務化されているので、業務中に酒気帯び運転になることはないと思いますが、後述しているようにお酒が抜けるまでにかかる時間は個人差があるものの思ったよりも長いので、「自分は大丈夫」と思いこまないことが大切です。
また、警視庁「飲酒運転による死亡事故件数の推移」によると、2024年の飲酒運転の死亡事故率は飲酒なしの約7.4倍となっています。
翌日運転する予定がある場合は、飲酒時間や飲酒量を考慮する必要があります。
夏の「飲み方改革」ポイント
お酒で失敗しないために、楽しい気分で飲むために以下を意識しましょう。もちろん夏以外でも取り入れてみてください。
お酒と一緒に「水分補給」する
アルコールを飲むときは、水をこまめに挟むことで脱水状態を防ぐことができるだけなく、酔いも和らげることができます。お酒と一緒に水も頼みましょう。
屋外での飲酒は控えめに、こまめな休憩を
炎天下での飲酒は体温上昇を招きやすく危険です。日陰や涼しい場所で飲む、頻繁に休憩をとる、水分と塩分をしっかり補給することで熱中症を予防しましょう。
キンキンに冷えた飲み物ばかり飲まない
冷たいお酒ばかり続くと胃腸が冷えて、消化機能が低下します。夏でも時には常温の水や温かいスープなどで内臓を温めましょう。
食事と一緒にゆっくり飲む
空腹での飲酒は血中アルコール濃度を急上昇させます。食事と一緒にゆっくり飲むことで、アルコールの吸収が緩やかになり、身体への負担も軽くなります。
体調が悪い時は「飲まない」判断を
暑さとアルコールが重なる夏は楽しい反面、身体への負担が大きくなる季節です。その場の楽しさだけでなく、翌日やその先の健康も見据えた飲み方の選択が求められます。
体調が悪いといつもより酔いやすかったり、熱中症にもなりやすかったりするので、ノンアルコールを選択したり、飲み会の席は遠慮したりすることも必要です。
適量を心掛ける
過度なアルコール摂取は、脳細胞を傷つけるといわれています。特に記憶や学習に関与する海馬などで顕著です。また脳が萎縮するという報告もあります。飲酒量が増えすぎないように注意しましょう。
厚生労働省では節度ある飲酒は、純アルコール20g/日としています。
<1日あたりの適正飲酒量目安>
| お酒の種類 | 飲む量の目安 |
| ビール(5%) | 中瓶1本(500ml) |
| 日本酒(15%) | 1合(180ml) |
| 焼酎(25%) | 0.6合(約110ml) |
| ワイン(14%) | グラス2杯(約180ml) |
| ウイスキー(43%) | ダブル1杯(約60ml) |
| チューハイ(7%) | 350ml缶1本 |
参考:厚生労働省「アルコール」
アルコールが身体から抜けるまでの時間(目安)
アルコール分解にかかる時間は性別や体格、年齢など非常に個人差がありますが、目安は以下になります。
厚生労働省から出ているアルコールウォッチで自分がどのくらい飲んだか、アルコールを分解するのにどれくらいかかるかおおよその計算ができるので、ぜひ参考にしてみてください。
<アルコール分解にかかる時間>
ビール500ml(アルコール約20g):約5時間
ハイボール350ml(約20g):4~5時間
チューハイ350ml(14~36g):3~9時間
日本酒1合(約20g):約5時間
参考:厚生労働省「アルコールウォッチ」
<参考>
・ 東京消防庁「命に関わることもある「急性アルコール中毒」~正しいお酒の飲み方で、楽しい時間を~」
・ 東京消防庁「救急搬送データからみる日常生活の事故(令和5年)」
・ 警視庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」
・ 特定非営利活動法人ASK「急性アルコール中毒による搬送者数(1983年~)」
・ 厚生労働省「アルコール」
・ 厚生労働省「アルコールウォッチ」



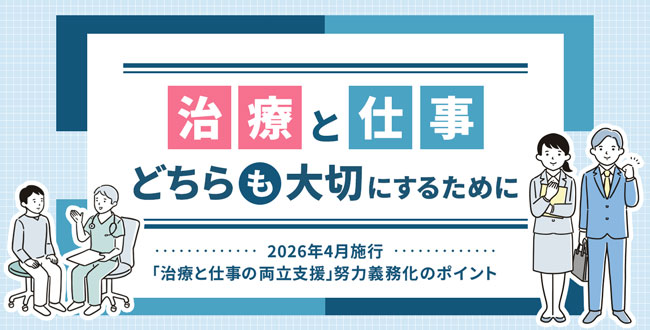

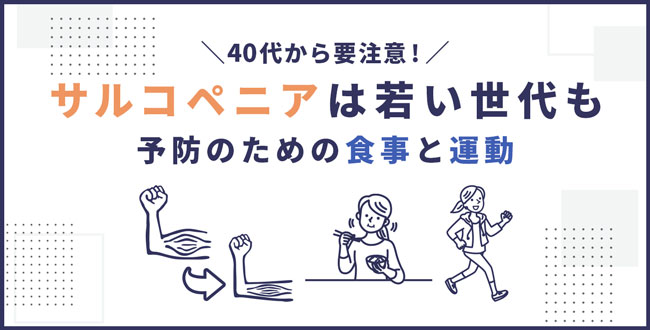
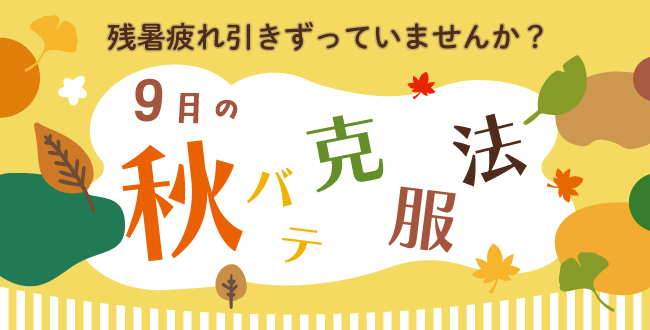
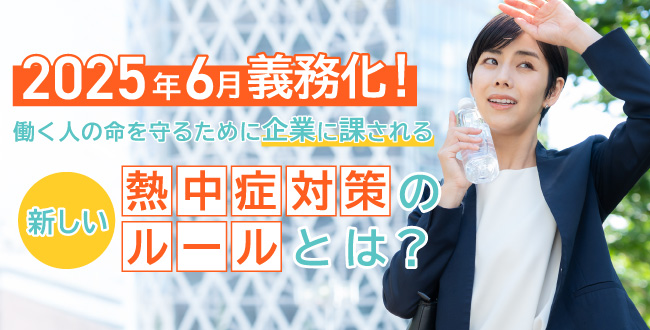











唐澤さん公益通報サムネ.jpg)

