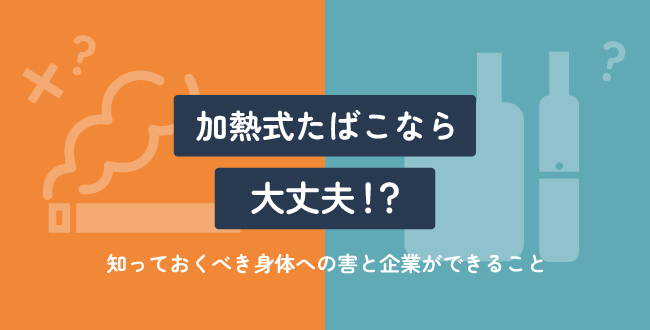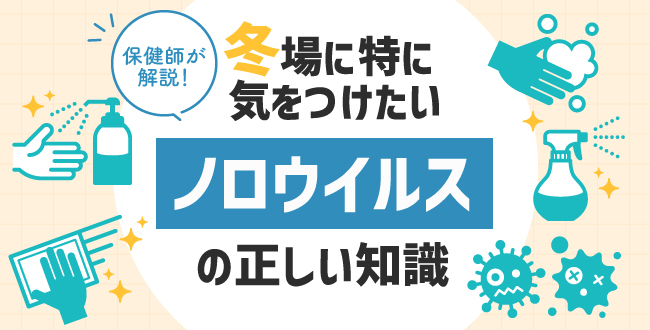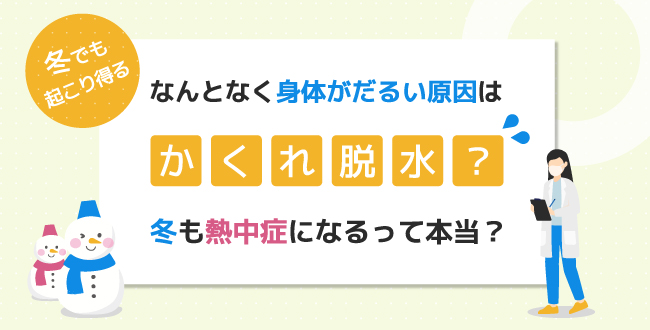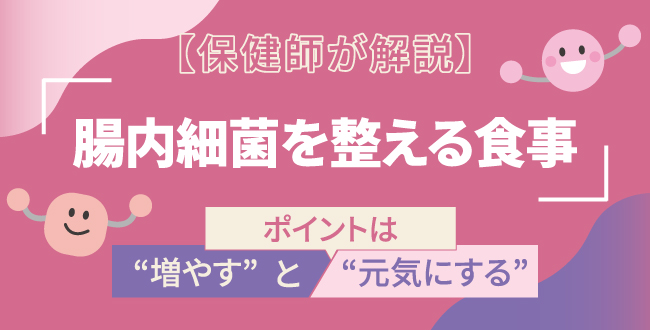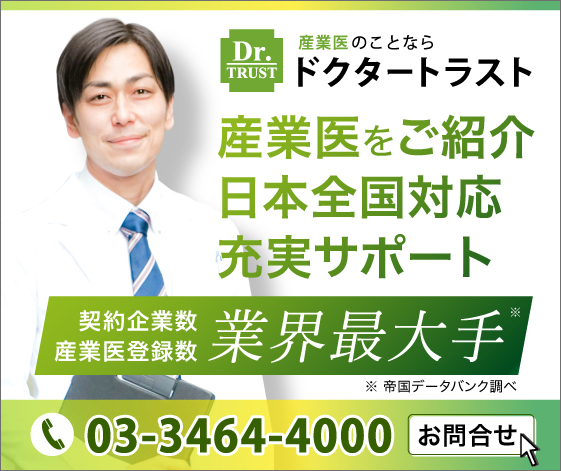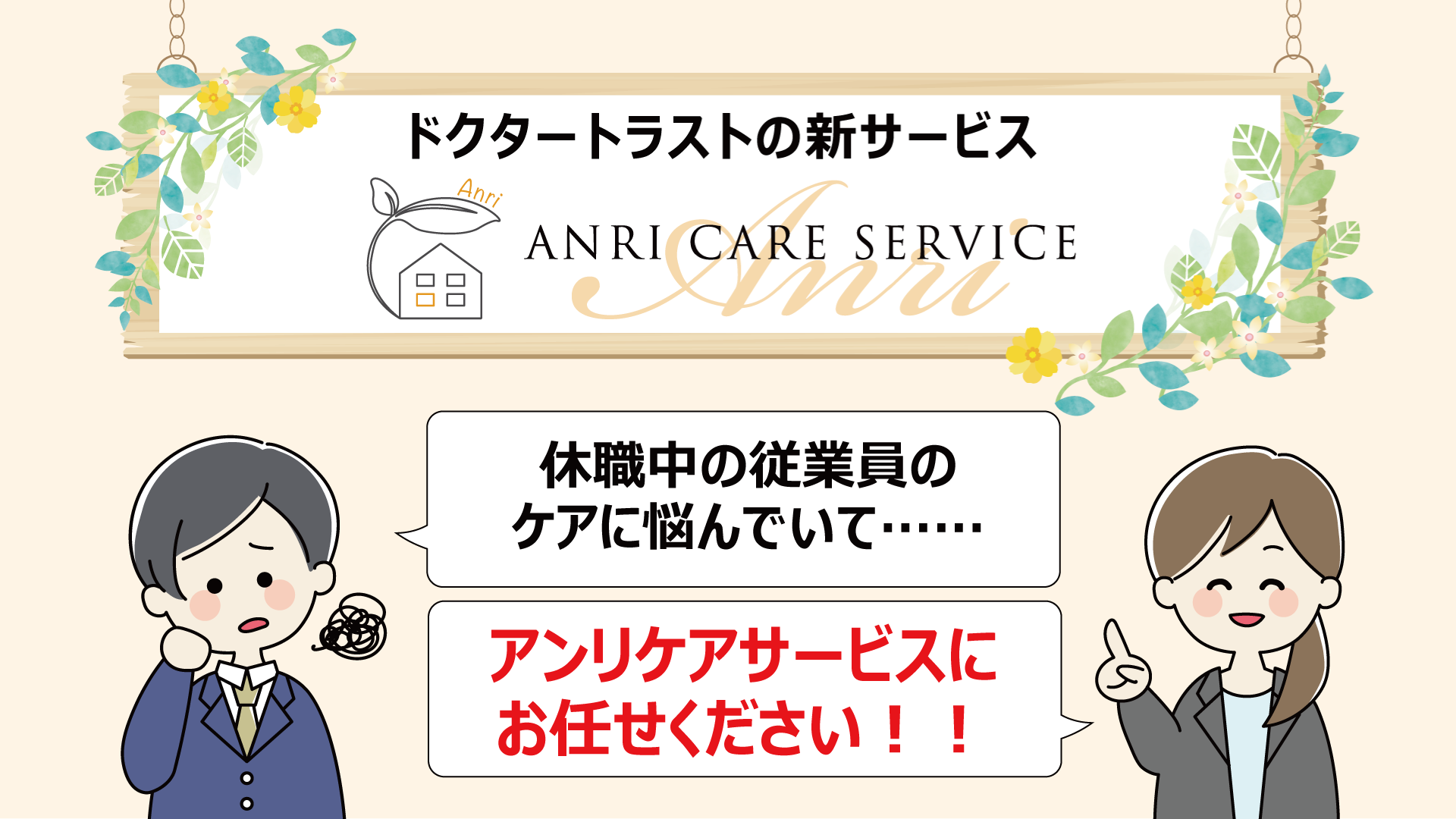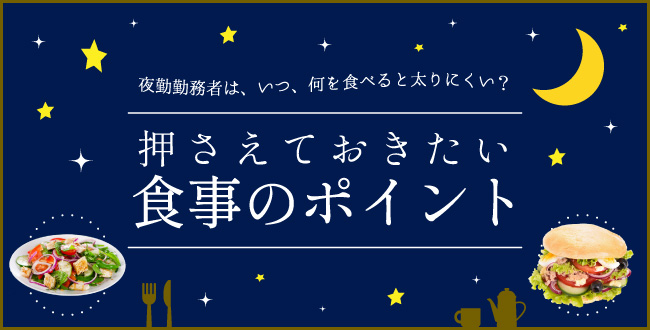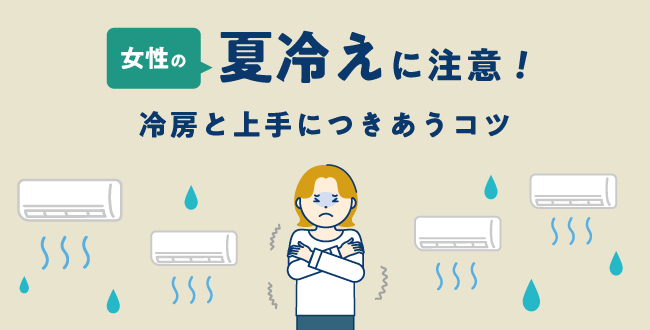
夏は暑さが厳しい季節ですが、特にオフィスや電車などでは冷房が効きすぎていることも多いですよね。
最近では、外の気温が30度を超えている日でも「冷え」を感じている人が増えており、私もそのうちの1人です。
特に、女性は男性より筋肉量が少ないので、体の中で熱を生み出せる量が少ないことや、ノースリーブや薄手のワンピースなど冷えやすい服装をする機会が多いため冷えを感じやすく、冷たいものを摂取するとより身体が冷えていくでしょう。
また、現代では入浴の際にシャワーだけで済ませる人も多く、体の芯から温まる機会が少なくなっているのも影響しています。
こうした習慣の積み重ねが、夏でも冷えを引き起こす大きな要因となっています。
夏冷えが引き起こす身体の不調
「冷え」は、血流悪化を招き、さまざまな体調不良のもとになります。
血液には、熱を運んで体温を調節する働きと、臓器に酸素や栄養を運び、二酸化炭素や老廃物を回収する働きがあります。
血流が悪化すると、内臓の働きも悪くなり、免疫力も低下します。
また、新陳代謝も低下するので、肌への影響や肥満などにもつながります。
以下に「冷え」が引き起こす代表的な症状を記載していますが、症状が1カ月以上続く場合や、急激に激しい症状が起こった場合は、別の病気が隠れている可能性がありますので、すぐに医療機関を受診してください。
<冷えが引き起こす主な症状>
身体面:肩こり、腰痛、頭痛、倦怠感、疲労感、むくみ、便秘、下痢など
美容面:抜け毛、白髪、くすみ、しわ、しみ、クマ、ニキビなど
心理面:イライラ、不安感など
また、女性の場合は、生理痛の悪化や月経周期の乱れなどの症状が出やすく、日常生活にも影響を及ぼすことがあります。
冷えがひどくなると、卵巣の機能が低下する可能性もあり、卵巣の機能が低下すると、女性ホルモンのバランスが崩れて、妊娠しにくい身体になることもあります。
さらに、身体が冷えた状態が続くと自律神経のバランスが崩れ、免疫力の低下や夏バテにつながるリスクも高まります。
冷房と上手につきあう4つの工夫
夏冷えを防ぐには、冷房との付き合い方とセルフケアを見直すことが大切です。
以下の4つのポイントを意識することで、体を冷やし過ぎず、快適に夏を過ごすことができます。
1.冷房の設定温度と風向きを工夫する
冷房の温度は25〜28℃が目安です。
外気との温度差を5℃以内に保つと、自律神経の負担が少なくなります。
また、風が直接体に当たらないように風向きを調整することも大切です。
2.羽織りものやひざ掛けを常備する
職場や外出先では、冷房対策としてカーディガンやストール、ひざ掛けを用意しておくと安心です。
特にお腹や足元は冷えやすいので、意識的に守りましょう。
また、オフィス内だけでも靴下を履くのがおすすめです。
3.身体を温める食材や飲み物を取り入れる
冷たい飲み物を摂り続けていると内臓が冷えてしまうため、白湯や生姜入りのお茶など、体を温める飲み物も取り入れましょう。
食材では、生姜やにんじん、れんこん、ネギ、ニンニク、ごぼうやほうれん草などの野菜、味噌、納豆などの発酵食品、肉や魚などのタンパク質食材、ビタミンEが豊富なナッツ類やアボカドがおすすめです。
4.湯船につかって体を温める
湯船につかることで、副交感神経が優位になり、リラックスできます。
38〜40℃のぬるめのお湯に10〜15分浸かるだけでも、血行が良くなり冷えの改善にも効果的です。
ただし、42度を超える温度は交感神経が優位になるため、ぬるめの湯を意識しましょう。
おわりに
「夏冷え」を防ぐことは、単に身体を温めるだけでなく、心身のコンディションを整えることにもつながります。
熱中症を予防するために冷房は必要ですが、うまく温度をコントロールしたり、「冷え」から身体を守るために、セルフケアを行ったりすることが大切です。
年々暑くなる夏を元気に過ごすために、今日からできる「冷え対策」をぜひ始めてみましょう。
<参考>
・女性の健康推進室ヘルスケアラボ「冷え」
・働く女性の心とからだの応援サイト「冷え対策!体をあたためる食材、冷やす食材」