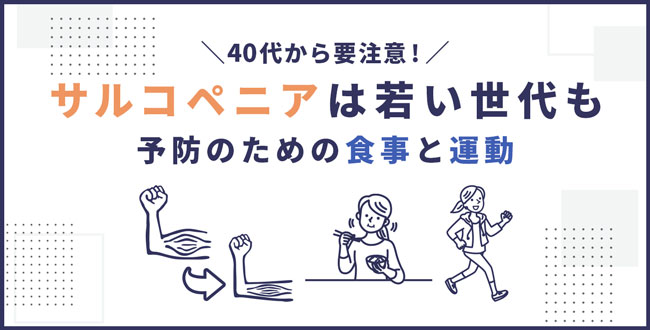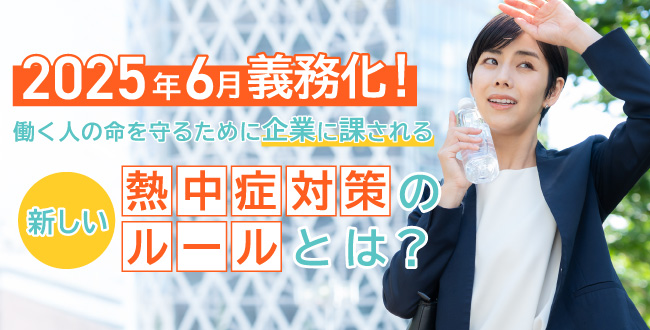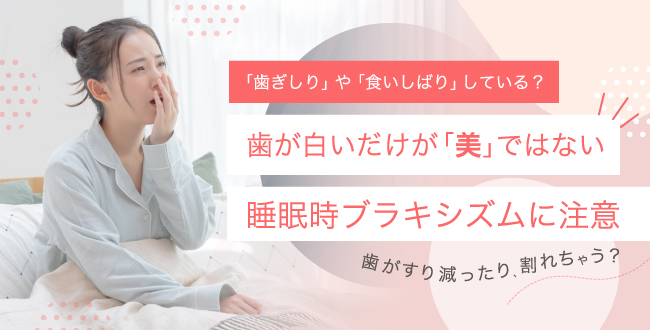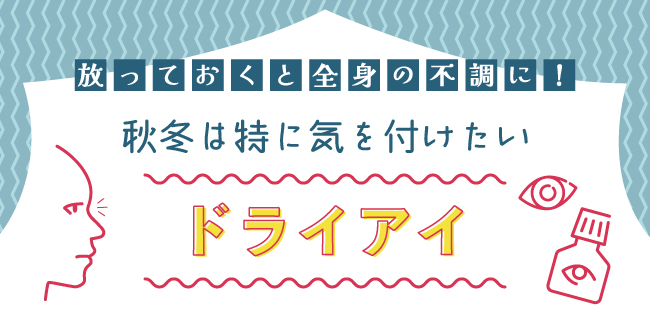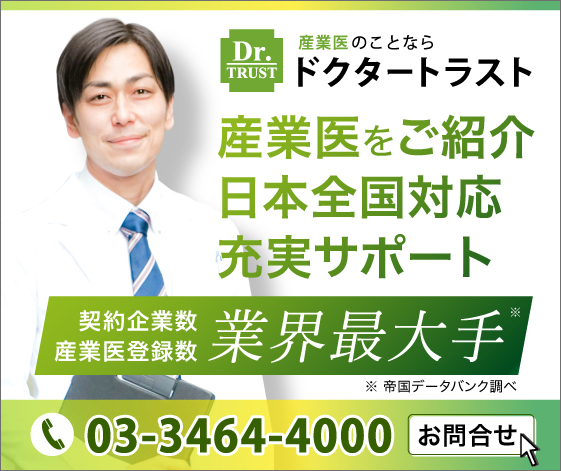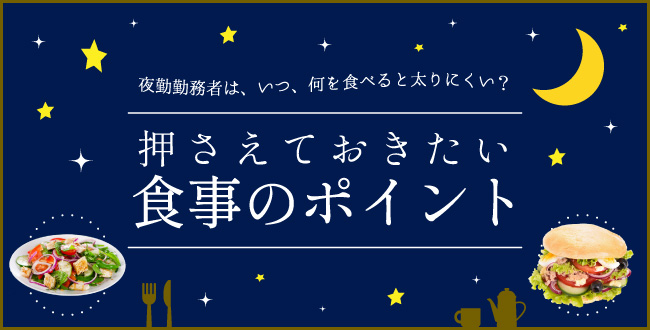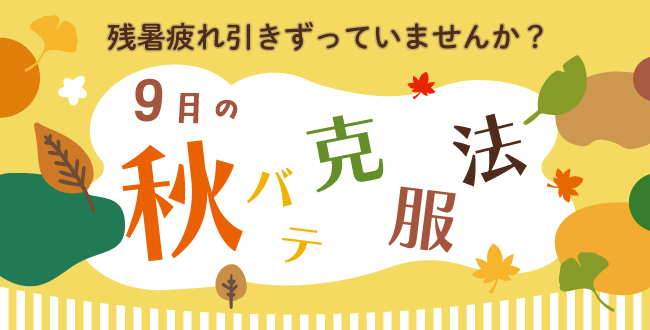
9月といえば秋の気配が感じられるはず……ですが、ここ数年は夏がずっと続いているような暑さですよね。日中は真夏のような日差しで、夜になっても蒸し暑さが残る日も多いです。
夏の延長戦こそが、私たちの身体にじわじわとダメージを与えています。
なんとなく身体がだるい、寝つきが悪い、食欲が戻らないなどの症状が出ている場合、秋バテかもしれません。
秋バテを起こさないように、今すぐ始められる対策について解説します。
なぜ9月に夏バテのような症状が起きるのか?
「夏バテ=真夏に起きる」というイメージを持つ人が多いですが、最近の気象を考えると9月こそ注意が必要な時期になります。
その理由は大きく3つあります。
長引く暑さと高湿度
気候変動などの影響で、近年は9月でも真夏日や熱帯夜が続くことは珍しくありません。
特に都市部ではヒートアイランド現象も加わって、夜になっても気温が下がりにくい状態になります。
夏の気候が続くことで身体は休まる暇がなく、疲労も蓄積しやすくなります。
自律神経の乱れ
日中30度以上に気温が上がる一方、朝晩は20度近くまで下がる日もあります。
この寒暖差が自律神経に負担をかけます。
自律神経とは呼吸や発汗、血液循環、体温調節といった、普段私たちが無意識に行っている働きを調整している神経のことです。
この自律神経が乱れると体温調整や睡眠のリズムが乱れやすくなるなどあらゆる不調が出現します。
夏の生活習慣の影響
冷たい飲み物や食事、冷房の効いた室内での長時間の生活は、胃腸の働きを弱め、血行不良や体の冷えを招く可能性があります。
また、冷たい麺類などで簡単に済ませることも多いと思います。
そういった夏の食生活の乱れによって、栄養が偏りがちになり体調を崩しやすくなります。その影響は8月を過ぎても続き、9月の体調不良につながります。
9月の秋バテは夏の疲れ+残暑+寒暖差のトリプルパンチとなります。そのため、自分自身を労わることが非常に重要です。
秋バテの症状とサイン
秋バテはじわじわと長引く不調が特徴です。次のような症状が出ている場合は秋バテの可能性があります。
・ 朝起きて疲れが抜けていない感じがする
・ 食欲がなく、冷たいものばかり欲しくなる
・ 胃もたれや下痢、便秘などの消化器症状がある
・ 頭痛やめまいが増えた
・ 手足の冷えやむくみが気になる
・ 気分が落ち込みやすく、集中力が続かない など
これらの症状は自律神経の乱れや消化器官の機能が低下しているサインです。
特に9月は夏の疲れで免疫力も下がっているため、軽い不調が風邪や感染症などに発展することもあります。
また、精神面にも影響が及びやすいのも特徴です。
夏の間は「暑いから仕方がない」と割り切れた不調も、残暑が長引くと気分が落ち込み、やる気の低下やイライラが増えてしまうこともあります。
秋バテの克服方法
秋バテかもしれないと思ったら、生活習慣を見直しましょう。
朝日と温かい朝食でリズムを整える
朝起きたらカーテンを開けて日光を浴び、体内時計をリセットしましょう。
朝食は温かいスープや味噌汁など、消化が良く身体を温めるメニューを取り入れましょう。
栄養は「温・補・整」を意識
冷たい飲み物や生野菜ばかりではなく、温かい料理で胃腸を労わりましょう。
たんぱく質と疲労回復に役立つビタミンB群や鉄分をバランス良く摂取するとより効果的です。
発酵食品で腸内環境を整えるのも胃腸の動きを改善できます。
たんぱく質が入っている食品:魚、肉(脂肪分が少ないものがベスト)、卵、豆類
ビタミンB群が豊富な食品:豚肉、玄米、うなぎ、魚介類、キノコ類、アボカド、納豆
鉄分が含まれる食品:赤身肉、ほうれん草、ひじき、ごま、プルーン
たんぱく質やビタミンB群はまとめて一度に摂取するよりも1日3食でこまめに摂取するのがポイントです。
身体は一度に大量のたんぱく質を使いきれず、筋肉や代謝の維持には分散して補うほうが効率的です。
また、ビタミンB群は体内でため込むことができないため、こちらも毎日こまめに摂取することをオススメします。
鉄分はビタミンCの豊富な食品と一緒に摂取すると鉄吸収を促進させます。
湯船にゆっくり浸かる
シャワーで済ませる方も多いですが、湯船にしっかり浸かることは自律神経にとってとても重要です。
38~40度のお湯に10~15分程度浸かることで、副交感神経が優位になり、睡眠の質が向上します。
冷房や冷たい飲食で冷えた身体を内側から温める習慣をつくりましょう。
運動を取り入れる
ウォーキングやストレッチなど、無理のない運動で血行を促進し自律神経を整えます。
特に朝や日中の運動は身体のリズムを整える効果が高くオススメです。朝日を浴びると幸せホルモン「セロトニン」の合成が促進され、自律神経を整えてくれます。
寒暖差対策をする
残暑でオフィスでは冷房が入っていたり、朝夕は冷え込みを感じたりすることも多いですが、気温の変動が激しいと自律神経に悪影響を及ぼします。
自分でも寒暖差を調節できるように衣類や寝具で対策をとるようにしましょう。
9月は暑さと涼しさが交錯する季節です。生活リズムを整えて身体を温め、栄養をしっかり取ることで、残暑疲れは軽くなります。
ちょっと体調優れないなという方はぜひ上記で取り入れられそうなものを今日から始めましょう。
<参考>
・ 株式会社ツムラ「【医師監修】その症状、秋バテかも!? 原因や対策、解消法などをご紹介」
・ 社会福祉法人恩賜財団済生会「心と身体がしんどい原因は、自律神経?!」
・ 一般社団法人奈良県医師会「『秋バテ』ってどんな病気?対策は?」