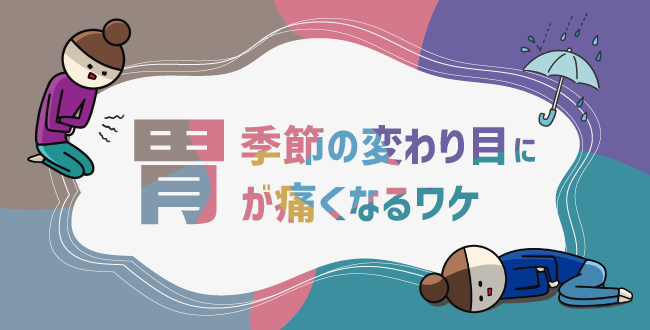9月1日は防災の日~体験から学ぶ「もしも」への備え~
- 2025/9/1
- 災害

毎年9月1日は「防災の日」です。
防災の日は台風や地震など自然災害に備えて、内閣府が1960年に防災意識を高めることを目的として制定しました。
なぜ9月1日が「防災の日」なの?
1923年9月1日に東京都、神奈川県を中心とする関東大震災が発生しました。
死者・行方不明者は10万人以上にのぼります。
昼食事の時間だったことから火を使う家庭も多く、火災による死者が9.2万人と大部分を締めました。
また、台風シーズンを迎える時期であり、1959年に発生した伊勢湾台風によって戦後最大の被害を被ったことが契機となり、地震や風水害等に対する心構えを育成するため、1960年に防災の日が創設されました。
防災の基本3原則とは?
災害時に被害を最小限に抑えるための3原則として「自助」「共助」「公助」という考え方があります。
自助:自分自身が自分の命と財産を守るため、日頃から防災対策を講じること
共助:地域や職場の仲間、近隣住民同士が協力し合い、助け合うこと
公助:消防、警察、自衛隊、地方公共団体などの公的機関による支援
これら3つは互いに補完し合う関係にあり、円滑な連携が災害に強い社会の構築に不可欠とされています。
ただし、大規模な災害が発生した場合は、公的機関も被災者となり、「公助」の面では十分な支援を受けられない可能性があります。
阪神・淡路大震災では、救出された人の約9割が自助や共助によるものでした。
公助だけに頼るのではなく、自分の身を守る「自助」と、近隣の人々と助け合う「共助」がより重要であることが、過去の災害からもわかります。
災害への備えをしよう
首相官邸サイトでは、災害が起きる前に準備ができることとして、5つのことが紹介されています。
上記でいう「自助」の部分にあたります。
・ 家具の置き方の工夫
・ 飲料・食料の備蓄
・ 非常用バッグの準備
・ 家族の安否確認方法
・避 難場所や避難経路の確認
どれも簡単にできることに感じると思います。
特に飲料・食料の備蓄や非常用バッグの準備以外は費用も掛からず、今からでも備えができるものになりますが、それゆえすぐに行動に移せない人が多いのではないでしょうか。
かく言う私も今まで大きな災害にあったことがなく、テレビで毎年のように災害報道を聞いても身近に感じることが難しく、未だにテレビの世界のように他人事に感じます。
防災を体験できる場所やイベントに行ってみよう!
全国各地に防災体験ができる施設やイベントがあります。
たとえば、東京消防庁が運営する防災館(池袋、立川、本所)では、地震や火災などの疑似体験が可能です。
東京臨海広域防災公園内にある「そなエリア東京」では、72時間生き抜くための知識を学べる体験ツアーが人気です。
変わった防災イベントとしては、音楽フェスと防災訓練を組み合わせた「防災ミュージックフェスティバル」や、渋谷を舞台に「もしも」の時に何ができるかを考える「もしもFES渋谷」などがあります。
これらのイベントは、楽しみながら防災意識を高め、実践的な知識やスキルを習得できる点が特徴です。
このような防災施設は各地域に多く存在しています。
まとめ
たくさんの大震災を経験した日本でも、時間が経てば防災や災害への意識が薄れてしまうことも多くあると思います。
災害に対する備えが必要とわかっていても、行動に移すためには何かのきっかけが必要です。
それが「防災の日」なのではないかと私は考えます。
実際に私も防災の日について調べていく中で、防災施設に興味が湧き、実際に訪れてみようと思いました。
皆さんにとって、この記事が防災へのキッカケのひとつになれば幸いです。
<参考>
・首相官邸「災害が起きる前にできること」






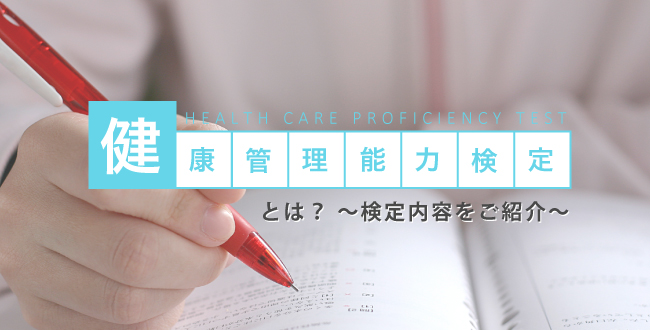

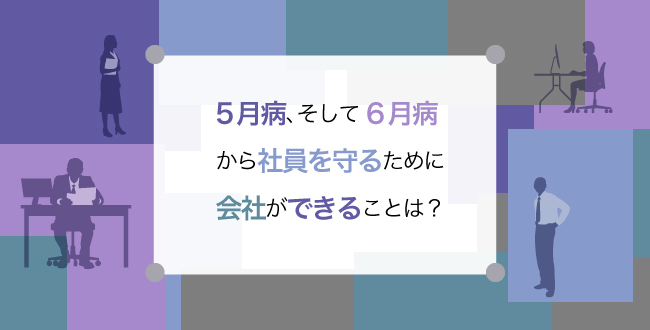


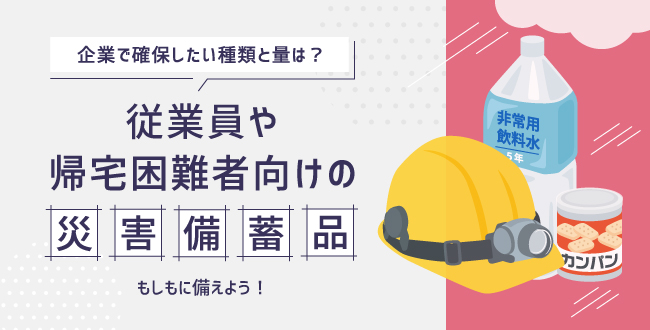

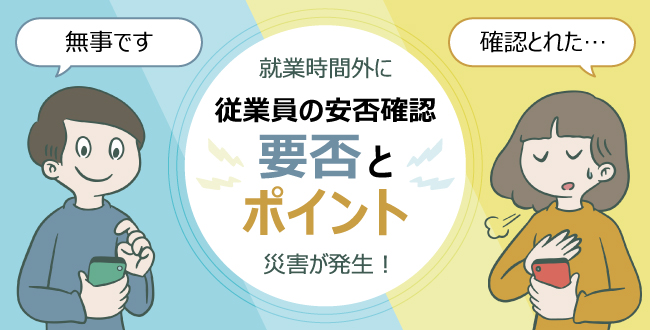


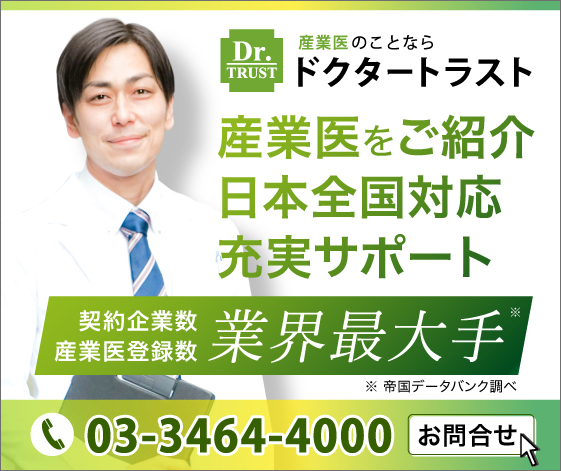


唐澤さん公益通報サムネ.jpg)