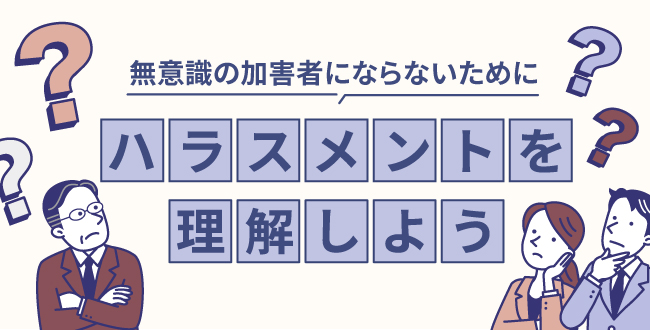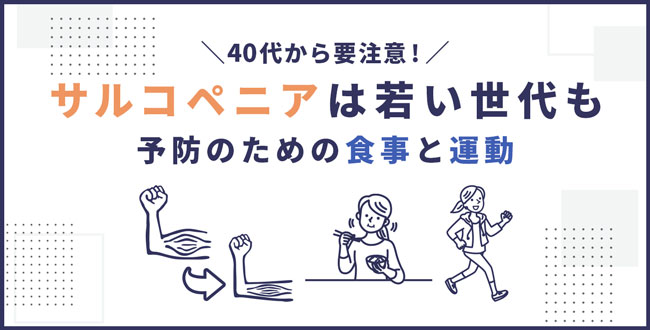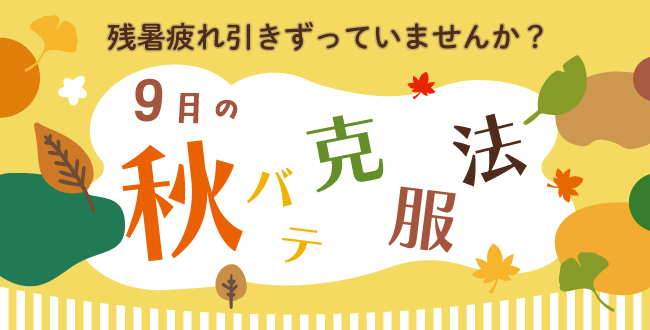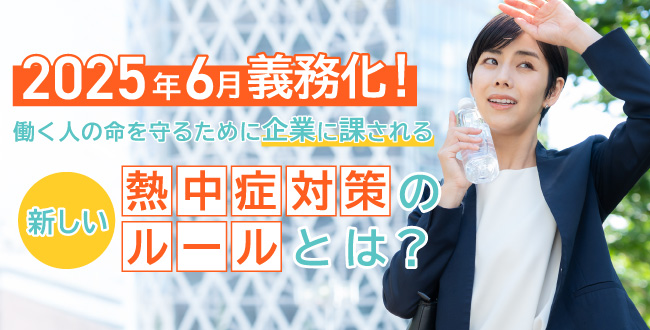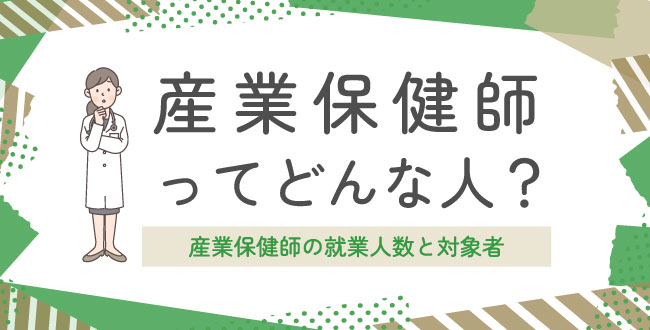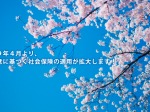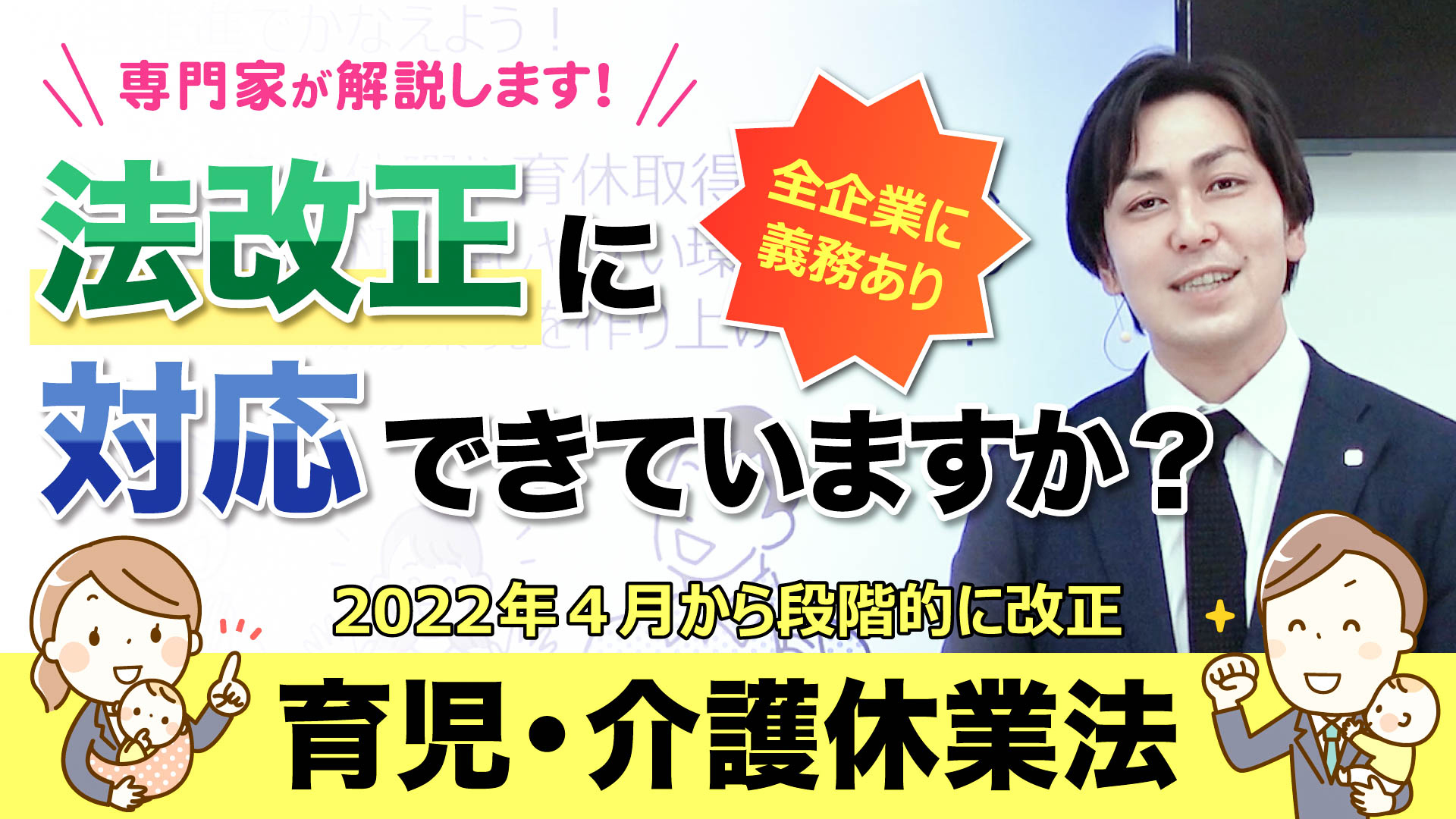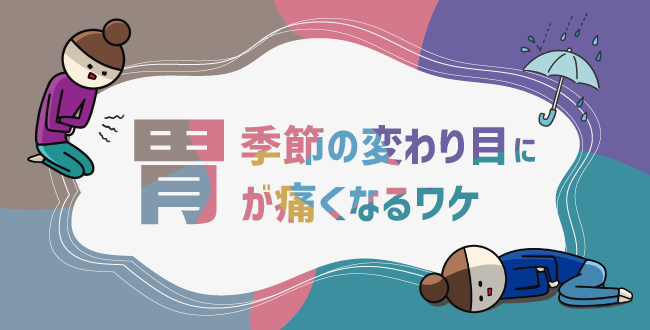- Home
- コミュニケーション, 保健師
- 対立しない、でも譲らない!アサーティブコミュニケーションを身につけよう

学校や仕事場、家族などさまざまな人間関係の場面でコミュニケーションは必要ですが、その難しさを感じることは誰にでもあるのではないでしょうか。
「自分の意見がなかなか言えない」「つい強い口調で伝えてしまう」「他者と関わることにストレスを感じる」などそれぞれ悩みがあると思いますが、その悩みを軽減するためのコミュニケーションとして注目されているのが、「アサーティブコミュニケーション」です。
以前執筆した『無意識の加害者にならないためにハラスメントを理解しよう』という記事でアサーティブコミュニケーションが有効とご紹介しました。
今回は、一歩踏み込んで、アサーティブコミュニケーションがどのようなコミュニケーション術であるかを詳しく解説します。
アサーティブコミュニケーションとは?
アサーティブコミュニケーションとは、自分の意見や感情を正直に、かつ相手を尊重しながら伝えるコミュニケーションスタイルの一つです。
アサーティブ(Assertive)とは「自己主張する」という意味ですが、一方的に自分の主張を述べることではありません。
攻撃的でも受動的でもない、バランスの良いコミュニケーションとなるため、相手を不快にさせず、自分もストレスを感じずに意見交換ができるものとなります。
アサーティブコミュニケーションを身につけることで得られるメリットは以下です。
人間関係が円滑になる
自分の意見を伝え、相手の意見も尊重する姿勢が生まれるので、信頼関係を築くことができます。
会話がうまくいくことで誤解や対立も減るため、働きやすい職場環境の形成にもつながります。
自己肯定感の向上・自己成長につながる
自分の気持ちや意見を表現することで無理に我慢する機会が減り、「自分を大切にできている」という感覚を得られます。
また、自分自身を素直かつ肯定的に捉える機会が増えてきます。
さらに、相手からのフィードバックを受けることで、新たな視点や学びも得られます。
生産性が向上する
自分の業務量の限界やタスク状況などを伝えられることで、情報共有もスムーズにでき、業務分担の調整もしやすくなります。
過剰な業務負担が防げたり、重要な業務に集中できたりします。
3つの自己表現タイプ
自己表現には3つのタイプがあります。
(1) 攻撃的自己表現(アグレッシブ)
攻撃的自己表現(アグレッシブ)とは、相手の感情や意見、立場を無視し、自分の気持ちや考えを伝えることが最優先な姿勢を持ったコミュニケーションを指します。
言葉だけではなく、場面に合っていない大きい声や鋭い視線、攻撃的な身振りなども含まれます。
この表現は相手を委縮させたり、嫌がられたりするので、感情コントロールも学ぶ必要があるでしょう。
(2) 非主張的自己表現(ノンアサーティブ)
非主張的自己表現(ノンアサーティブ)とは、主張をすることなく受け身に徹するアグレッシブとは真逆の自己表現のことです。
弱々しい声や視線を合わせないなどもこれにあたります。
過度に対立を恐れたり避けたりするので、無理な主張や間違ったことでも受け入れてしまいます。
そのような状態が続くと、ストレスやフラストレーションがたまり、メンタル不調に陥ることもあります。
ただし、「言わない」というのももちろんひとつの選択なので、「後で振り返ったときに自分が後悔しないか」と考えてみましょう。
(3) アサーティブな自己表現(アサーティブ)
前記「アサーティブコミュニケーションとは?」のとおり、アサーティブな自己表現(アサーティブ)とは、自分も相手も尊重する表現方法です。
落ち着いた声で、相手と目を合わせてリラックスした姿勢で関わります。
互いに納得できる結論や解決策を導きだすことができるのは、この自己表現になります。
性格は変えられないが、伝え方は変えられる!4つのポイント
アサーティブコミュニケーションを実践するためには以下の4つのポイントを意識しましょう。
① 誠実
自分の感情や考えを隠さず、正直に表現することを大切にしましょう。
その際、態度と言葉選びを心がけます。
相手と主張や意見が食い違っても、攻撃的に反論する、自分を押し殺して無条件に賛同することは避けましょう。
・伝える内容と表情は一致させる
・無理をする前に「これ以上は難しい」と伝える勇気をもつ
・感情を具体的に言語化する
(例)
✕「(本当は嫌だけど)別に大丈夫だよ」
〇「今は少し疲れているので、あとでお願いしたいです」
② 率直
回りくどい表現は避けて、具体的にわかりやすく伝えましょう。
・ポジティブなフレーズを意識する
・Iメッセージを使う(自分を主語にした表現)
(例)
✕「(あなたは)何回言えばミスがなくなるのか」
〇「(私は)こっちの方法でやってみると、うまくいくと思うよ」
・具体的な行動や事実を伝える
(例)
✕「最近仕事が雑だよ」
〇「前回のレポートで数か所(具体的な個所を提示し)データミスがあったので、次回はもう少し確認をお願いしたいです」
③ 対等
上司部下、先輩後輩など、立場の違いや力関係に左右されることなく、対等な関係での意見交換が重要です。
上司や先輩などの立場の者がより意識することで、部下や後輩はリラックスした気持ちでコミュニケーションができるでしょう。
・相手の話を最後まで聞く
・共感する
・批判ではなく提案をする
④ 自己責任
自分の感情や行動に責任をもってどのような結果になっても「自分軸」の意識を持ちましょう。
「言った責任」は、相手だけではなく自分にもあるという自覚は必要です。
そして、「言わなかった責任」も自分が引き受けます。
・自分の感情をコントロールする
・問題が起きたときに責任を共有する
・謝罪や感謝を忘れない
上記のポイントは、すぐに習得できるほど簡単なものではありません。
焦らずに日常のちょっとした会話で試してみたり、家族や友人など信頼できる相手と練習したりすることで身につけましょう。
また、「私の言い方で気になるところがあった?」と相手に確認することで、自分では気づかない改善点が見つかるかもしれません。
相手の主張がわかりにくかったり間違っていたりしても、「全然わからない」「全然違う」という言い方ではなく、「そういう考え方もあるけど、○○はどうか」「私の理解力が足りないかもしれませんが」など、相手を尊重し柔らかい表現を使うよう心がけてみましょう。
また、忙しいときに頼まれ事をされても「今日は無理です」と突っぱねるのではなく、「明日なら(○日後なら)大丈夫です」など、ポジティブな言い方を選ぶほうが印象も良くなります。
私自身も日々コミュニケーションの難しさを実感します。
ぜひ一つずつ取り入れてみて、自分の強みになるように一緒に頑張りましょう!