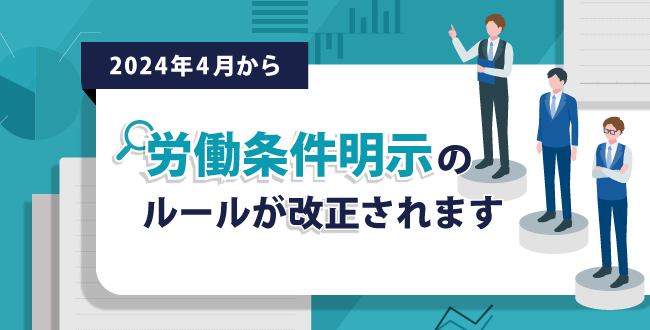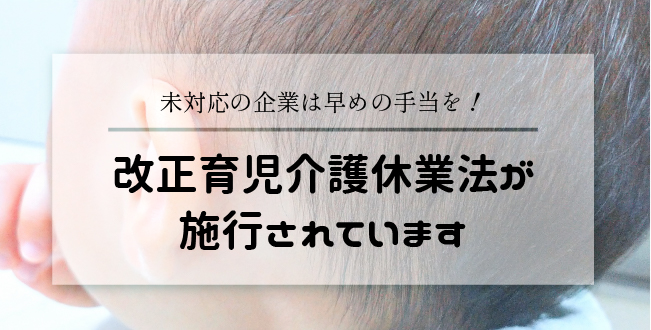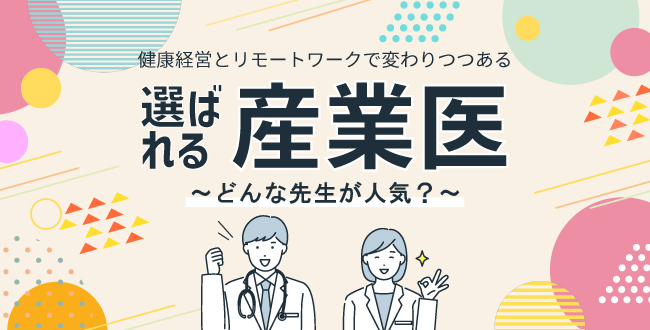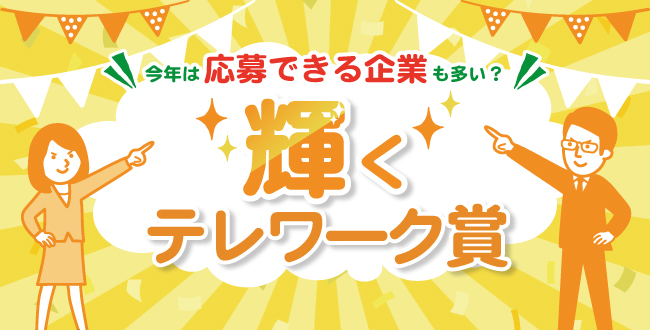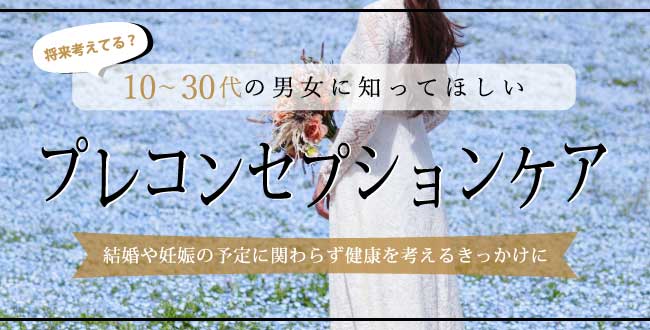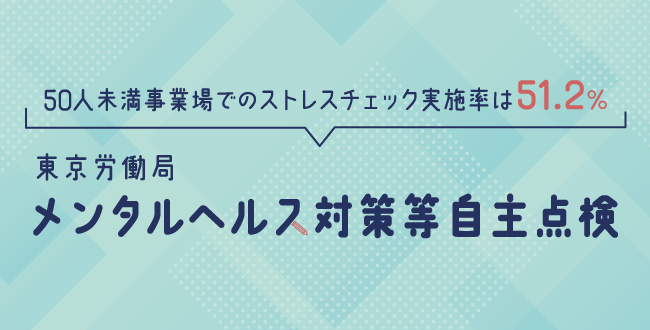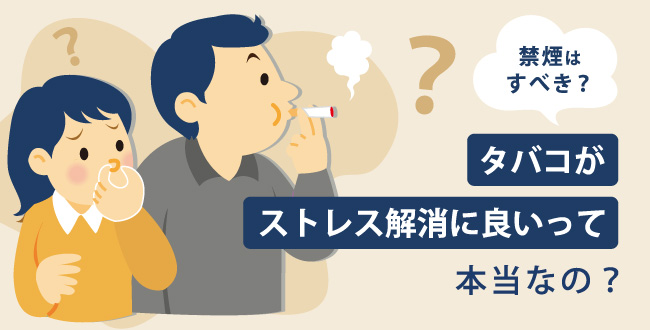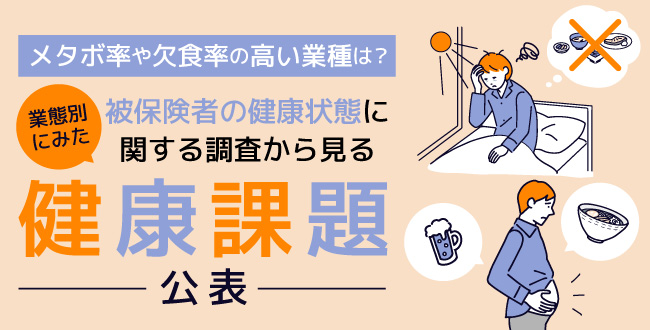
2024年11月、健康保険組合連合会は「令和4年度 業態別にみた被保険者の健康状態に関する調査」の結果(以下、本調査結果)を公表しました。
本調査は、業種ごとに異なる健康リスクや課題を明確化し、今後の健康政策や職場環境の改善に活用するために行われるもので、今回は2022年度の特定健診・特定保健指導データおよびレセプトデータをもとに業態別に被保険者の健康状態や服薬の状況、メンタル系疾患の有病者割合をまとめています。
健康状態および服薬状況は40~74歳の被保険者の特定健診の問診回答と健診検査値をもとに出され、メンタル系疾患の有病者割合は全年齢の被保険者を対象としています。
生活習慣、健康状態、医療受診状況、健診検査値の特徴が業態別に比較・分析されているほか、単なる統計分析にとどまらず、性別や年齢層別の健康課題も詳細に掘り下げられている点が特徴です。
本記事では、調査結果などをわかりやすく解説します。
調査結果
「第一部 生活習慣」では、生活習慣に関する調査結果が紹介、以下のように業態ごとに異なる生活習慣の特徴が明らかになりました。
宿泊業・飲食サービス業:「朝食を抜くことが週に3回以上ある」と回答した割合が全体では23.0%に対し、31.3%と高いことや、「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」と回答した割合が全体は34.1%に対し、52.6%と高い。
労働者派遣業:「1日あたりの飲酒量が3合以上」と回答した割合が全体は4.8%に対して9.3%と高いことや、「20歳時の体重から10㎏以上増加している」と回答した割合が全体の43.4%に対して57.0%と高い。
電気・ガス・熱供給・水道業:「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している」と回答した割合が全体24.4%に対して29.1%と高いことや、「睡眠で休養が十分とれている」と回答した割合が全体では62.4%に対して70.8%と高い。
宿泊業・飲食サービス業はシフト制などで生活リズムが乱れやすいことから、食習慣に関しても影響が考えられます。
一方で、電気・ガス・熱供給・水道業に関しては、ほかの業種よりも運動習慣があり、睡眠休養感も高い人が多いという結果でした。
「第二部 健康状態」では、生活習慣病リスクなどが紹介されています。
建設業、労働者派遣業:肥満該当者の割合が全体では43.1%に対して、建設業51.9%、労働者派遣業51.6%と過半数を占める。なお、建設業は「メタボリックシンドローム」該当者の割合も23.4%で、約4人に1人の割合である。
飲食料品小売業:「受診勧奨判定値」の血圧の割合が全体では20.3%に対して、30.8%と10%以上高い。また、脂質の割合が全体では31.2%に対して35.1%と高い。
さらに、「第三部 医療受診状況」によると、「血圧を下げる薬」を使用している割合は全体で18.0%だったのに対して、建設業では23.3%と高いことがわかりました。
建設業は「第二部 健康状態」において肥満該当者の割合が過半数を超えています。
また、気分(感情)障害(躁うつ病を含む)の被保険者に占める入院外の有病者割合は全体では2.4%だったのに対して、情報通信業が3.3%、学術研究・専門・技術サービス業が2.5%と高い結果でした。
高度な知識を要する仕事による精神的な負担が高いことが考えられます。
「第四部 健診検査値及び問診回答・業態別年齢調整指数レーダーチャート」では、レーダーチャート形式で業種ごとの違いを男女別で視覚的に表現し、各業種の健康リスクの特性が明確化されています。
建設業、運輸業では、同業種の女性に比べて男性の結果が基準を超えている項目が多く、一方、飲食料品小売業や労働者派遣業では、同業種の男性にくらべ女性のほうが基準より高い項目が多い傾向がみられました。
具体的な対策
企業が取り組むべき施策
・健康経営の推進
健康経営の推進は企業の生産性向上に直結します。
まずは、健康診断結果などのデータから社内の健康状態を把握したのち、今回のような業種平均のデータと比較し課題を明確にしましょう。
具体的な施策としては、運動習慣を支援するプログラムや健康教育の実施が効果的です。
・ストレスチェックの活用
メンタルヘルスケアの一環としてストレスチェックを定期的に実施し、結果を活用しましょう。
ストレスチェック結果から課題のあぶり出しや対策の検討を行うことで、職場環境改善や社員のメンタルヘルス不調の予防が可能です。
また、専門家のフォローアップを導入することで職場環境改善の取り組みが明確になったり、他社と比較して結果を活用できたり、社内の業務負担を軽減できたりなどのメリットもあります。
・産業医、保健師などの活用
健康診断結果を基に、面談対象者を抽出し、産業医や保健師による面接指導を実施しましょう。
健康診断とその事後措置は組織の健康管理の基本です。
また、健康診断の結果を集計し、組織の健康課題を明らかにしたうえで、産業医や保健師などの医療職の視点からアドバイスをもらうことも効果的です。
そのアドバイスを基に、衛生委員会で目標の立案や健康教育を計画することで効果的に社員の健康状態を改善できるでしょう。
②個人ができる取り組み
・生活習慣の改善
毎日3回の食事で、肉や魚、野菜とともにごはんなどの炭水化物を適度に食べるバランスの良い食事を心がけ、程よく運動を取り入れ、質の良い睡眠を取ることで、生活習慣病のリスクを軽減できます。
また、特にデスクワークの多い業種では、毎日のウォーキングや簡単なストレッチを取り入れることで運動不足を緩和できます。
すきま時間の活用がおすすめです。
・メンタルヘルスケア
ストレスを溜め込まず、趣味やリラクゼーションを通じてリフレッシュする習慣を作ることが大切です。
また、悩みについては一人で抱え込まず、信頼できる人に相談する機会をつくるようにしましょう。
周囲に話をすることに対して億劫になる場合、外部相談窓口を利用することもおすすめです。
おわりに
本調査結果は、働く人々が抱える健康課題や傾向が明らかになりました。
特に、企業と個人が連携して健康管理に取り組むことが、労働者の健康だけでなく、企業の生産性向上にも寄与することが期待されます。
本調査をきっかけに、業態に応じた適切な健康対策を実施していき、できることから一歩ずつ始めていきましょう。
<参考>
健康保険組合連合会「令和4年度 業態別にみた被保険者の健康状態に関する調査」
監修者プロフィール
 | 中森 チカ 株式会社ドクタートラスト 保健師 大学卒業後、大学病院での病棟勤務(循環器内科・糖尿病内分泌科)を経て、地域包括支援センターの保健師として高齢者総合相談、介護予防事業などに従事。ドクタートラスト入社後は、セミナーの実施や年間100件超の保健指導やカウンセリング業務に携わっている。 「楽しく元気に働ける人を世の中に増やしていく」が保健師としての目標。心身の健康や予防が大切だと痛感したことから、「行動が変わる、考え方が変わるきっかけ作り」に邁進中。 【保有資格】保健師、看護師、公認心理師、国家資格キャリアコンサルタント、第一種衛生管理者、健康経営エキスパートアドバイザー、両立支援コーディネーター、人間ドック健診情報管理指導士 詳しいプロフィールはこちら |