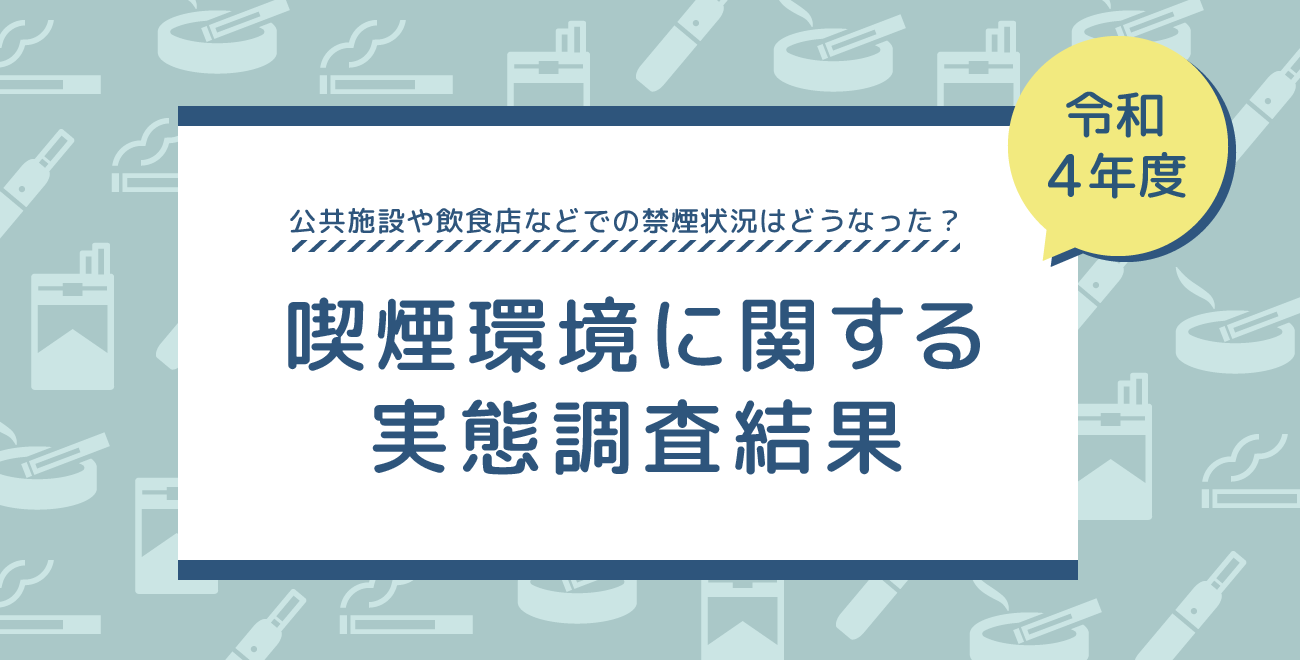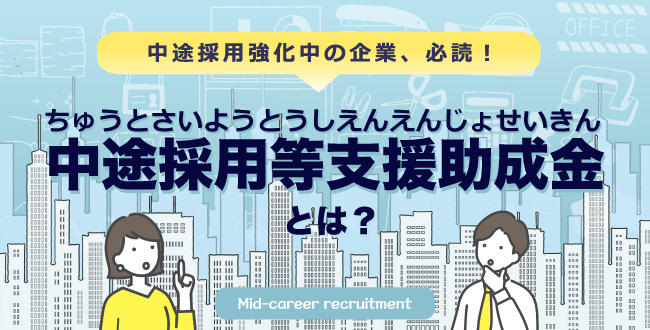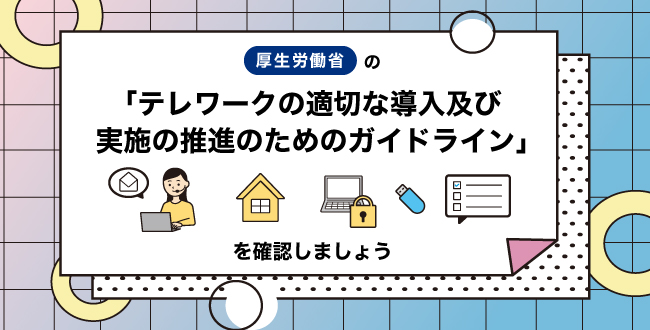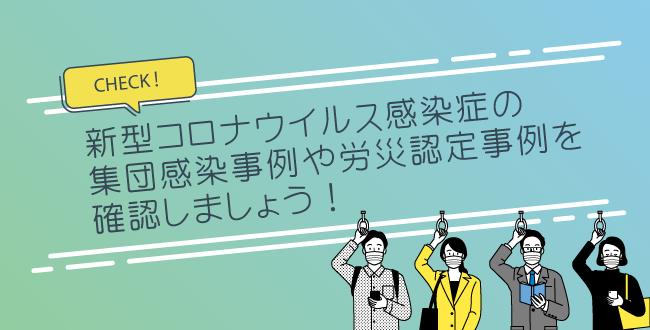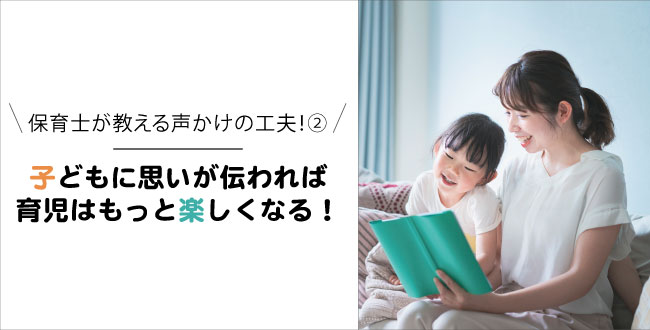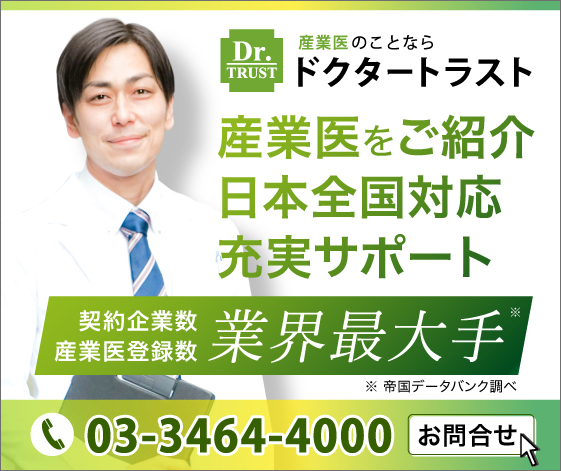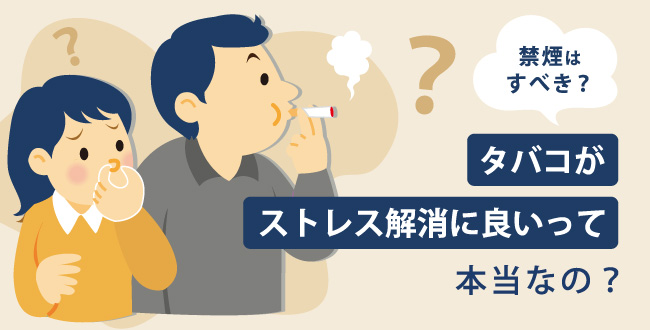2025年7月4日、厚生労働省は「イクメンプロジェクト」の後継として、新たに「共育(トモイク)プロジェクト」を開始すると発表しました。
「イクメンプロジェクト」はこれまで、男性の育児参画や育児休業取得を後押しする広報活動を中心に展開され、2023年度には男性育児休業取得率が30.1%と過去最高を記録するなど一定の成果を上げました。
その一方で、家事・育児時間における男女差や長時間労働といった構造的課題は依然として残る状況です。
「共育(トモイク)プロジェクト」の目的
共育(トモイク)プロジェクトの軸となる部分は、「きっかけ」「長時間労働の是正」「職場環境の見直し」です。
これまでの「男性の育児休業取得促進」に加えて、育児休業を「男女の家事・育児分担を見直すきっかけ」として活用する視点を新たに強化します。
また、育児への参加を阻害する大きな要因の一つである「男性の長時間労働」そのものを見直し、是正する取り組みも併せて推進するとしています。
さらに、プロジェクトの主戦場は「企業」のため、「職場風土の改善」や「雇用環境づくり」に重点を置き、多くの企業に対し啓発活動や情報提供を通じて「共育て」に取り組みやすい風土の醸成を目指します。
具体的には、管理職向け研修や育児支援制度の導入支援などを展開するとみられます。
背景にある社会的実情と共育(トモイク)プロジェクトの展望
日本社会では少子・高齢化が進行し、共働きや共育てを前提とした支援策の強化をするべきとの声が多いです。
背景には、総人口の減少や高齢化率の増加があり、職場・家庭双方でのワンオペ状態を脱却することが課題とされています。
法律的側面でも、近年の育児・介護休業法の改正が追い風となっており、「子の看護休暇の見直し」、「育児休業取得状況の公表義務の適用拡大」など、企業と従業員双方に影響を与える改正が続いています。
さらには「産後パパ育休」、「育児時短就業給付金」も登場し、経済的支援も強化されています。
個人の選択肢だけでなく、企業の制度整備・運用の実効力が問われるようになっています。
共育(トモイク)プロジェクトは、こうした法改正を背景に、「育児休業を取得すること」から「育児と仕事をともに担う社会づくり」へと意識を転換しようとする大きな試みとして注目されます。
厚生労働省はすでにティザーサイトを公開しており、今後は具体的なモデル事例や企業の取り組み、産業保健と連携した支援内容が明らかになることが期待されます。
まとめ
共育(トモイク)プロジェクトは次のような成果を目指しています。
・ 育児休業取得が、男女ともに家事・育児の分担見直しの契機となること
・ 長時間労働の是正を通じて、男性も育児に関われる時間的余裕を創出すること
・ 企業への働きかけによる職場風土・雇用制度の改善
・ 社会全体で「誰もが希望に応じて仕事と育児を両立し、共に育てられる社会」の実現
「産業保健新聞」のテーマである産業保健の視点では、ここに働き方改革とワーク・ライフ・バランスの実現が深く重なり合っています。
産業医や保健師、衛生管理担当者は、職場での制度浸透や従業員相談の担当として、重要な役割を担うことになります。
たとえば、男性社員への育児制度の周知、長時間労働是正のための面談・分析、企業セミナー場での啓発活動などがその一環です。
特に中小企業や業界によっては、意味ある制度が存在しても使いづらい文化・職場風土が根強いケースもあります。
産業保健の担い手が、企業内の声にも耳を傾けながら、現場に合った落とし込み支援を行う重要性が増しています。
<参考>
・ 厚生労働省「『共育(トモイク)プロジェクト』開始のお知らせ」
・ 厚生労働省「イクメンプロジェクト趣旨」