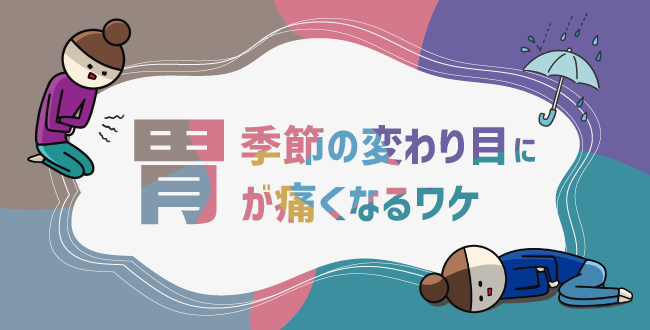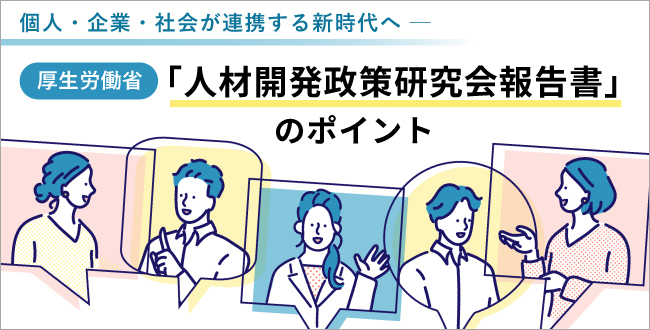
2025年7月7日、厚生労働省は「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」(以下、本報告書)を公表しました。
この報告書は、人材開発政策の基本的方向について「労働市場でのスキル等の見える化の促進」、「個人のキャリア形成と能力開発支援の充実」、「企業の人材開発への支援の充実」、「人材開発機会の拡大、技能の振興」の4つの柱で整理するとともに、非正規雇用労働者や中高年労働者、キャリア形成の初期段階にある若者への支援策や、現場人材育成の支援策をまとめた内容となっています。
今回はその4つの柱に注目し、課題と今後の取り組みについて解説します。
人材開発政策の課題
本報告書では、以下の課題が取り上げられました。
企業・労働者による人材開発の取組の促進
・ 企業の人材開発投資、個人の自己啓発が低調
・ 非正規雇用労働者への人材開発と中小企業の人材開発が低調
・ 仕事以外の時間の確保が必要な就業者が増加傾向
人材開発投資、個人の自己啓発が低調している状態であり、改善するための働きかけが求められます。
特に、非正規で働く人や中小企業での人材育成は進んでいないため、こうした層への支援が重要です。
さらに、育児や介護などの事情で、仕事以外の時間が必要な人も増えているため、そうした状況に対応できる環境づくりも大切になっています。
労働供給制約への対応
・ 構造的な労働供給制約と人材不足が見込まれる
・ 高齢者や非正規雇用労働者等の一層の戦力化
今後、構造的な人手不足が続くと見込まれる中で、経済の発展を目指すには、働く人のスキルを高めることに加えて、人材の需要と供給をうまく調整できるしくみを整えることが大切です。
そのためには、労働市場の環境を改善していく必要があります。
また、高齢者や非正規で働く人などがより活躍できるように、働き続けやすい環境を整えたり、スキルアップの機会を広げたりすることも重要になります。
労働者の自律的・主体的キャリア形成の促進
・ 寿命が延びる中、長期化する生涯労働時間において、雇用と仕事を取り巻く環境の変化に柔軟に対応・支援する
・ 職務・スキル・処遇・人材開発機会の情報の充実、それへのアクセス性の向上
働く期間が長くなり、雇用や仕事の環境が大きく変化する今、こうした変化に柔軟に対応しながら、自分のキャリアを主体的に考えられるような支援・環境が求められています。
そのためには、仕事内容や必要なスキル、待遇、人材育成の機会などに関する情報をわかりやすく提供し、誰もがアクセスしやすくすることが重要です。
<デジタル技術の進展等による 産業構造等の変化への対応>
・ AIの進化やデジタル技術の進展、業務のDX化などに応じたプログラムの開発、提供
・ デジタル技術を上手く活用しつつ、人でしかできない仕事に求められる技能
AIやデジタル技術の進化、業務のデジタル化(DX)の進展により、産業の構造や求められる人材像が大きく変わりつつあります。
これに対応するには、そうした新たなニーズに合った教育プログラムを開発・提供していくことが重要です。
また、テクノロジーを使いこなすスキルだけでなく、人間の判断や対話など「人にしかできない役割」に必要な能力にも、これまで以上に目を向ける必要があります。
人材開発政策の課題をふまえた今後の取り組み
本報告書では、今後の取り組みとして以下が挙げられていました。
<労働市場でのスキル等の見える化の促進>
〇 職務(ジョブ)や業務内容(タスク)、スキル、賃金水準などを分類・整理する「job tag」※1の拡充
〇 団体や企業が実施する認定制度や社内検定への支援
〇 社内で通用するスキル基準(社内スキル標準)づくりの検討
〇 個人のスキルを企業に伝えるための新たな仕組みの検討
〇 企業が自社の人材育成に関する情報をより積極的に開示・発信できるようにするための方策
<個人のキャリア形成と能力開発支援の充実>
〇 キャリアプランの作成や定期的な見直しを支援する「伴走型支援」の拡充
〇 若年層が早い段階からキャリア相談を活用できるよう促す取り組み
〇 上司や指導者など、キャリア支援を行う立場の人への支援
〇 キャリアコンサルタントの専門性強化と、そのスキル・経験の「見える化」
〇 社外でも気軽にキャリア相談できる環境整備
〇 相談者同士の横のつながりの重要性にも着目
〇 自己啓発や学び直しに積極的に取り組める土台として、企業への支援も強化
〇 働く人が自分から学ぼうと思える雰囲気づくり
<企業の人材開発への支援の充実>
〇 育成制度の整備や周辺環境の構築を後押し
〇 事業内職業能力開発計画や職業能力開発推進者制度の普及
〇 訓練の計画段階から企業に寄り添う「伴走型支援」の強化
〇 専門家による企業内人材育成の支援体制の整備
〇 「セルフ・キャリアドック」※2の活用促進
〇 特に中小企業への個別支援を手厚く
〇 経営者のデジタル知識(DX)向上を支える取り組み
<人材開発機会の拡大、技能の振興>
〇 地域ごとに職業訓練のあり方を見直す協議体の機能強化
〇 実務経験を取り入れた訓練機会の充実策を検討
〇 企業の枠を超えた、産業・地域単位での共同人材開発の推進
〇 団体による検定制度や認定職業訓練の活性化
〇 教育訓練給付金の対象講座の拡大
〇 職業訓練やキャリア相談に関する情報提供の充実
〇 民間教育機関の質向上
〇 2028年の技能五輪国際大会の開催を契機に、技能の価値を再認識し、技能者の育成強化を図る
※1 職業情報提供サイト
※2 企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・定期的に従業員の支援を実施し、従業員の主体的なキャリア形成を促進・支援する総合的な取組み、また、そのための企業内の「仕組み」のこと。
まとめ
本報告書では、上記取り組みを支える基本的な視点として「個別化」「共同・共有化」「見える化」の3つが示されています。
これらは、一人ひとりのニーズに応じた支援を行い、企業や地域との連携を深めながら、スキルや取り組みの可視化を進めていくという方向性を意味します。
人材開発を「個人だけ」「企業だけ」に任せるのではなく、社会全体で支え合う時代へ。
すべての人が学び、成長し続けられる仕組みづくりが、これからの日本の持続的な発展を支える鍵となります。
<参考>
・ 厚生労働省「『今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書』を公表します」
・ 厚生労働省「『セルフ・キャリアドック』導入の方針と展開(PDF)」




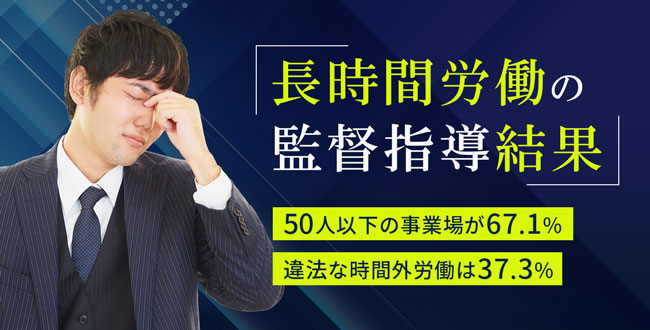

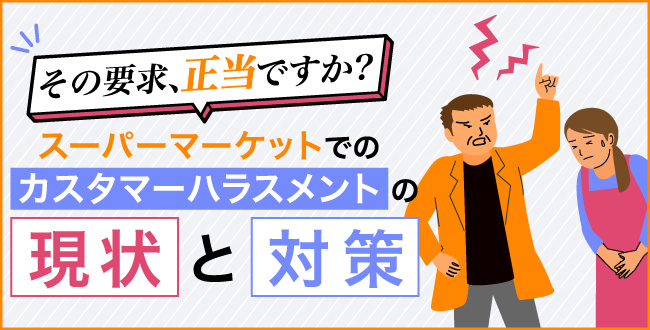
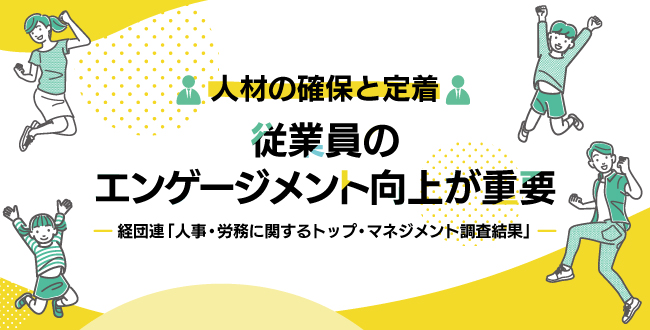
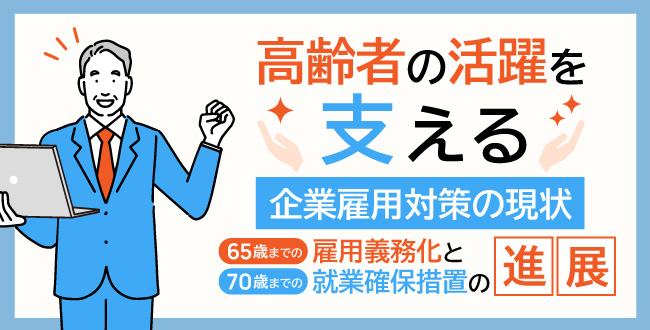
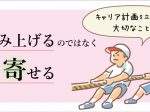



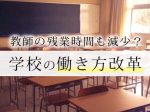





唐澤さん公益通報サムネ.jpg)