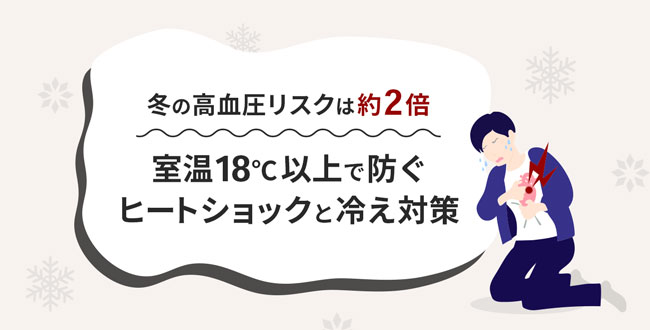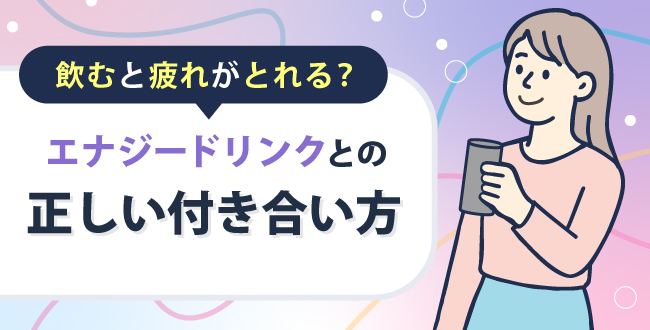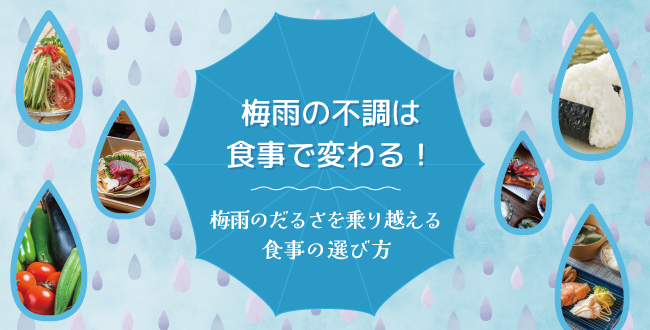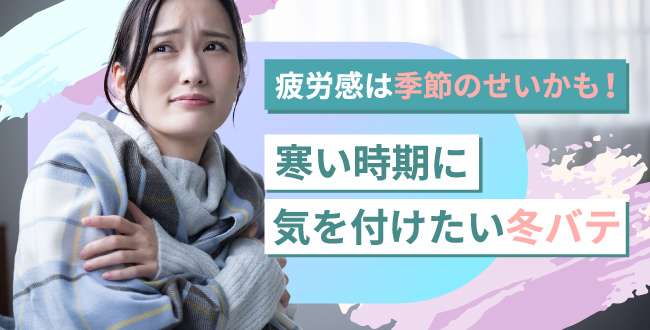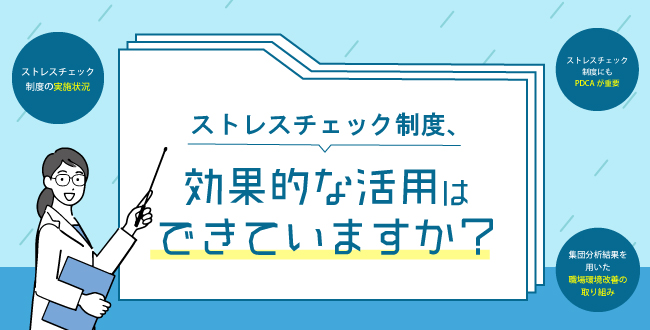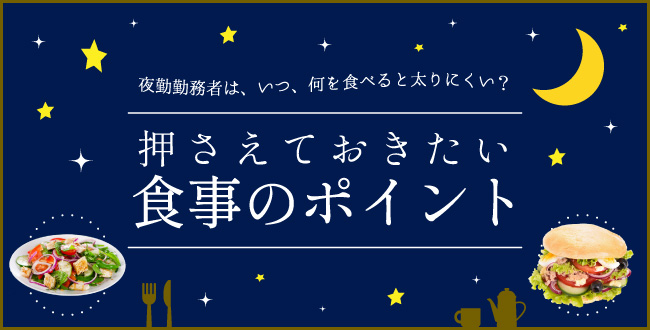- Home
- ドクタートラストニュース, 管理栄養士, 食事
- 骨粗鬆症予防ガイドライン10年ぶり改訂!若い世代も要注意
骨粗鬆症予防ガイドライン10年ぶり改訂!若い世代も要注意
- 2025/11/25
- ドクタートラストニュース, 管理栄養士, 食事
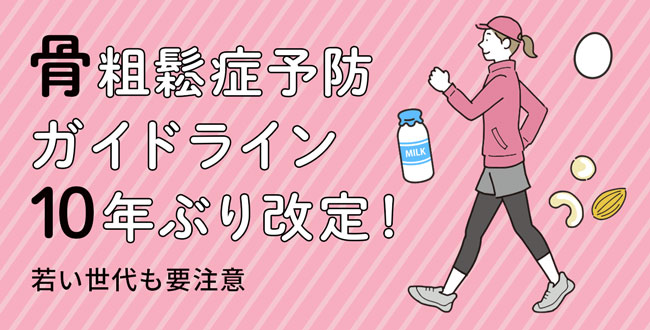
2025年7月に「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」が10年ぶりに改訂されました。
治療選択肢の拡大や、骨折既往歴がある方への治療の明確化などがアップデートされています。
厚生労働省が3年ごとに実施する患者調査によると、骨粗鬆症の総患者数は2020年度の135万9千人から、2023年度には138万7千人へと約3万人増加しました。
高齢化の影響に加え、栄養バランスの偏りなどにより若年層でも発症するケースが報告されています。
「まだ若いから大丈夫」と油断は禁物です。
1. 骨粗鬆症とは
骨粗鬆症とは、骨の代謝バランスが崩れて骨量が減少し、骨がもろくなった状態を指します。
骨は「骨形成(新たに作られる)」と「骨吸収(壊される)」を繰り返し、常に新しく作り変えられています。
しかし、加齢やホルモンバランスの変化により骨吸収が骨形成を上回ると、骨密度が低下し、わずかな衝撃で骨折しやすくなります。
発症リスクが高い方
・ 閉経後の女性(ホルモンバランスの変化)
・ 喫煙習慣がある方
・ 多量飲酒の習慣がある方
・ 低体重の方
気になる方は、国際骨粗鬆症財団(IOF)の「骨粗しょう症リスクチェックリスト」を活用してみましょう。]
2. 早期発見のために
厚生労働省が2024年4月から実施している「健康日本21(第三次)」では、骨粗鬆症検診受診率の低さが問題視されており、受診率15%への向上が新たな目標として掲げられています。
骨粗鬆症は自覚症状がほとんどなく、骨折して初めて気づくケースが少なくありません。
検診で早期発見し、適切に対処することが重要です。
骨粗鬆症検診の内容
・ 病歴・生活習慣に関する問診
・ 骨量測定(超音波またはX線使用)
・ 測定時間:1~8分程度
・ 痛みなし
40歳以上の女性は特に受診が推奨されており、各自治体で40~70歳の女性を対象に5歳刻みで検診が実施されています。
対象の方はぜひ活用しましょう。
3. 骨を強くするために
骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインで、栄養療法として積極的な摂取が推奨されているのがカルシウムとビタミンDです。
カルシウム
・ はたらき:骨の材料となる
・ 多く含む食品:牛乳、ヨーグルト、小魚、干しエビ、わかめ、ひじき など
乳製品は特にカルシウムの吸収率が高くおすすめです。
カルシウムは加熱で失われる栄養素ではないため、牛乳が苦手な方は料理に加えて摂取量を増やすとよいでしょう。
また、ビタミンKは血中カルシウムを骨に沈着させ、骨形成を促す作用があります。
ビタミンKを豊富に含む納豆を食べるのがおすすめです。
ビタミンD
・ はたらき:骨の発育を促進する
・ 多く含む食品:きのこ類、しらす、鮭、卵、牛乳 など
ビタミンDは食品からだけでなく、日光に当たることで皮膚でも作り出せます。
適度な日光浴も大切です。
特に避けるべき食品はありませんが、食塩・カフェイン・アルコールの過剰摂取には注意しましょう。
運動習慣
骨の長軸方向に刺激が加わると、骨の強度が増すといわれています。
ウォーキングやジョギングのような重力がかかる運動が効果的です。
運動習慣がない方やデスクワークが多い方は、意識的に歩く機会を設けることを心がけましょう。
骨粗鬆症を発症し生活に影響が出始めてからでは取り返しがつきません。
日頃から骨を強くする習慣を心がけましょう。
<参考>
・ 厚生労働省「令和5年患者調査」
・ 厚生労働省「健康日本21(第三次)」
・ 厚生労働省「骨粗鬆症予防のための運動 -骨に刺激が加わる運動を」
・ 公益財団法人骨粗鬆症財団「どんな人がなりやすい」
・ 公益財団法人骨粗鬆症財団「40歳からはじめる骨粗鬆症検診」
・ 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会(日本骨粗鬆症学会 日本骨代謝学会 骨粗鬆症財団)編集『骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版』(ライフサイエンス出版、2025年7月)