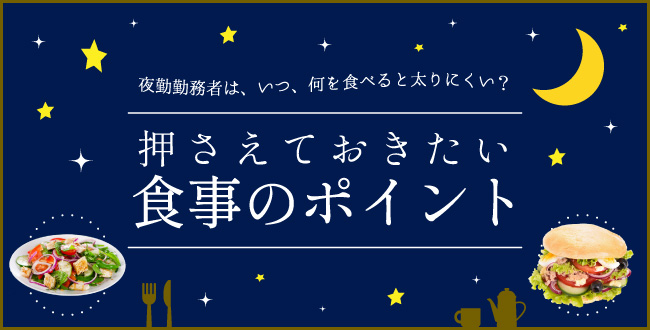約3人に1人が発症!帯状疱疹ってどんな病気?
- 2025/11/21
- 病状・症状

皆さん、帯状疱疹という病気をご存知ですか?
よく水ぼうそうやヘルペスと間違えられる帯状疱疹、日本では80歳までに約3人に1人が発症すると推定されています。
帯状疱疹は水ぼうそうにかかったことがあれば、誰でも発症するリスクがあります。
今日は、そんな帯状疱疹について、帯状疱疹が発症する仕組みや受診の目安、症状について解説していきます。
帯状疱疹の原因としくみ
帯状疱疹は、「水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)」が再び活性化することで起こる病気です。
このウイルスは、子どもの頃にかかる「水ぼうそう(水痘)」の原因でもあります。
実は、成人の約9割は水痘・帯状疱疹ウイルスを持っているといわれています。
発症までの流れ
① 水ぼうそうを発症する
初めて水痘・帯状疱疹ウイルスに感染すると、水ぼうそうを発症します。
② ウイルスが神経節に潜伏する
水ぼうそうが治った後も、ウイルスは神経を通って神経節という体内に潜伏しています。
③ 免疫力が低下
休眠状態で眠っていたウイルスは、強いストレスや病気などにより免疫力が低下すると、再び活性化します。
④ 帯状疱疹を発症
ウイルスが再活性化し、神経に沿って体の表面に現れて発症します。
症状や合併症
体の右側、もしくは左側のいずれかの神経に沿って症状が出現することが多いです。
下記のような経過を経て、約3週間で皮膚症状が治まることが多いです。
◎症状
① 痛みや違和感:チクチク、ピリピリ、ズキズキした痛み。焼けるような、刺されるような痛みと表現されることもあり。
② 発疹:小さなブツブツやわずかな盛り上がり程度だったものが、赤みを帯びた小さな水疱に変化する。徐々に数が増えていき、帯状に分布していく。
③ 水疱が破れてびらん(水ぶくれが破れてただれた状態)となり、かさぶたとなる。
帯状疱疹は、発症する部位や治療の遅れなどにより、重篤な合併症を起こす可能性がある恐ろしい病気です。
◎合併症
・味覚障害
・結膜炎や角膜炎など
・顔面神経麻痺
・難聴
・排尿障害
・帯状疱疹後神経痛(皮膚症状が消えた後も痛みが続く)
◎帯状疱疹になりやすい人
・50歳以上の人
・基礎疾患のある人(例:糖尿病、膠原病、リウマチなど)
・血液がんの方(白血病、悪性リンパ腫など)
・疲労やストレスで免疫力が低下している人
※帯状疱疹の発症率は50歳以上で急増し、患者全体約7割を50歳以上が占めています。
帯状疱疹を早期に発見して治療を開始するためにも、発疹が現れてから3日以内に受診をすることをおすすめします。
発疹が出ていない段階(痛みや違和感など)では、正確な診断を下すことが難しいので、原則発疹が出てから皮膚科を受診しましょう。
また、合併症のリスクが高い顔面に症状が現れた場合は早急に受診しましょう。
帯状疱疹って人にうつるの?
先述した通り、帯状疱疹は体内に潜伏しているウイルスが再活性化することで発症するため、帯状疱疹として周囲にうつることはありません。
ただし、水ぼうそうを発症したことがない方(乳幼児含む)と帯状疱疹を発症している方が接触すると、ウイルスをうつしてしまう可能性があります。
この場合、うつった方は帯状疱疹ではなく、「水ぼうそう」を発症します。そのため、帯状疱疹を発症した場合、水ぼうそうにかかったことのない乳幼児や妊婦などとの接触は控えましょう。
帯状疱疹を予防する有力な手段として、ワクチン接種がございます。
2025年度からは、65歳の方などへの帯状疱疹ワクチンの予防接種が定期接種の対象にもなりました。
帯状疱疹になりやすい方は、予防の一つとしてワクチン接種をご検討ください。
<参考>
・株式会社法研「へるすあっぷ21」(2023.6、p43-49)
・厚生労働省「帯状疱疹ワクチン」


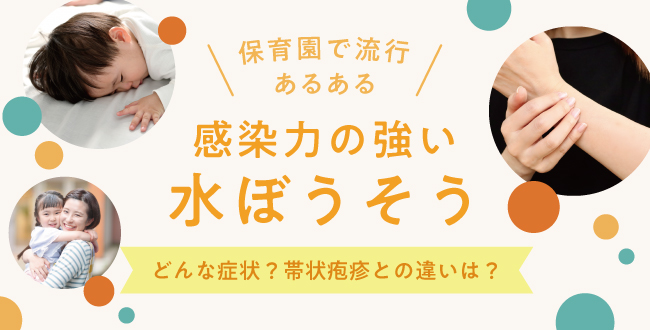


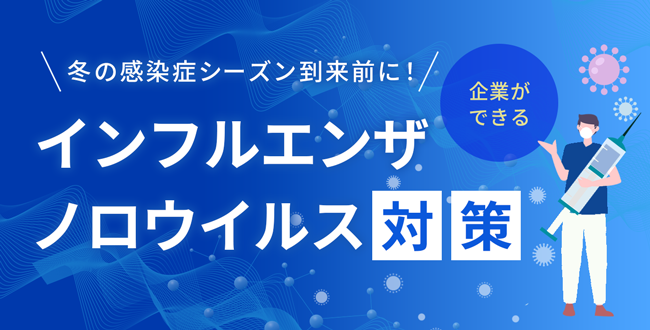
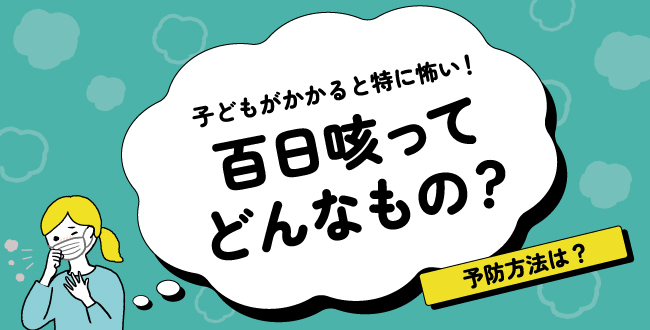
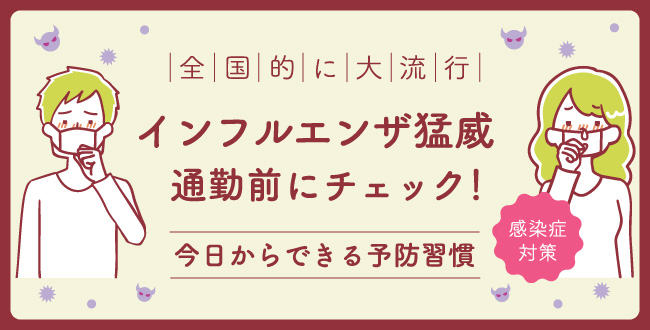
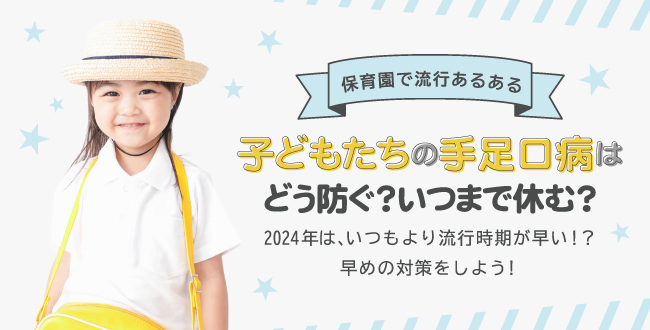




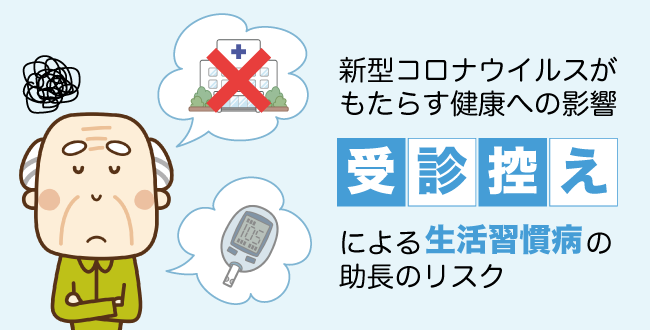


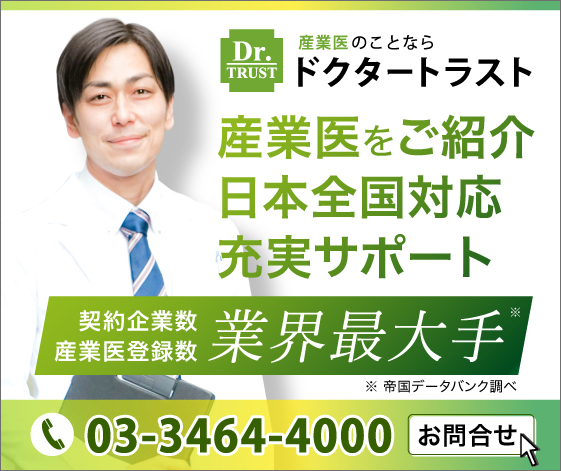


唐澤さん公益通報サムネ.jpg)