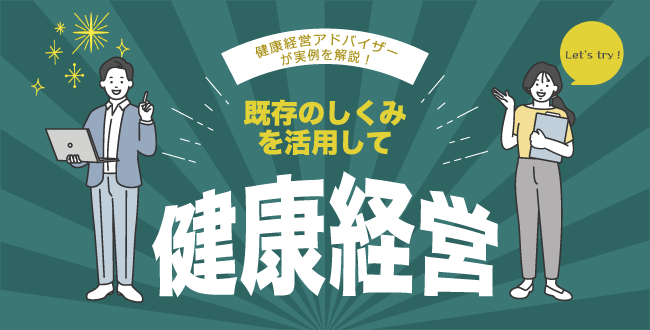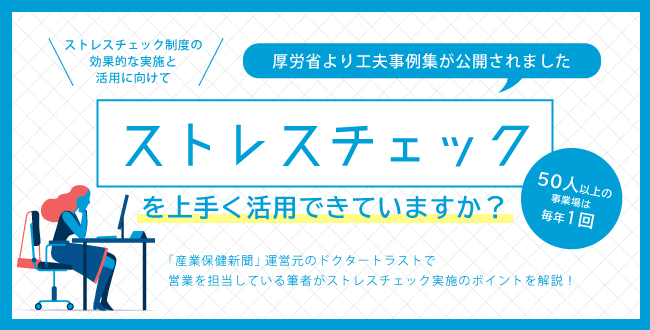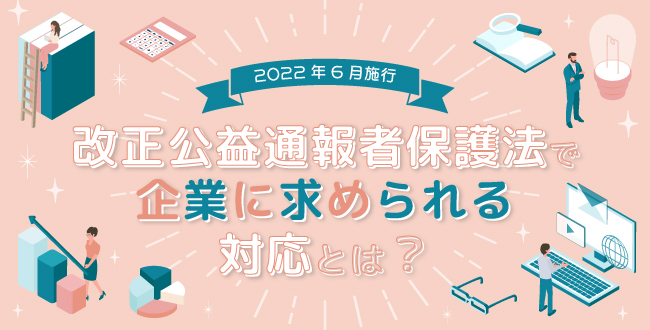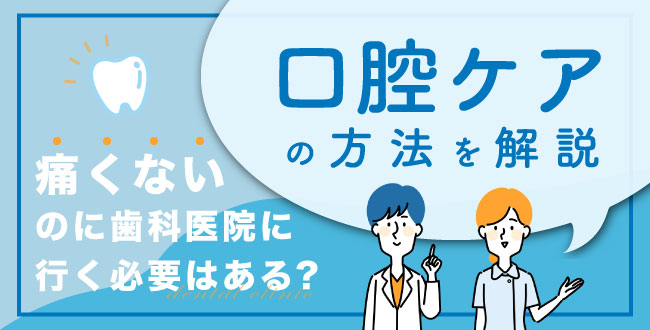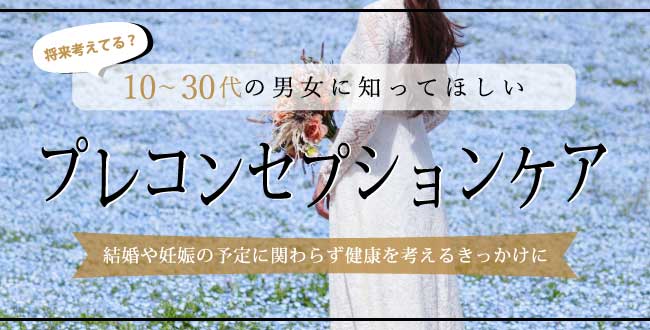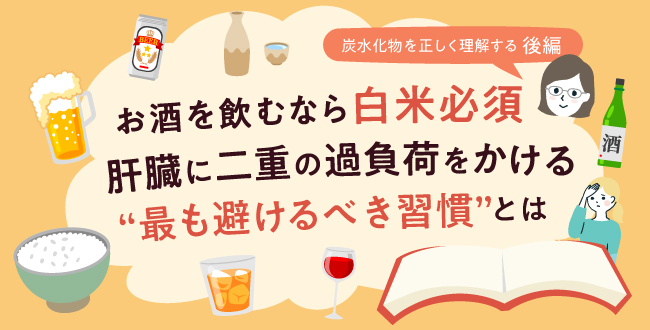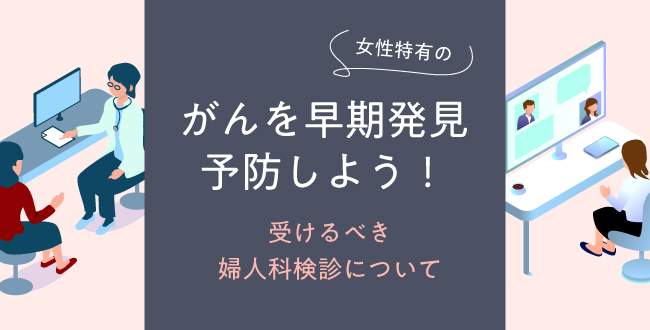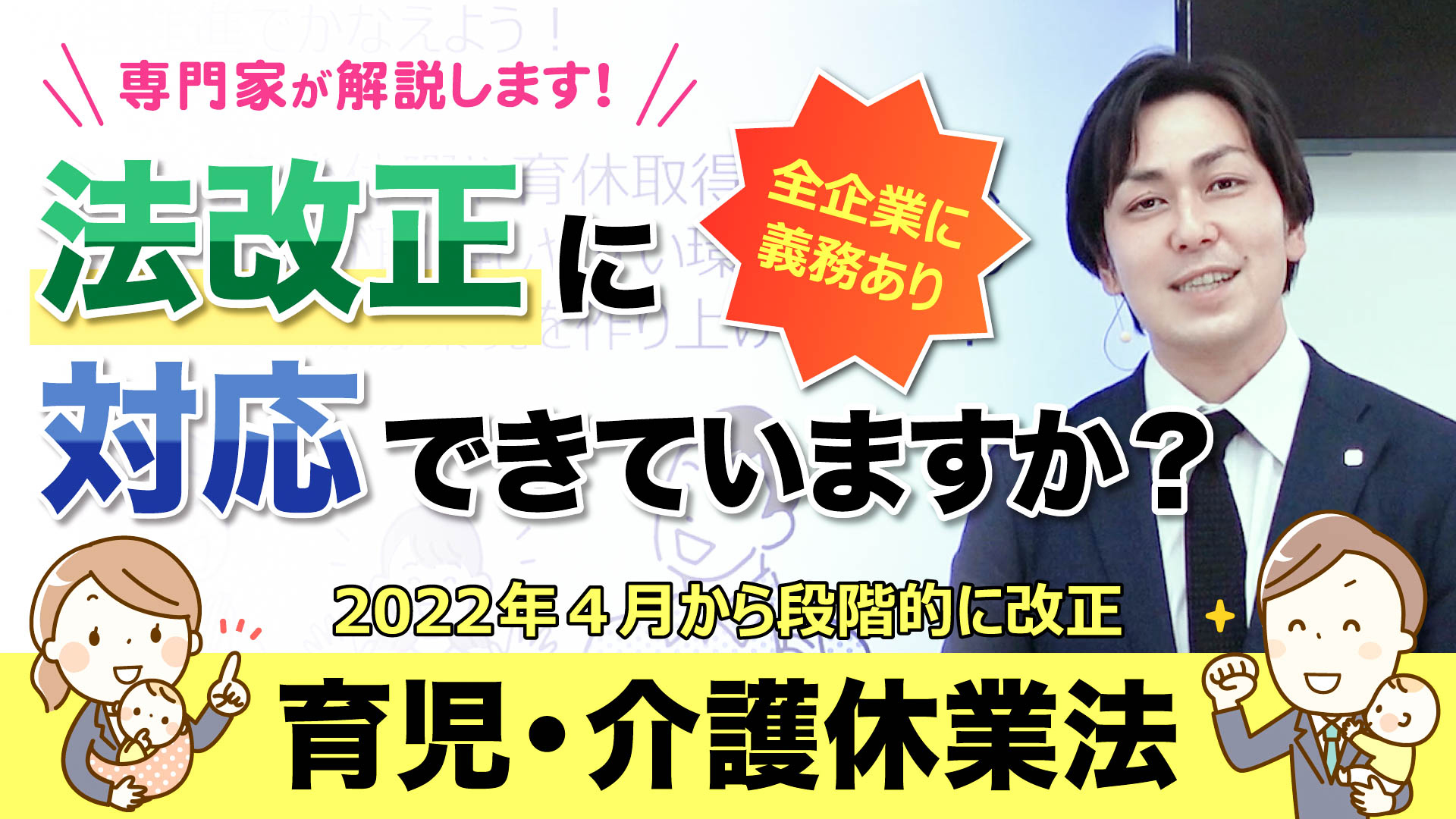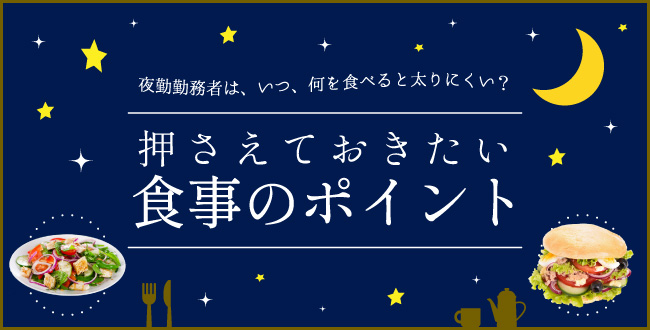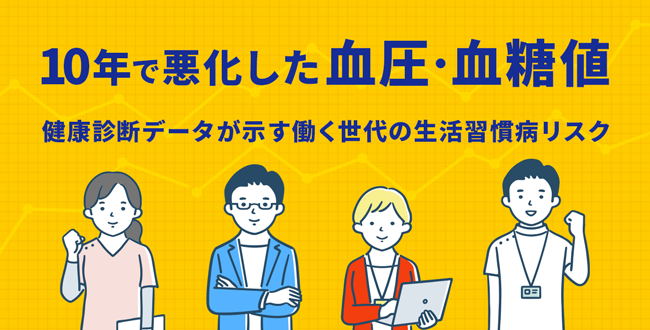
10年で加速した「生活習慣病の静かなる危機」:血圧・血糖値の悪化
私たちが毎年受ける企業健診の結果は、単なる個人の健康状態を示すだけでなく、働き方と生活習慣の変化を映し出す鏡です。
法令義務として「仕方なく受診している」という従業員・企業も少なくはありません。
しかしながら健康診断結果に注目すると、日本の働く世代が直面している「生活習慣病の静かなる危機」が浮き彫りになります。
厚生労働省の定期健康診断結果によると、「有所見率」は、この10年で6.2ポイントも増加しています。
この増加を最も強く牽引しているのが、血圧と血糖値の項目です。
まず、血圧の有所見率は、2014年の15.1%から、2024年には18.4%へと3.3ポイントも増加しました。
高血圧、またはその予備軍であるという深刻な状況を示しています。
次に、血糖検査の有所見率も、同データによると2014年の10.4%から、2024年には13.1%へと着実に増加しています。
これは、働き盛りの糖尿病予備軍や境界型糖尿病の増加を意味します。
高血圧も高血糖も、自覚症状がほとんどないまま進行するため、健診結果で指摘されても放置されがちですが、放置すれば脳卒中や心筋梗塞、腎不全といった重大疾患へ直結します。
この10年間で、仕事の負荷増大と座りっぱなしの生活が定着し、身体は慢性的なストレスと運動不足にさらされました。
その結果、交感神経が優位になり血圧が上昇しやすくなり、またインスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性)ことで血糖値が上がりやすくなったのです。
このデータは、「現在の働き方や生活習慣を放置すれば、将来に待っているのは重症化リスクの増大である」という、未来への警告かもしれません。
悪化要因の深層分析:仕事のストレスと食生活の偏り
血圧と血糖の悪化の裏側には、この10年間で顕著になった二つの大きな構造的な要因が潜んでいます。
要因1:ストレスと不規則な勤務体制
血圧は、ストレスレベルと密接に関係しています。
この10年間で、業務のデジタル化は進んだものの、業務の複雑性やプロジェクトの納期は厳しくなる一方です。
特に40代から50代の管理職層では、プレッシャーによる持続的なストレスが交感神経を常に緊張させ、血管収縮を促し、血圧の上昇を招いています。
さらに、不規則な残業や睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、高血圧を定着させる大きな要因となっています。
健診データは、彼らが直面する「働きすぎの代償」を明確に示しています。
要因2:食生活の急激な変化
血糖値の悪化は、主に食生活の偏りと運動不足に起因します。
この10年間で、コンビニエンスストアやデリバリーサービスの利用が日常化し、手軽に高カロリー・高糖質の食事を取る機会が増えました。
特に、清涼飲料水や加工食品に含まれる隠れた糖分、そして運動せずに摂取される過剰な炭水化物が、血糖値を慢性的に高い状態に保ち、インスリンを疲弊させています。
血圧と血糖値の異常は、互いに悪影響を与え合い、「動脈硬化」という共通のゴールへと向かわせます。
この複合的な悪化傾向を放置することは、個人のQOL(生活の質)の低下だけでなく、企業全体の医療費や休業補償費を増大させる経営リスクそのものです。
健診結果を「自己投資」に変えるアクションプラン:血圧・血糖値改善への戦略的介入
「待っているだけでは健康は悪化する一方だ」ということが健康診断結果では物語っています。
改善するための戦略的なアクションプランが必要です。
1. 特定保健指導へのインセンティブ強化
高血圧や高血糖のハイリスク層である特定保健指導対象者への介入を最優先します。
指導を業務時間内に受けられる制度の導入や、完了者へのインセンティブ(例:健康グッズの提供)を設けるなど、参加へのハードルを下げる工夫が求められます。
データが示すように、この層への介入こそが、最も費用対効果が高い健康投資となります。
2. 食事と運動への「データに基づく動機づけ」
従業員に対して、単なる「減塩」や「減量」の呼びかけに留まらず、具体的な「行動変容」を促します。
血圧対策: 健診結果で血圧が高かった社員に、カリウムを多く含む食品(野菜や果物)の積極的な摂取を奨励する社内レシピコンテストを実施します。
血糖対策: 血糖値の高い社員に、食後の軽いウォーキング(10分程度)を推奨し、その習慣化をサポートするアプリを導入するなど、データに基づく具体的な行動を促します。
3. ストレスと血圧の連動対策
長時間労働とストレスによる血圧上昇に対抗するため、産業医や保健師と連携し、血圧が高い社員へのストレスチェック結果の個別フィードバックを強化します。
単なる身体の数値だけでなく、メンタル面も含めた総合的なフォローアップを行うことで、心身の健康を一体として捉える健康経営を実践します。
この10年間のデータが示す悪化傾向は、私たち自身の生活習慣と向き合う最後のチャンスかもしれません。
血圧と血糖値の改善は、個人にとっては健康寿命の延伸であり、企業にとっては活力ある職場環境の再構築に直結します。
健診結果を自己投資に変え、次の10年で健康リスクを改善しましょう。
<参考>
・ 厚生労働省「定期健康診断結果」
・ 厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ」