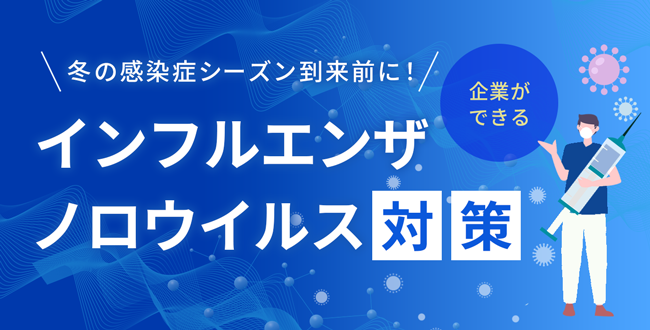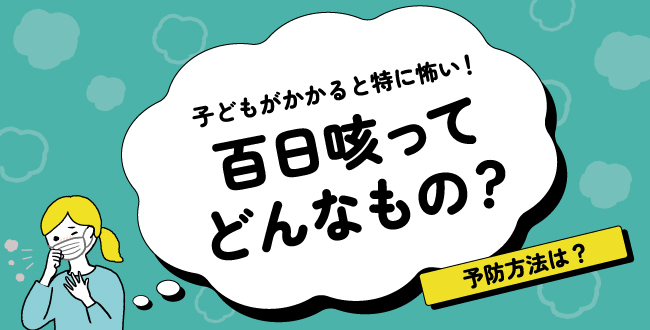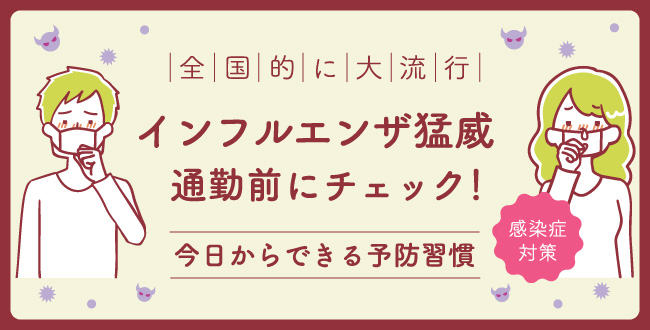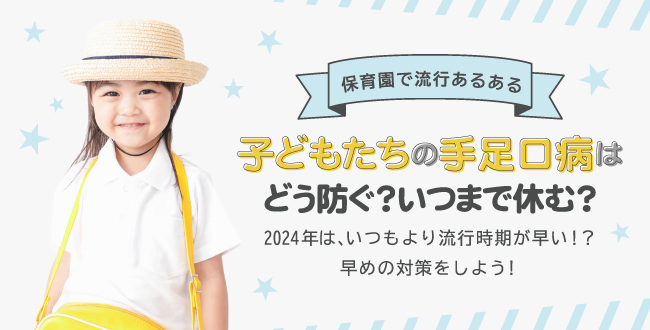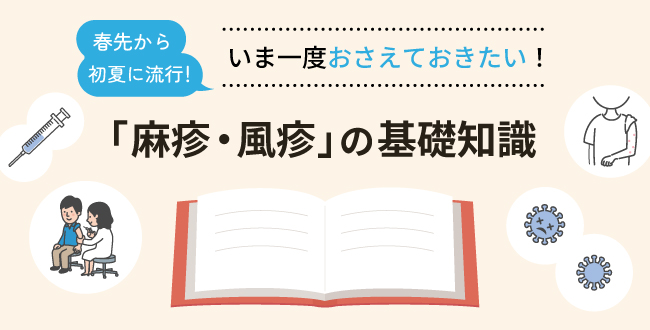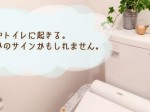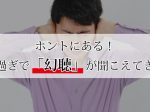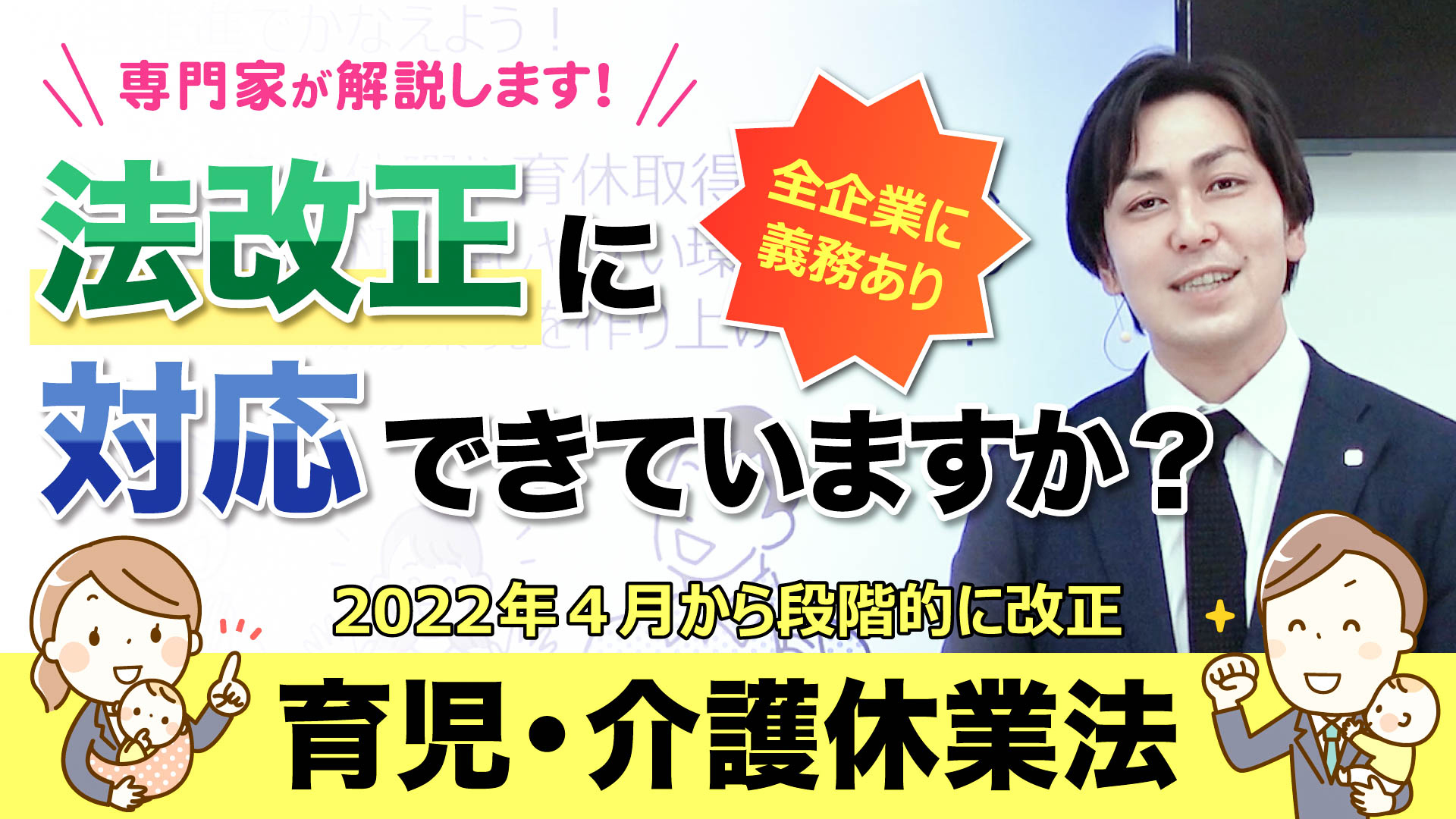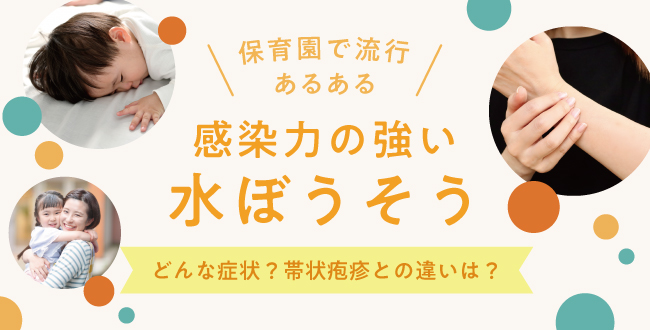
水痘の症状
皆さん、「水痘(すいとう)」をご存知ですか?
いわゆる「水ぼうそう」のことを指します。
水痘・帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされ、主に子どもに感染しやすい病気です。特に9歳以下での発症が90%以上を占めるとも言われています。
水痘には約10〜21日の潜伏期間があり、その後に特徴的な症状が現れます。
主な症状は以下のとおりです。
発疹
頭、体幹、四肢の順に現れることが多く、なかでも体幹に最も多く出ます。
かゆみを伴いながら、赤みのある「紅斑」、盛り上がった「丘疹」、水ぶくれ、かさぶたという順で変化していきます。
急性期には新たな発疹が次々と現れるため、異なる段階の発疹が混在しているのが特徴です。
すべてがかさぶたになるまでには、およそ6日間かかります。
※鼻や喉、気道の粘膜にも発疹が出ることがあります。
成人の場合
発疹が出る前に1〜2日間の発熱や倦怠感を伴うことがあります。
その他の症状
・ 倦怠感
・ 掻痒感(かゆみ)
・ 約38℃前後の発熱(2〜3日ほど)
水痘感染経路と予防方法
水痘は非常に感染力が強く、以下の3つの経路で感染します
・ 飛沫感染:咳やくしゃみなどによって飛んだ飛沫に含まれる病原体を吸い込み感染すること
・ 接触感染:感染している人の皮膚や粘液に触れたり、病原体がついたドアノブや手すりなどを介して間接的な接触により、病原体が付着し感染すること
・ 空気感染:空気中のウイルスを含む微細な粒子を吸い込むことで感染すること
マスクや手洗い・うがいだけでは十分な予防は難しく、最も効果的な予防手段は予防接種です。
ワクチンの有効性
1回の接種で重症の水痘をほぼ100%予防できます。
2回接種すれば、軽症を含めて発症の可能性をさらに減らせると考えられています。
定期接種制度(2014年10月から)
■対象:生後12か月〜36か月未満のお子様(1歳の誕生日前日〜3歳の誕生日前日)
■接種スケジュール
1回目:標準的には生後12か月~生後15か月までの間
2回目:1回目から3か月以上あけ接種。標準的には1回目接種後6〜12か月の時期に接種
※詳細は、お住まいの地域の保健センターやかかりつけ医などへご相談ください
登園・登校再開の目安
働いている方が特に気になるのは、「いつまで保育園や幼稚園を休む必要があるのか」ですよね。
水ぼうそうは学校保健安全法にて第2種感染症に定められており、「すべての発しんが痂皮化するまで出席停止」とされています。
保育施設によっては、再登園の際に医師の許可書が必要な場合もございます。感染症にかかった際は、保育施設に再登園について確認することをおすすめします。
帯状疱疹とどう違うの?
水痘と似て非なるものが「帯状疱疹」です。
水痘も帯状疱疹も、同じ「水痘帯状疱疹ウイルス」による病気ですが、発症のしくみが異なります。
帯状疱疹は、「体内に潜伏していたウイルスが再び活性化する」ことで起きる病気です。
<帯状疱疹がおこるしくみ>
・ 水ぼうそうに感染
・ 水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内に潜んでいる
・ 加齢・ストレス・疲れなどで免疫力が低下するとウイルスが再び活性化し、皮膚症状などが現れる
帯状疱疹は外部から感染するのではなく、体内に潜んでいるウイルスが原因で発症することから、帯状疱疹として他人にうつることはありません。
ただし、帯状疱疹の発疹には水痘と同じウイルスが含まれているため、乳幼児など水ぼうそうにかかったことがない人に接触した場合、水痘として発症する可能性があります。
そのため、帯状疱疹にかかった際は、発疹などの症状が治まるまでは、水痘にかかったことがない人との接触を避けることをおすすめします。
子育て中の皆様、毎日本当にお疲れ様です。
特に、入園して間もないお子様は、次々と感染症にかかることが多く、大変な思いをされていることと思います。
お子様の健康はもちろんですが、皆様ご自身の体調も大切にしながら、毎日を健やかに過ごせるよう願っています。
<参考>
・ 厚生労働省「水痘ワクチン」
・ 国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「水痘」
・ 「へるすあっぷ21」(法研、2023.6.p40)