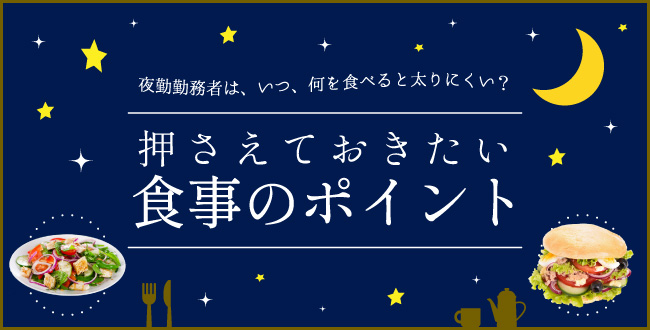働く人にこそ紅茶を。カフェイン控えめでリラックス効果も
- 2025/10/31
- 食事

11月1日は「紅茶の日」です。
日本で最初に大黒屋光太夫が紅茶を飲んだ記録が残る11月1日にちなみ、日本紅茶協会が制定しました。
紅茶は世界中で親しまれ、私たちの職場や日常生活でも身近な存在となっています。
一方、ビジネスシーンで多くの方が愛飲しているのはコーヒーです。
株式会社ハリオ商事による調査によると、職場で飲むことが多いのは、お茶よりもコーヒー派が約7割と多数派です。
香りで気持ちを切り替えたり、眠気を抑えて集中力を高めたりと、仕事の相棒としてコーヒーは重宝されています。
ただ、コーヒーを飲むと「胃がもたれる」「お腹がゆるくなる」と感じる方も少なくありません。
これは、コーヒーに含まれるカフェインやクロロゲン酸などが胃酸分泌を刺激しやすいためと考えられています。
そのため、健康上の理由や体質からコーヒーを控えたい方にとって、代替の飲み物を見つけることは大切です。
そんな方にこそ、「紅茶」がおすすめです。
コーヒーと紅茶のカフェイン量を比較
紅茶にもカフェインは含まれていますが、コーヒーと比較すると約半分です。
集中力を高めたいけれどコーヒーが体に合わないという方は、カフェインの少ない紅茶で代替するのがおすすめです。
コーヒー200㎖あたり:120㎎
紅茶200㎖あたり:60㎎
個人差はあるものの、カフェインの血中濃度は摂取後30分~2時間程度でピークとなり、2~8時間程度で効果が薄れていきます。
そのため、一般的に16時以降は睡眠への影響を考慮してカフェインを避けることが推奨されます。
また、遺伝子により分解速度は異なりますが、子どもや肝機能が低下している人は分解速度が遅くなります。
以下に当てはまる方も、カフェイン摂取量を減らすことが推奨されるため、コーヒーよりカフェインの少ない紅茶がおすすめです。
貧血気味の方
コーヒーやお茶に含まれるカフェインやタンニンは、鉄分の吸収を阻害する可能性があります。
タンニンも紅茶よりコーヒーに多く含まれます。
生理中の方
血管を収縮させ、子宮の血流を悪化させて生理痛を悪化させる可能性があります。
妊娠中の方
胎児はカフェインを排出しにくいため、胎盤を通じて低出生体重児などの影響を及ぼす可能性があります。
逆流性食道炎
カフェインは胃酸の分泌を促進させるため、胃酸が食道に逆流しやすくなります。
紅茶とリラックス効果
産業保健の現場で働く人の話を聞いていると、日々のストレス解消法として暴飲暴食や飲酒をしている方が多く感じます。
もちろんストレス解消は大切ですが、健康面からはあまりおすすめできない方法でもあります。
そこで、リラックス効果のある紅茶をストレスをためないためのセルフケアとしておすすめします。
紅茶や緑茶など、チャノキから作られるお茶には、リラックス効果のある「テアニン(L-テアニン)」というアミノ酸の一種が含まれています。
テアニンは、リラックス状態を示す脳波であるα波を出現させ、これが摂取後40分から2時間程度続くという研究結果もあります。
また、成分だけでなく紅茶の香りにもリラックス効果を期待できることが研究からわかりました。
三井農林株式会社と筑波大学大学院の共同研究では、ストレスを感じやすく睡眠に悩みを抱える30~40代の健康な女性を対象に、就寝時に紅茶の香りを部屋に漂わせることで睡眠にどのような影響があるかを調べました。
就寝時に紅茶の香りを嗅ぐことで期待できる効果
・ 入眠潜時および離床潜時の短縮
・ 睡眠時間の延長
・ 睡眠効率の向上
・ 主観的な睡眠の質の向上
・ 起床時の眠気改善
・ 入眠・睡眠維持の改善
・ 疲労回復
・ 睡眠時間に対する満足感の向上
・ ストレス意識の低減
こちらの実験では、ダージリン紅茶の香り成分を用いて行われました。
ダージリン紅茶には、ホトリエノールという香気成分が含まれており、これが副交感神経を高める要因になったと考えられます。
洋菓子と紅茶の組み合わせは理にかなっている?
製造過程で発酵を行う紅茶には、ポリフェノールの一種である「テアフラビン」という成分が多く含まれます。
このテアフラビンには抗酸化作用があり、脂質の吸収を抑える効果があることがわかっています。
紅茶を洋菓子のお供に飲むという方も多いかと思いますが、洋菓子は脂質が多いため、紅茶との組み合わせは理にかなっています。
洋菓子以外にも、揚げ物や中華料理など脂っこい食事と合わせて紅茶を飲むのも良いでしょう。
紅茶は含まれる栄養や香りによって心身を整え、集中力やリラックス効果をもたらす飲み物です。
紅茶の日を機に、日々の業務の合間に紅茶を選ぶことで、業務のパフォーマンス向上やほっと一息つく時間につながれば幸いです。
<参考>
・ 日本紅茶協会「紅茶の日」
・ 株式会社ハリオ商事「【コーヒー派 VS お茶派】職場の飲み物、約7割が「お茶」より「コーヒー」派!」
・ 農林水産省「カフェインの過剰摂取について」
・ 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター「カフェインと睡眠」
・ 小林加奈理、長戸有希子、青井暢之、L.R. ジュネジャ、金武祚、山本武彦、杉本助男「L-テアニンのヒトの脳波に及ぼす影響」(『日本農芸化学会誌』72巻(1998)2号)
・ 大野敦子、佐久川千津子、矢田幸博「紅茶の香りがストレス意識の高い女性の睡眠に及ぼす効果」(『におい・かおり環境学会誌』52巻(2021)2号)
・ 三井農林お茶科学研究所
・ 日本紅茶協会「脂質の消化吸収と紅茶」



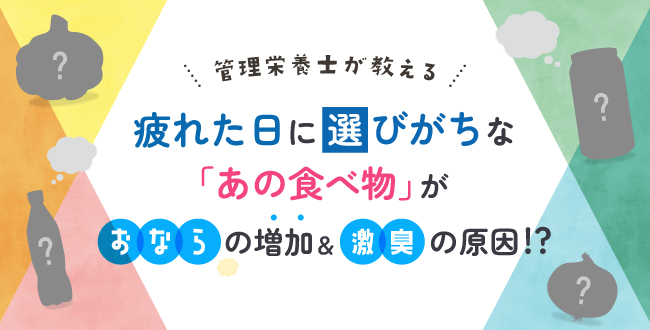



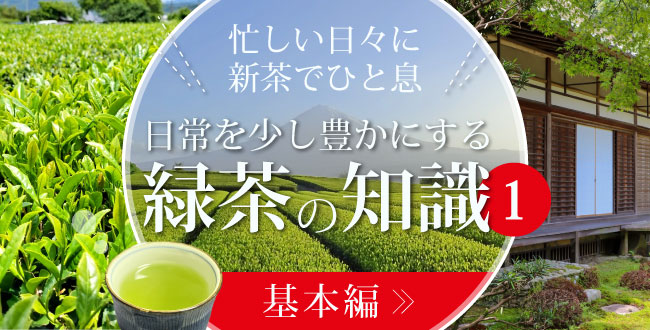

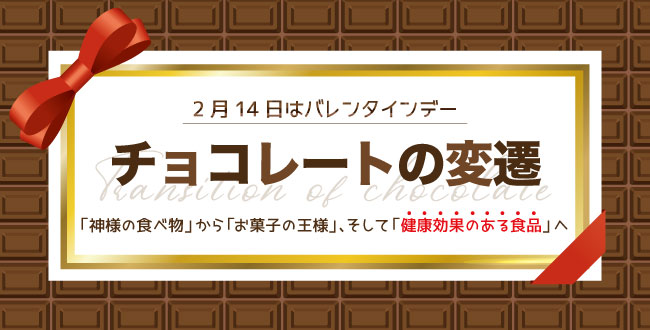
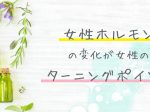








唐澤さん公益通報サムネ.jpg)