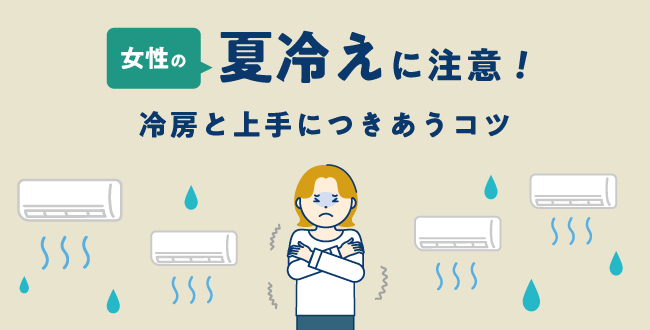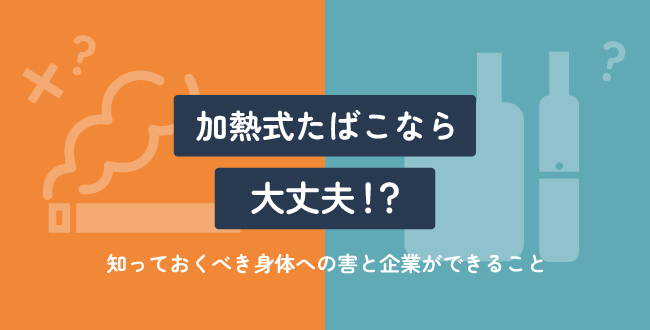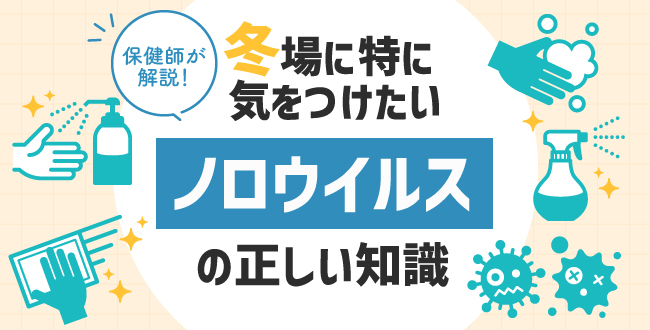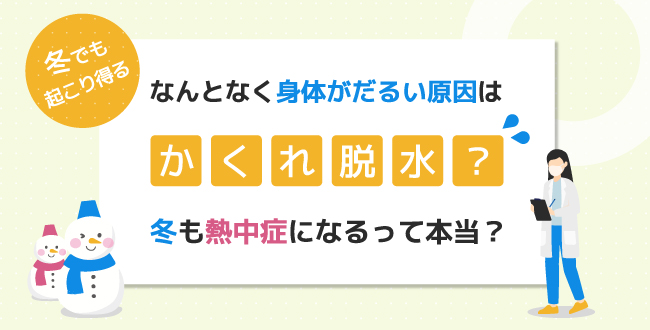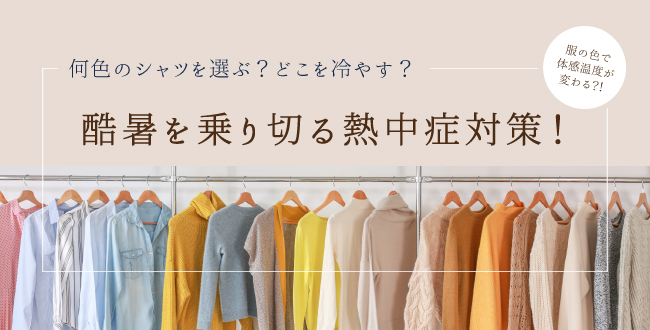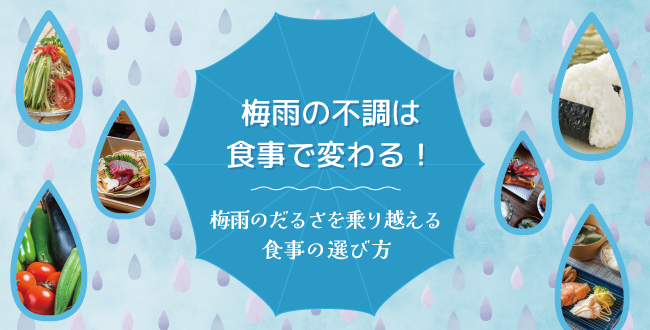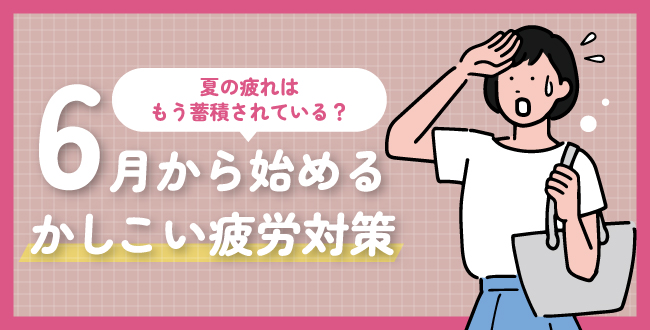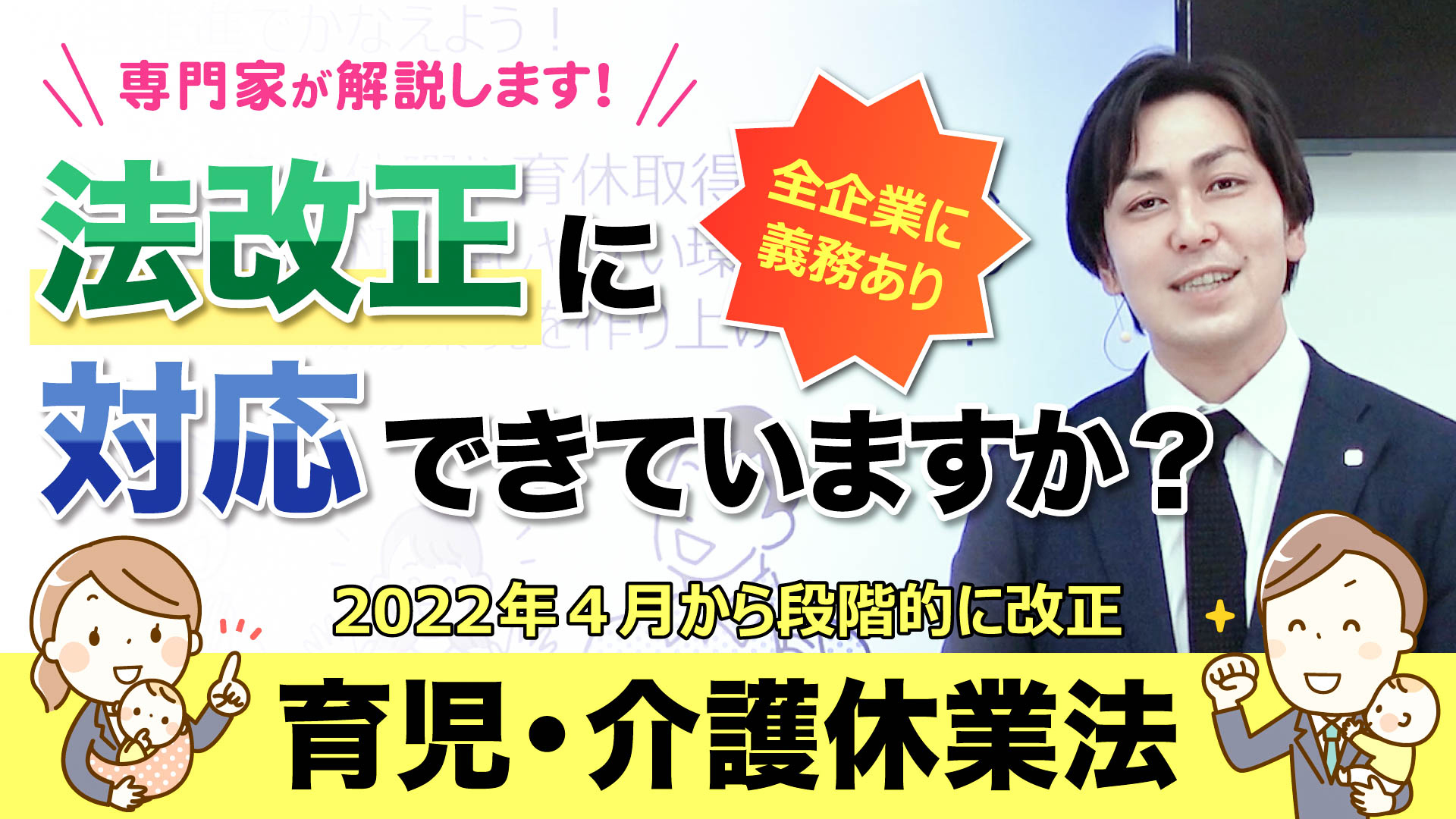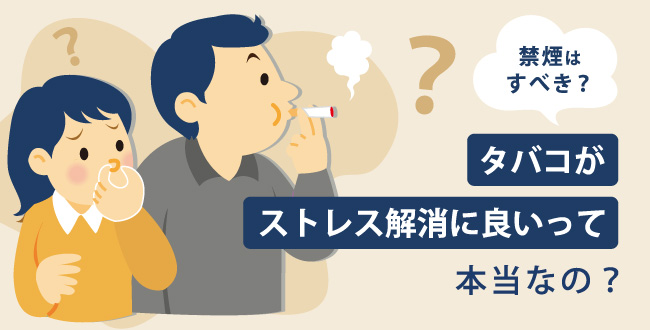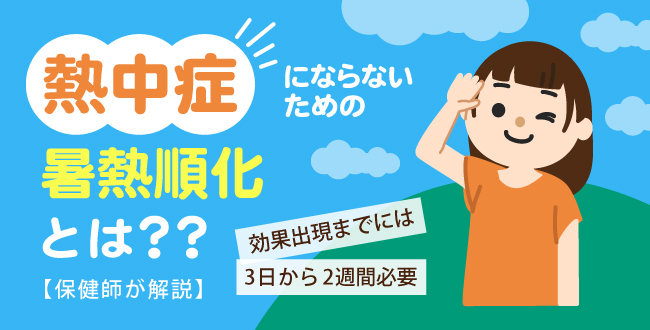
熱中症とは
日中は「暑いな」と感じる日が増えてきました。
身体が暑さに慣れていないと、熱中症になる危険性が高まります。
身体が暑さに慣れる「暑熱順化」について知り、本格的に暑くなる前から、熱中症の予防・対策を行っていきましょう。
熱中症とは、高温多湿の環境下で体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能がうまく働かなくなったりして、体温の上昇やめまいなどさまざまな症状が出現することをいいます。
運動や仕事などで身体を動かすと、体内で熱が産生されて、体温が上昇します。
汗をかくことによる「気化熱」や、心拍数の上昇や皮膚血管が拡張されることによって、身体の表面から空気中に熱を逃がす「熱放散」で体温を調節しています。
この体温調節がうまくできなくなると、熱がこもってしまい、体温が上昇して、熱中症が引き起こされるという仕組みです。
2023年(5月~9月)の全国における熱中症による救急搬送者数は91,467名で、2008年の調査開始以降2番目に多い搬送数となりました。
また、熱中症の発生場所別の救急搬送の人数を見ると、住居が1番多く、次いで屋外、仕事場となっており、都道府県別では1位東京都、2位大阪府、3位埼玉県と、人口が多いエリアが中心となっています。
暑熱順化とは
暑熱順化とは、身体が暑さに慣れることをいいます。
暑い日が続くと、身体は次第に暑さに慣れて、暑さに強くなります。
暑熱順化ができると、汗の量や皮膚の血流量が増加し、熱放散がしやすくなります。
暑熱順化に有効な対策4つ
身体を暑さに慣れさせることが重要であるため、実際に気温が上昇し、熱中症の危険性が高まる前に、無理のない範囲で汗をかくことが大切です。
日常生活の中で、運動や入浴を行って汗をかき、身体を暑さに慣れさせましょう。
熱への順化は個人差がありますが、3日から2週間で効果が現れるといわれています。
暑熱順化には、ぜひ以下の方法を試してみてください。
(1) 屋外でのウォーキング・ジョギング
帰宅時に1駅分歩く、外出時に階段を使用するなど、普段から取り入れやすい運動を意識して、少し汗ばむくらいの活動を行いましょう。
目安としては、ウォーキングは1回30分、ジョギングは1回15分で、週5回程度です。
(2) サイクリング
通勤や買い物など、日常の中で取り入れやすいサイクリングもおすすめです。
1回30分、週3回程度行うと良いでしょう。
(3) 筋トレ・ストレッチ
室内での筋トレやストレッチでも汗をかくことができます。
高温多湿の環境下で行うと熱中症のリスクが上昇しますので、室内の温度には十分注意し、脱水とならないように、水分・塩分補給も行いましょう。
(4) 入浴
シャワーだけで済ませず、湯船にお湯をはって入浴しましょう。
湯の温度が高めな場合には時間は短め、湯の温度が低めの場合は少し長めの入浴をすることがおすすめです。
また、サウナを利用するのもいいでしょう。
入浴やサウナの前後には、水分・塩分補給をしっかり行ってください。
おわりに
5月や6月でも最高気温が高い夏日や、真夏日になることがあり、梅雨が湿度が上昇します。
身体はまだ暑さに慣れていないため、気温・湿度が高くなる日に活動をするときには、屋外でも室内でも、自分の体調の変化に注意し、水分・塩分補給と適度な休憩をとるようにしましょう。
また、バランスのよい食事や、睡眠をしっかりとることも大切です。
暑熱順化は、一度暑さから遠ざかると効果はなくなってしまいます。
日ごろから暑熱順化を意識した生活習慣を送り、暑さに負けず元気な毎日を過ごしましょう。
<参考>
・ 総務省「令和5年(5月から9月)の熱中症による救急搬送状況」
・ 厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」
・ 一般財団法人日本気象協会「熱中症について学ぼう:熱中症ゼロへ」