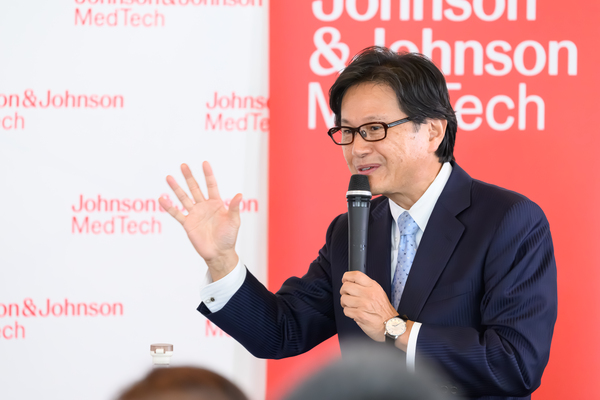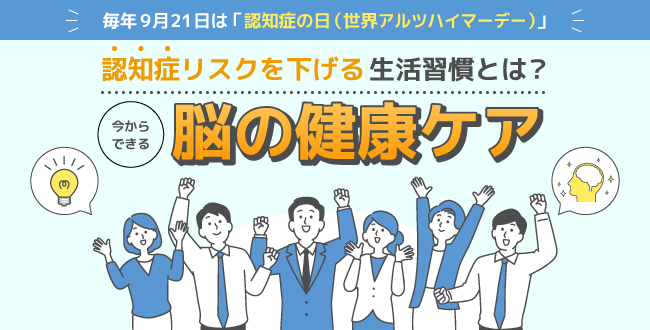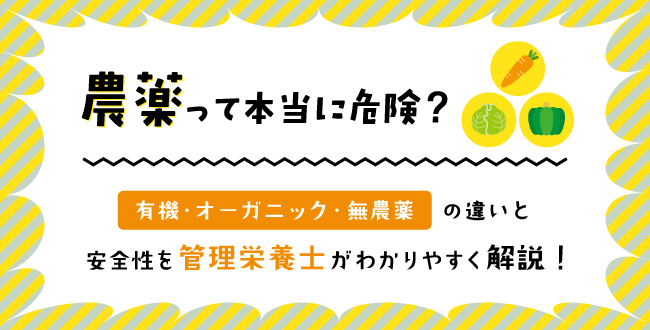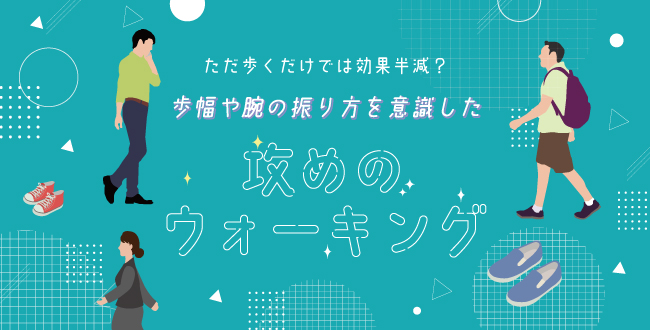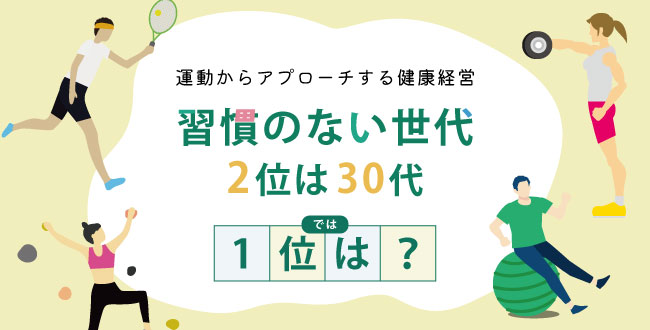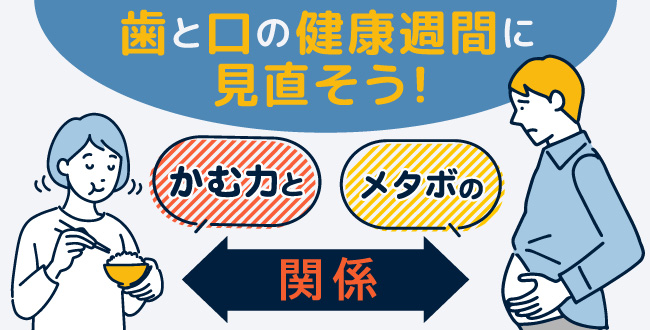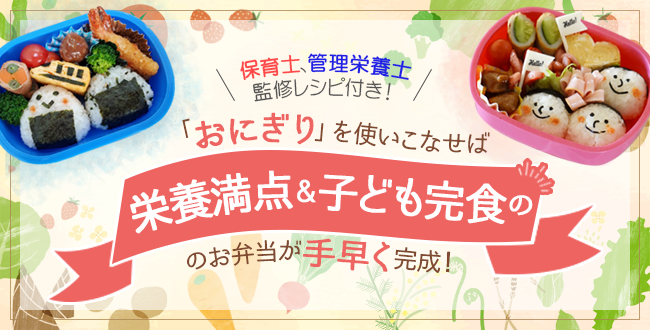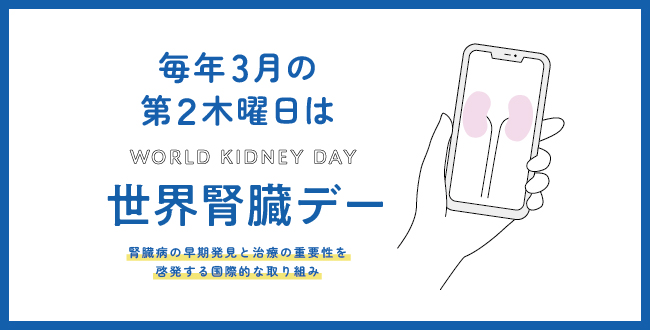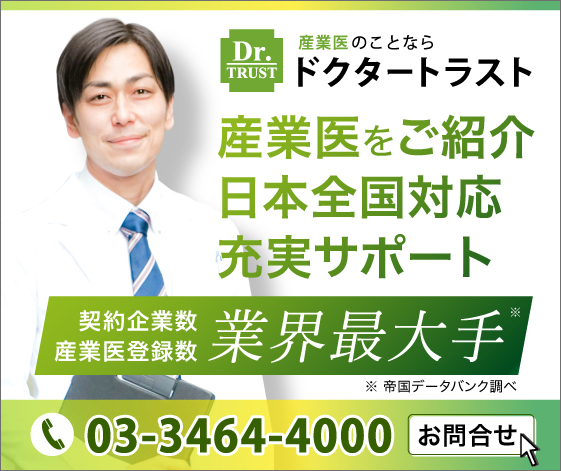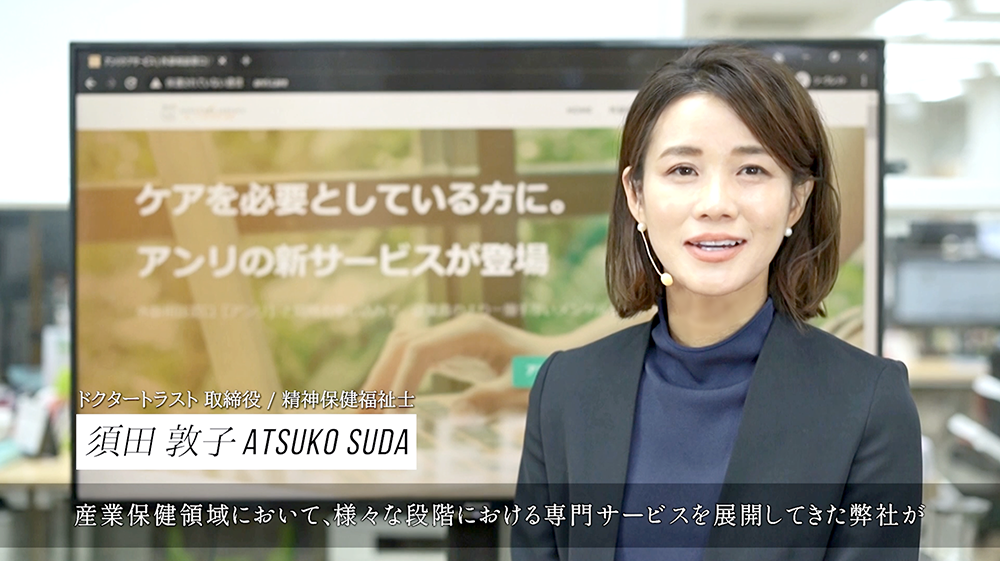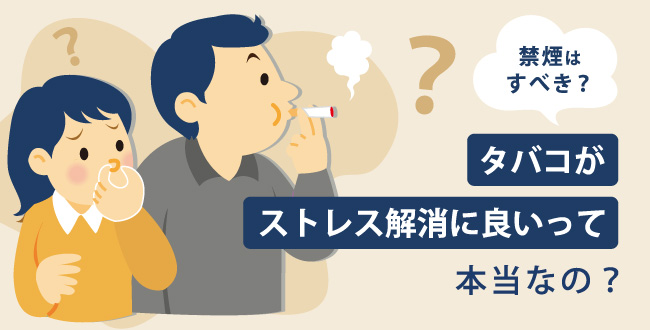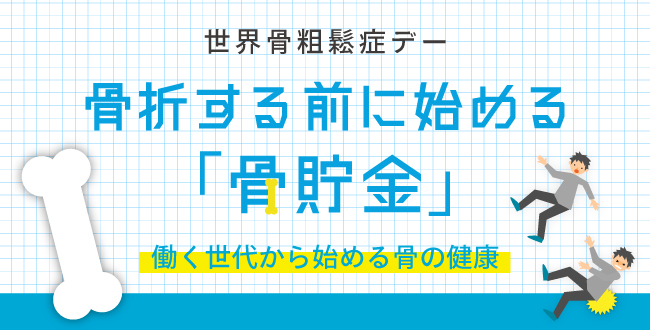
毎年10月20日は「世界骨粗鬆(しょう)症デー」。
骨の健康は、高齢になってからだけでなく、働く世代や10代、20代から意識することがとても重要です。
本記事では、10月2日にジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社で開催されたトークセッション「親子で話す骨のこと」(登壇者:慶應義塾大学医学部整形外科学教室の中村雅也教授、歌手の早見優氏)の様子を紹介し、管理栄養士目線で今日からできる骨の健康づくりの生活習慣をお伝えします。
骨粗鬆症が要介護状態を引き起こす?
骨粗鬆症とはずばり、「骨折リスクが増大した状態」です。
厚生労働省「令和5年 患者調査」によれば、骨粗鬆症で医療機関を受診している患者数は 約138万7,000人(男性約7万8,000人、女性約130万9,000人)と推計されています。(※1)
一方、骨密度検査などから潜在的な患者も含めると、2015年時点で約1,590万人が骨粗鬆症(大腿骨頸部または腰椎)の可能性があると推計されており(※2)、診断・治療を受けていない「隠れた患者」が非常に多いことがわかります。
また、年齢が高くなるほど患者数は増える傾向にあり、50歳代女性の10人に1人、60歳代女性の5人に1人、70歳代女性の3人に1人、80歳以上の女性の2人に1人が骨粗鬆症といわれています。
骨粗鬆症の恐ろしいところは、骨折するまで気づきにくいということ、そして骨折や転倒は要介護・要支援状態を引き起こすリスクが非常に高いということです。
転んで怪我をしてしまい、治療のために安静にしている中で筋肉が落ちて歩けなくなってしまう、寝たきりになってしまうというのは珍しい話ではありません。
高齢になっても自分の脚で生き生きとした生活を送るためには、できる限り早いうちから骨粗鬆症の予防をすることが非常に大切です。
家庭で話してみてほしい 骨の話
トークセッションを主催したジョンソン・エンド・ジョンソンは健康課題に広く取り組む企業で、「My Health , My self」というスローガンをもとにヘルスリテラシーの向上を掲げています。
セッションの冒頭では、同社メドテック オーソペディックス事業本部 事業本部長の渡代隆介氏が、「適切な健康情報を得る力(ヘルスリテラシー)の向上が、人生100年時代を健康で充実させるために必要」と強調しました。
では、イベントテーマにあるようになぜ、骨について親子で話す必要があるのか。
中村教授によると、骨の量が最も増える年代が10代や20代であり、その頃の生活習慣が数十年後の骨の健康に大きく影響を与えることから、「骨の健康づくりは10代、20代から始めることが重要」とのことです。
骨密度は、女性ホルモンとの関連が強く、閉経によってエストロゲンが減少することで急速に低下します。
骨粗鬆症の患者数において、女性が圧倒的に多いのはこれが理由の1つです。
一生においてもっとも骨量の多い「ピークボーンマス」を10代や20代のうちにいかに高めることができるかが大切になります。
ですので、ご自身のことはもちろん、お子さんとも一緒に骨について話してみてほしいというのが今回のテーマの理由です。
特に重要な生活習慣としては、中村教授は3つの要素をあげていました。
1日15分程度日に浴びること
紫外線を浴びることが重要なため、日傘や日焼け止めで完全にブロックすると効果が期待できません。
運動すること
特に骨に負荷を与える動作のある「階段の上り下り」がおすすめです。
バランスの良い食事をとること
カルシウムやビタミンDはもちろん、全体的な栄養バランスも重要です。糖質や脂質、リンの過剰摂取は骨に悪影響を与えるため注意しましょう。
「骨折する前から日々の生活の中で骨貯金をすることが大切」と話す中村教授
働く世代に今日から取り組んでほしいこと4選
10代、20代の時に骨のことをあまり考えられていなかったという方、これから始めるのでも遅すぎるということはありません。
以下の点を心掛けて、今日から健康的な骨づくりをしていただければと思います。
① 適切な体重管理
痩せでも肥満でも、骨粗鬆症のリスクは高まります。
BMIが18.5以上、25未満に収まるよう、体重管理に努めましょう。
② 骨に適度な刺激を与える運動を
中強度以上の筋力トレーニングと、骨への衝撃を与えるトレーニング(ランニングや階段昇降など)を組み合わせて週に2回以上行うことが理想的です。
まずは、エスカレーターではなく階段を使うなどの心がけから始めてみてはいかがでしょうか。
踏み台を購入して、自宅でトレーニングをするのもおすすめです。
③ 飲酒量を適正に
アルコール摂取量が22g/日以下で骨粗鬆症性骨折のリスクが低くなることがわかっています。
日頃お酒をたくさん飲んでいる方は、少しずつ量を減らすことをお勧めします。
ビールであれば500㎖、チューハイ類であれば350㎖がアルコール摂取量20g程度に該当します。
④ カルシウムのとれる食品を1日1品プラス
カルシウム摂取量が少ない閉経後の女性に対して、1日あたり800㎎の摂取を目指す指導を行った研究結果では、骨密度の上昇が確認されています。
ですので、年齢を重ねてからでもカルシウムをとることは効果的です。
カルシウムを多く含む食品は、納豆や豆腐、ししゃも、牛乳、ヨーグルト、小松菜、ひじきなど。
朝食に乳製品をプラスしたり、夕食に納豆や豆腐を組み合わせてみるのはいかがでしょうか。
骨の健康は、一生を通して意識することが大切です。
今日からできる小さな習慣の積み重ねが、将来の骨の健康につながります。
本記事を読んでくださった方はぜひ、今日ご家庭で骨について話してみていただければと思います。
<参考>
※1:厚生労働省「令和5年 患者調査 傷病分類編」
※2:骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会(日本骨粗鬆症学会 日本骨代謝学会 骨粗鬆症財団)編集『骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2025年版』(2025年7月、ライフサイエンス出版)