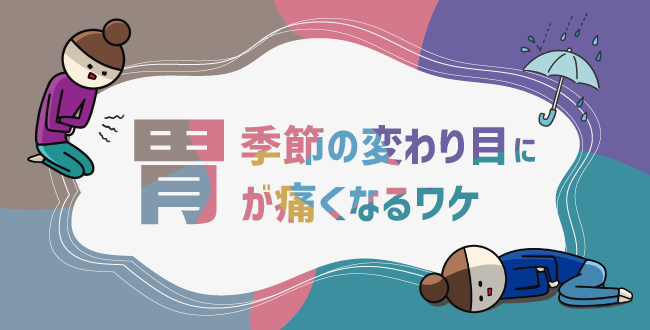毎年10月17日から23日は「薬と健康の週間」です。
これは、厚生労働省、都道府県、薬剤師会が中心となって、「医薬品や薬剤師等の専門家の役割に関する正しい知識を広く国民に浸透させることにより、国民の保健衛生の維持向上に寄与する」ことを目的として行われている全国的な啓発活動です。
薬剤師・薬局の活用方法や医薬品についての正しい知識の普及が目的とされています。
薬剤師や薬局の本当の役割とは?
薬局と聞くと「病院でもらった処方箋を出して処方薬を受け取る場所」というイメージが強いかもしれません。
しかし、薬剤師や薬局の役割はそれだけではありません。
たとえば、複数の病気で多くの薬を飲んでいる人に対しては、ポリファーマシー(多剤併用)の解消や重複投薬(複数の医療機関から同じ効能の薬が重複して処方されること)の防止を行います。
さらに、飲み忘れや使い残した薬の整理を支援する「ブラウンバッグ運動」では、自宅にある薬を薬局へ持参して薬剤師が確認することで、不要な薬を減らし、服薬の安全性を高めています。
ほかにも、服薬後の体調変化を観察し、必要に応じて医療機関への受診を勧めるといった継続的なサポートも行っています。
薬局は、風邪気味など体調不良の際に気軽に相談できる「ファーストアクセス」としても活用できます。
市販薬やサプリメントの選び方、生活習慣病のセルフケア、健康相談などを受け付けている薬局もあります。
病気や高齢などの理由により薬局へ行くことが困難な場合には、薬剤師が自宅を訪問し、薬を届けたり服薬状況を確認したりするサービスも広がっています。
自分にあった薬局選びをしましょう
また、みなさんはどのような基準で薬局を選んでいますか?
「かかりつけの病院の近くにあるから」や「自宅に近いから」といった理由で選びがちですが、実は薬局によって、機能や特徴に違いがあります。
全国の医療機関や薬局について検索ができるシステムである医療情報ネットでは、全国の薬局について住所や営業時間だけでなく、生活習慣病や介護・育児の相談可否、バリアフリー設備の有無、薬の配送サービスの有無などを調べることが可能です。
こうした情報を活用して、自分の生活スタイルや健康課題に合った「かかりつけ薬局」を見つけておくと、日常的に薬剤師へ相談できる安心感が得られます。
ウェブサイトやお薬手帳を活用しましょう
最近は、インターネットを利用すれば簡単に薬が手に入るようになりました。
その結果、個人輸入薬による健康被害などの問題も起きています。
薬に関する正しい情報が欲しいときに日常生活で活用できるウェブサイトとして、厚生労働省ではおくすりe情報を運営しています。
ここでは、薬に関する最新の話題や法令、厚生労働省からのお知らせ・注意喚起が載っています。
普段からチェックしておくと、いざというとき安心です。
また、自分の薬の情報を整理するうえで欠かせないのが「お薬手帳」です。
処方内容や服薬状況を一元管理でき、複数の医療機関を受診するときや新しく処方を受けるときにも大変役立ちます。
マイナ保険証で過去の薬剤情報が確認できるようになってはいますが、登録されるまでにタイムラグがあることやアレルギー・副作用歴の情報などは反映されないことを考えると、今後もお薬手帳の併用が望ましいです。
災害時や急病時にも迅速な対応につながるため、持ち歩く習慣をつけましょう。
スマートフォン上で管理できる電子版お薬手帳も普及が進んできていますので、ご自身の生活と合わせてご活用いただけるとよいと思います。
まとめ
「薬と健康の週間」は、薬について学び直す良いきっかけです。
お薬手帳を活用して服薬情報を整理したり、かかりつけ薬剤師を持って日常的に相談できる関係を築いたりすることは、働く世代の皆さまにとって強い味方になります。
薬と健康の週間をきっかけに、一人ひとりが薬との付き合い方を見直し、より安心で健やかな生活につなげていきましょう。
<参考>
厚生労働省「令和7年度『薬と健康の週間』の実施について」
厚生労働省「電子版お薬手帳」



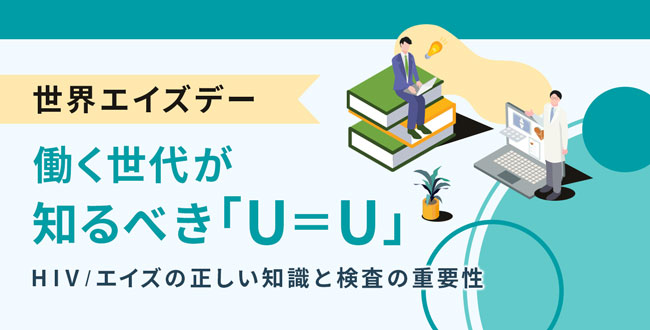




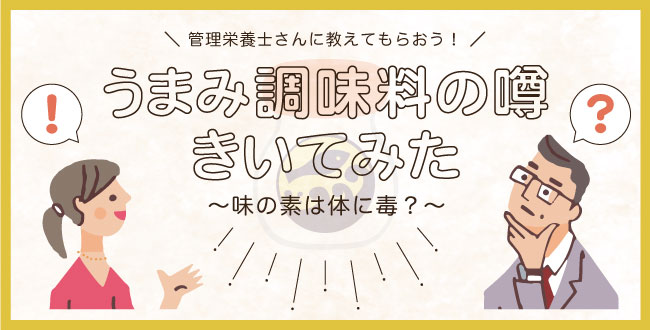





唐澤さん公益通報サムネ.jpg)