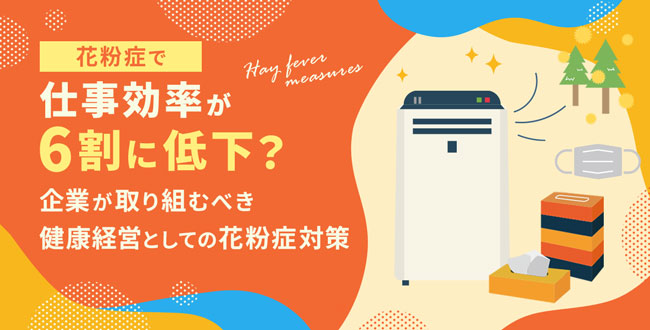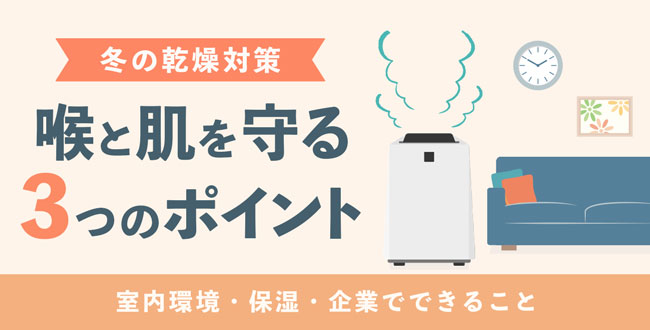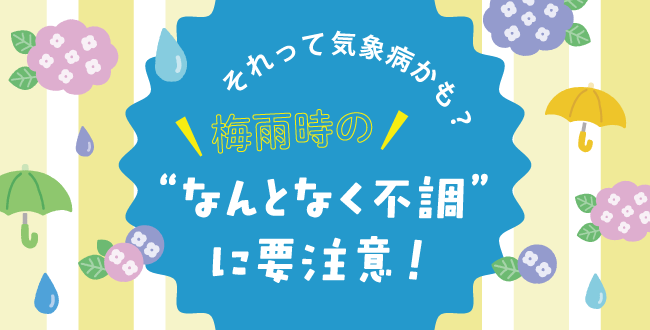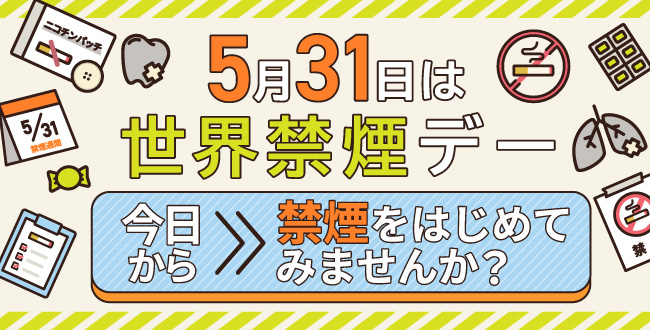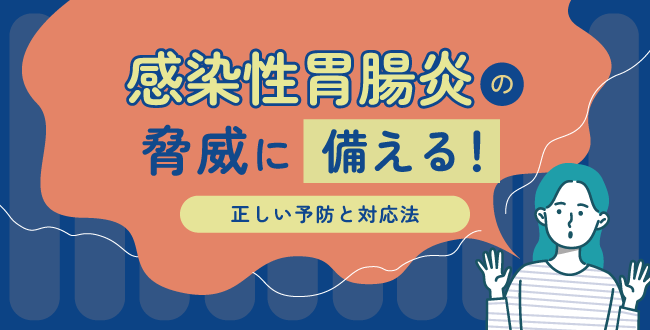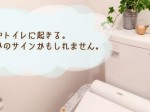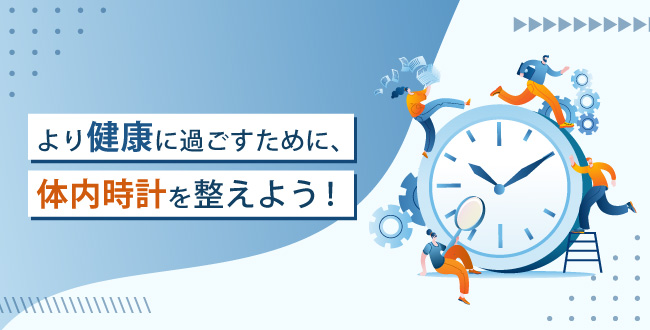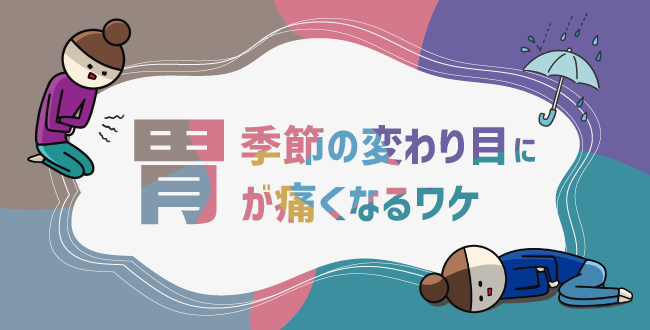「目の愛護デー」とは?
10月10日は「目の愛護デー」です。
目の健康に関心を持ち、日ごろから目を大切にすることを呼びかける日として、各地でイベントが行われています。
由来には、10月10日を横に倒すと人の目と眉の形に見えることから、この日が制定されました。
現代人にとって、仕事や日常生活の中で、スマートフォンやパソコンの使用時間が増えるなか、目の疲れや視力低下は大きな健康課題の一つではないでしょうか。
働き方と目の健康リスク
近年、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを長時間使用する「VDT作業」が日常化しており、日常生活や職場においてVDT作業が増加する中、それに伴い「VDT症候群」を訴える労働者も増えています。
厚生労働省の調査によると、VDT作業に従事している人の約7割が目の不快感や疲れを自覚しており、中でも「眼精疲労」や「ドライアイ」は代表的な症状です。
VDT症候群の主な症状には、「目の疲れや痛み」「かすみ」「充血」などの視覚的な不調に加え、ドライアイによる乾燥感や異物感が慢性的に続くこともあります。
さらに、これらの目の症状が悪化することで、肩こりや腰痛といった筋骨格系の問題、集中力の低下や不眠、ストレスの増加といったメンタル面への影響も生じる可能性があります。
しかし、こうした目のトラブルは軽視されがちです。
「一時的な疲れ」と見過ごされ、症状が悪化してから受診するケースも少なくありません。
VDT症候群の症状を放置してしまうと、単に症状に悩まされるだけでなく、仕事のパフォーマンスや日常生活の質が低下する可能性があります。
そのような状態で仕事を続けることで、業務上のミスや事故のリスクが高まるおそれもあるため、早期の対処が重要です。
職場でできる目のケア
目の健康を守るためには、日常生活や職場環境の中にちょっとした工夫を取り入れることが大切です。
個人での対策はもちろん、企業側が目の健康を守るために行動を起こすことも一つです。
1. 作業環境の整備
モニターの位置や明るさ、作業距離、照明の反射などは、目に直接影響を与える要素です。
たとえば、モニターの高さが合っていないと、自然と目を大きく開けたり下を向きがちになり、乾燥や疲労を招きます。
照明の配置やブラインドの使い方なども含めて環境の改善を見直すことがポイントです。
2. 作業姿勢の見直し
意外と見落とされがちなのが姿勢の影響です。
猫背や前傾姿勢が続くと、首や肩だけでなく目にも負担がかかります。
正しい椅子の高さ、モニターとの距離、足の位置などを正しく理解することや乱れたときに正しい姿勢を取ることで、目の疲労だけでなく体の疲労も軽減されます。
3. 「目の休息」を促す取り組み
厚生労働省では、VDT作業において「1時間作業ごとに10~15分程度の休憩をとる」ことを推奨しています。
「眼球運動」
目を上下・左右・円を描くようにゆっくり動かす簡単な体操で、目の周囲の筋肉をほぐし、血行を促進します。
加えて、運動の合間に少し遠くを見ることで、緊張していたピント調節機能(毛様体筋)をリラックスさせる効果があります。
デスクワークの合間や休憩時間に1セット(各方向に3回程度)を取り入れると、目の疲れの軽減につながります。
目の乾きには「意識的なまばたき」や「加湿」
まばたきの回数が減ると目が乾きやすくなるため、意識的にまばたきを行うことが効果的です。
また、エアコンの風が直接当たらないようにする、加湿器を活用するなどの工夫も、ドライアイの予防につながります。
「ホットアイマスク」の活用
目の周囲を温めることで、眼の筋肉の緊張がほぐれ、血行が促進されます。
これにより疲れが取れやすくなり、休憩中のリラックスにもつながります。
市販のホットアイマスクのほか、水で濡らしたタオルを電子レンジで温めて使用するのも手軽で効果的です。
4. 企業でも取り組めること
目の健康に関する健康教育や情報の啓発は、VDT症候群の予防・対策として効果的です。
企業が主体的に取り組むことで、従業員の健康意識を高め、生産性の維持・向上にもつながります。
たとえば、適切な度数のコンタクトレンズ・眼鏡の使用や調整を促すことは、眼精疲労やドライアイの軽減に有効です。
さらに、長時間同じ姿勢で作業を続けることによる肩こりや首の疲労を防ぐために、軽いストレッチや体操を推奨するのも効果的です。
また、講話やポスター掲示、社内報での特集などを通じて、目の健康を身近なテーマとして浸透させることも重要です。
さいごに
スマートフォンやパソコンなどの機器は、今や私たちの生活に欠かせない存在となっています。
仕事や日常生活で長時間使用することが増え、知らず知らずのうちに目に大きな負担がかかっていることも少なくありません。
今回の内容をきっかけに、ぜひご自身の目の健康を見直し、日々のケアを心がけていただければと思います。
<参考>
・ 厚生労働省「平成20年技術革新と労働に関する実態調査結果の概況」
・ 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(PDF)」
・ 政府広報オンライン「目の愛護デー」