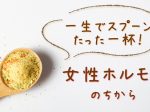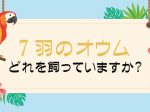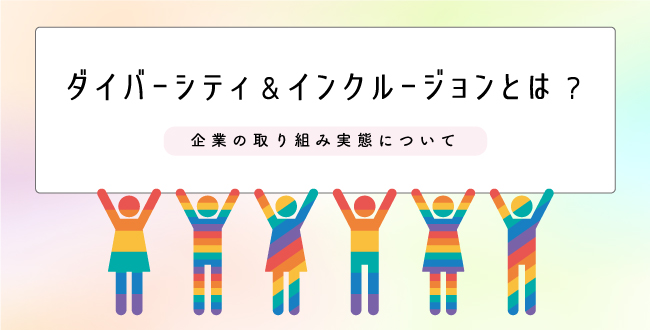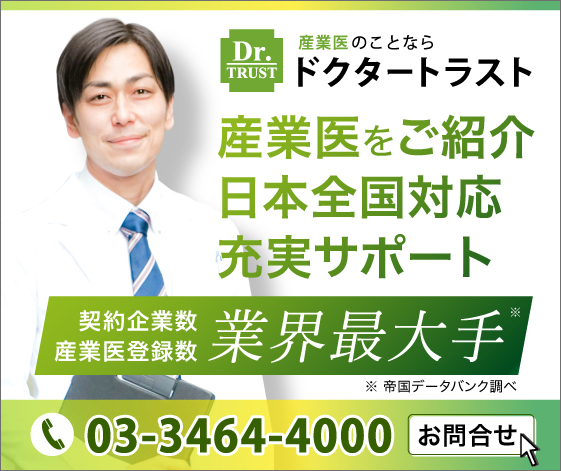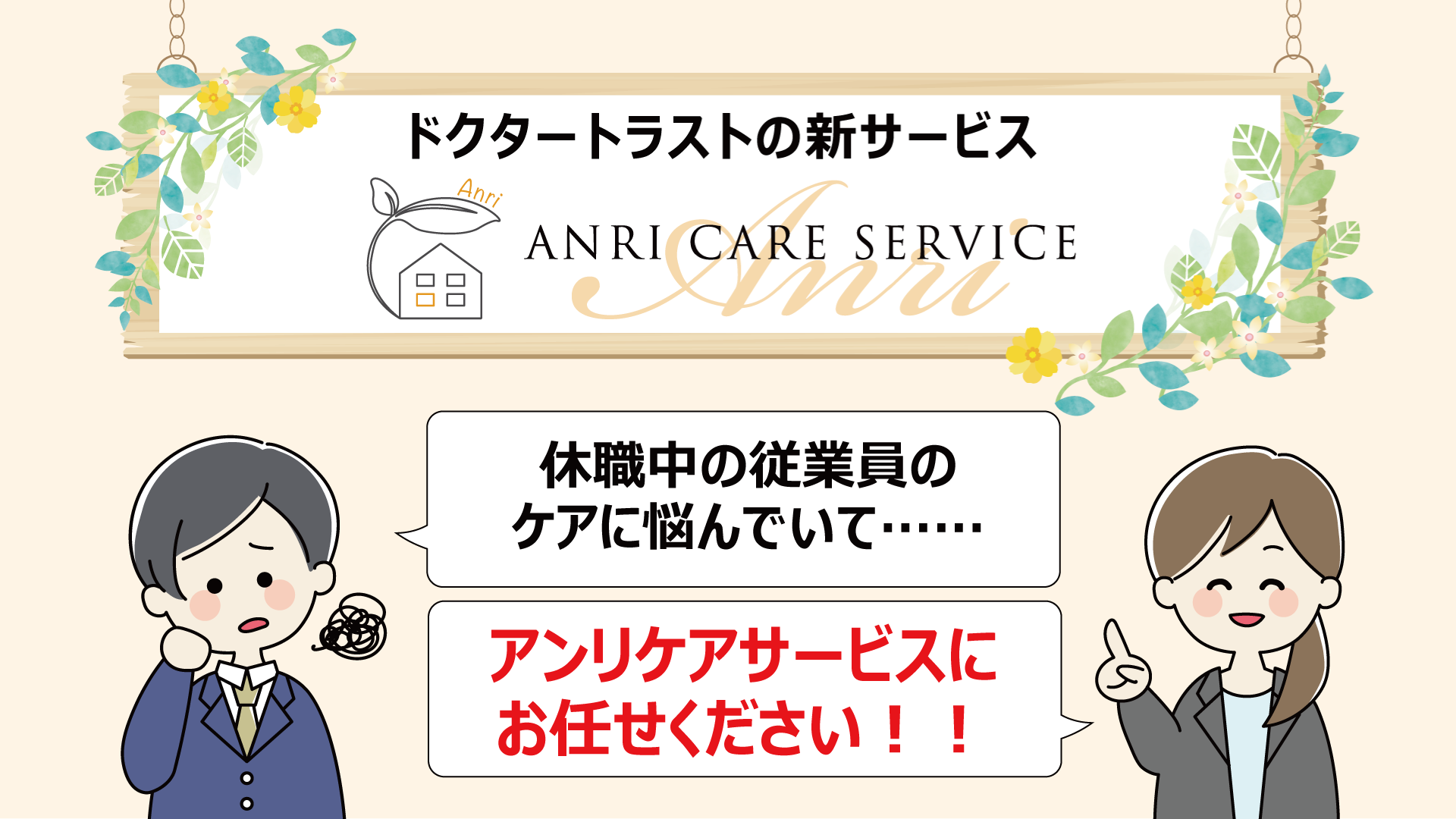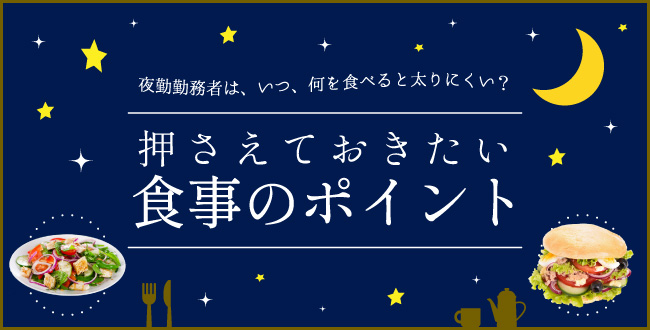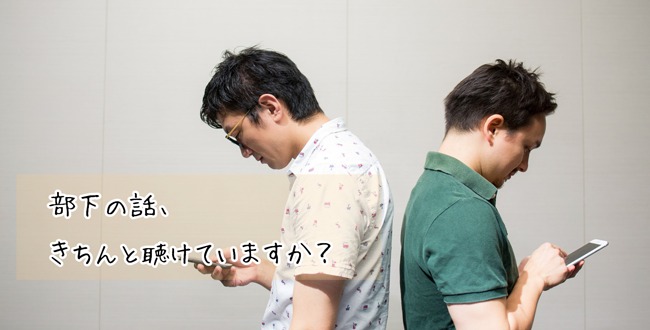
思い込みや勝手な判断をしてしまいがち
相手をありのまま受け止めることは大事と言われていますが、相手が部下となると、指示や確認ばかりになっていませんか?
医師が問診をしないと診断ができないように、上司も部下の話を聴かなければ的確な指導をすることはできません。
自分では部下の話を聴いているつもりでも、実は正しく聴けていない…という上司も少なくないのではないでしょうか。
このような聴き方に心当たりはありませんか?
① 矢継ぎ早に根掘り葉掘り聴く
② 勝手に分析する
③ 自分の経験談を話し出す
④ 批判、説教を始める
⑤ 過剰に同意、同情する
⑥ 話をはぐらかす
部下の話を聴くときは、アドバイスも説教も不要です。
話を聴いている途中でアドバイスや説教に走ってしまうのは、聴き手ではなく語り手になっている状態といえるでしょう。
まずは、聴き手に徹し、きちんと「傾聴」することがコミュニケーションの第一歩です。
相手を理解する3つの方法
相手を理解するには、次の3つの方法があるといわれています。
1.相手についての情報を理解する方法
情報とは、年齢、職業、学歴、地位、生育歴、家族などのデータです。
2.準拠枠で相手を理解する方法
準拠枠とは、自分の関心、経験、価値観、感情、知識、想像力などです。
準拠枠は、コミュニケーションでもっとも多く用いられるものですが、思い込みや決めつけ(先入観やレッテルともいう)になりやすいものです。
3.相手とともに理解していく方法
自分の準拠枠を外し、相手に寄り添い、相手が何をどのように感じているのか、相手の世界を内側から理解することです。
傾聴には、2の準拠枠を外し、3の相手に寄り添い、相手を内側から理解するような姿勢が必要です。
傾聴は、「耳」「目」「心」で
傾聴の「聴」という字は、「耳」「目」「心」から成り立っています。
声を耳に入れ、目で相手をしっかり見て、言葉の裏にある思いや心を理解する。これが傾聴です。
以下のような対応は、部下の気づきや学びの機会を奪い、モチベーションを下げてしまいます。
● 感情的に怒って人格否定してしまう
例)「君はそんなことばかり言ってるから、いつまでたってもダメなんだ」
● 過去の失敗に終始して、未来に目が向いていない
例)「俺の指示と違うだろ。何でそんなことをしたんだ」
● 納得していない目標を強引に押しつける
例)「目標の数字は達成できるんだろうな。できなかったら、わかってるよな」
このとき、部下はどのような気持ちでしょうか?
部下は、自ら問題に気づく能力をもっているものです。
部下の本当の力を引き出すために
トヨタ自動車の張富士夫名誉会長は、トヨタ自動車の人の育て方について、求める結果だけ伝えて、やり方は自分で考えさせるというのが徹底していたと述べています。
「ほんとうに困ったら、相談に来い」と言うのですが、誰も相談に行かずに自分で考えたといいます。
もちろん、マネジメントは傾聴だけで完成するものではありません。
指示命令、指摘、アドバイス、また、時には否定や批判が必要な場面もあるでしょう。
しかし、それらの行為は、すべて傾聴という前提の姿勢があってこそ成り立つものです。
部下には部下なりの考えや意図があるもの。
一人の人間として部下を尊重し、相手の話をしっかりと聴き、思いをありのままに吐露できるという安心感があってこそ、部下の本当の力を引き出すことができます。
部下とのコミュニケーションがうまくいっていないなぁと感じる時には、まず部下の声を耳に入れ、目で相手をしっかり見て、言葉の裏にある思いや心を理解することを意識してみることも一つの方法です。