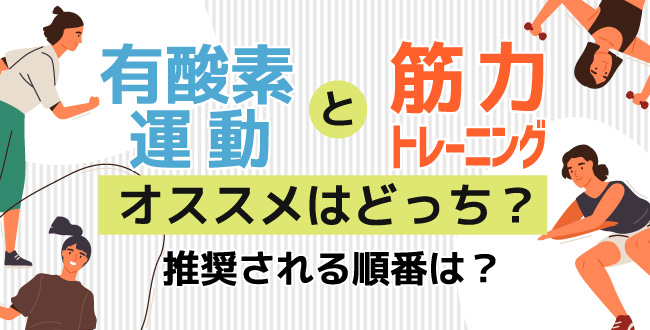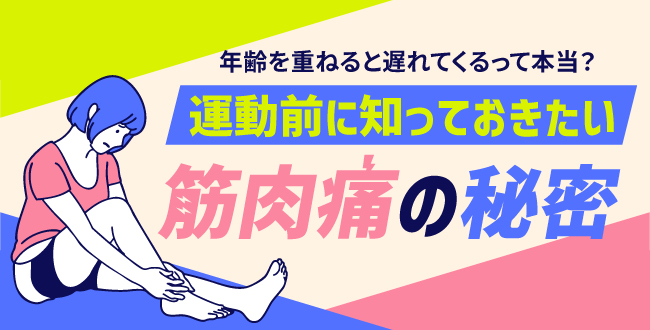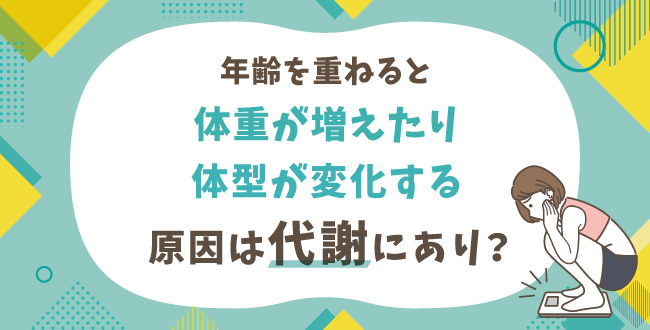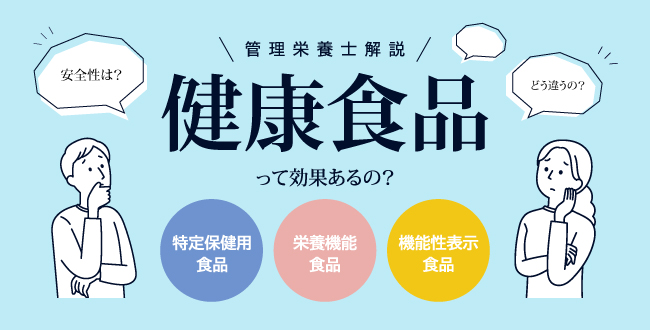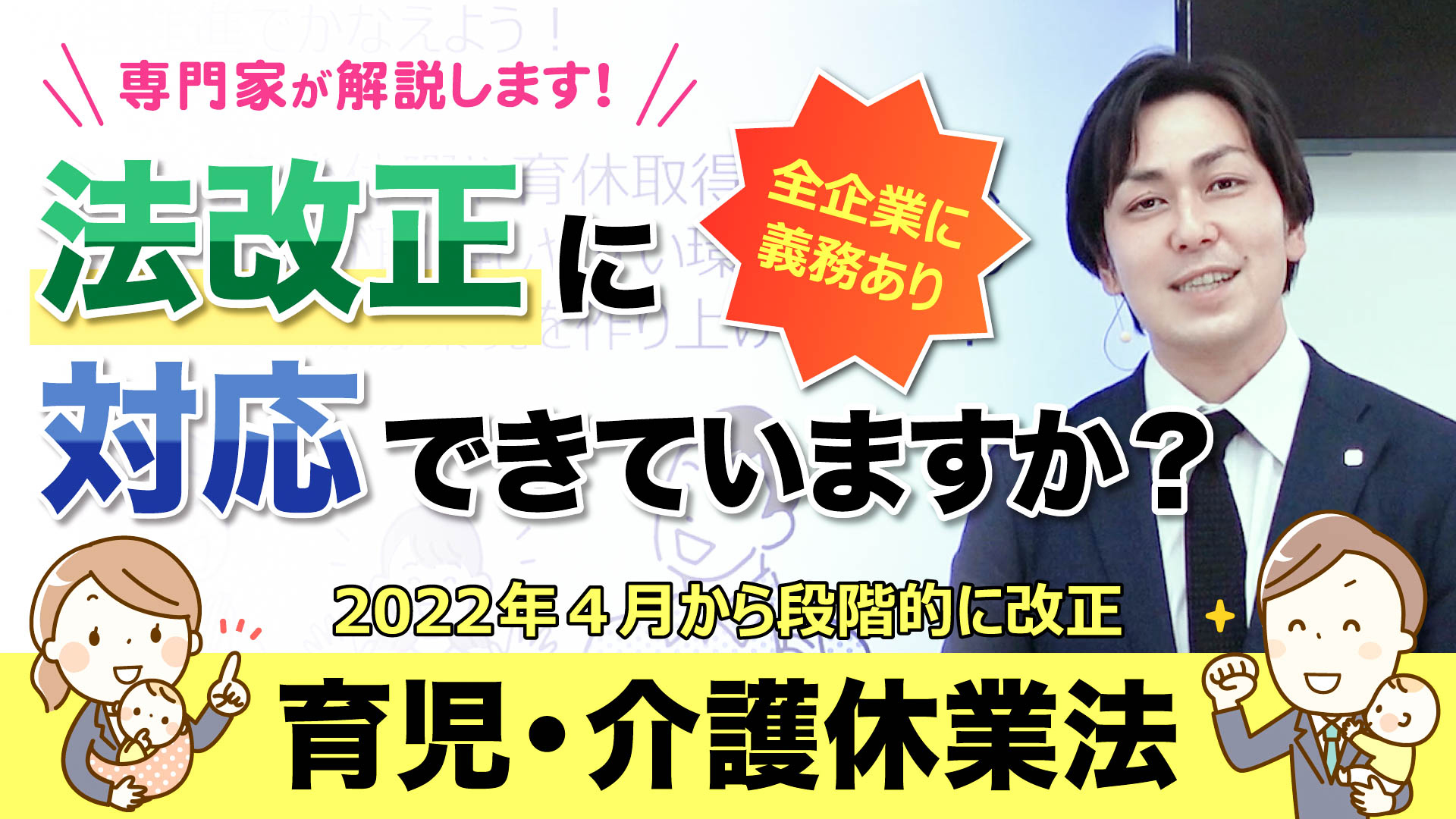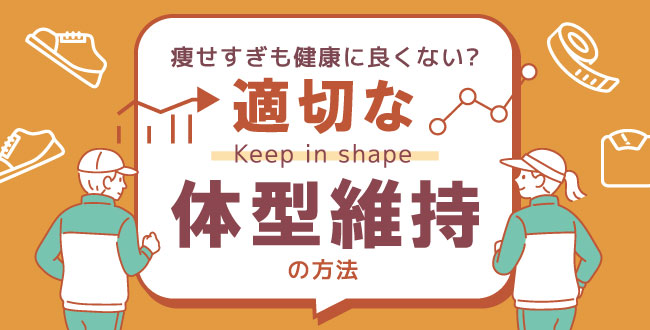
健康的な体型と聞くと、多くの人が「太りすぎないこと」をイメージするのではないでしょうか。
しかし、実は「痩せすぎ」もまた、健康に悪影響を及ぼすことがあります。
極端なダイエットや不健康な食生活によって、意図せず痩せすぎてしまう人も少なくありません。
この記事では、痩せすぎが健康にどのようなリスクをもたらすのかを解説し、最も大切な「適切な体型」を維持するための具体的な方法をご紹介します。
痩せすぎがもたらす健康リスク
見過ごされがちな「痩せすぎ」は、深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。
特に若い女性に多く見られる傾向ですが、性別や年齢に関わらず注意が必要です。
<痩せすぎの健康リスク>
・ 免疫力の低下:必要な栄養素(特にタンパク質やビタミン、ミネラル)が不足することで、免疫細胞が十分に機能せず、風邪や感染症にかかりやすくなります。
・ 骨密度の低下(骨粗しょう症のリスク):カルシウムやビタミンDなどの摂取不足、女性ホルモンの分泌低下により、骨がもろくなり、若い世代でも骨粗しょう症や骨折のリスクが高まります。
・ 貧血:鉄分やビタミンB12などの不足により、貧血になりやすく、倦怠感、めまい、息切れなどの症状が現れます。
・ 筋力低下・疲れやすさ:エネルギー不足やタンパク質不足により筋肉量が減少し、体が疲れやすくなったり、基礎代謝が落ちやすくなったりします。
・ 生殖機能への影響(特に女性):ホルモンバランスが崩れ、月経不順や無月経になることがあります。将来の妊娠・出産にも影響を及ぼす可能性があります。
・ 体温調節機能の低下:体脂肪が少ないと、体温を維持しにくくなり、寒さを感じやすくなったり、体調を崩しやすくなったりします。
・ 精神的負担:痩せることへの強迫観念や、ボディイメージの歪みから、摂食障害(拒食症・過食症)などの精神疾患につながることもあります。
適切な体型とは? BMIと体脂肪率の活用
太りすぎでも痩せすぎでもない「適切な体型」を知る指標として、BMI(Body Mass Index)と体脂肪率があります。
BMI(ボディマス指数)
BMIは、以下から算出される国際的な肥満度を表す指標です。
BMI = 体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)
<BMIの目安>
・ 18.5未満:低体重
・ 18.5以上25未満: 普通体重
・ 25以上: 肥満
ご自身のBMIを計算し、「普通体重」の範囲内を目指しましょう。
<参考>
直近5年分の平均BMIの推移は以下でご紹介しています。
体脂肪率
体脂肪率は、体重に占める脂肪の割合です。
BMIが普通体重でも、筋肉量が少なく体脂肪率が高い「隠れ肥満」の場合もあります。
・ 男性:10〜20%程度が標準
・ 女性:20〜30%程度が標準
BMIと体脂肪率の両方を参考にすることで、より正確に自分の体型を把握し、適切な目標設定ができます。
適切な体型を維持するための適切な運動習慣
理想の体型を維持するためには、体重という数字のみに注目するのではなく、体型や見た目の変化なども加味して理想の体型を目指しましょう。
特に今回は筋肉をつけることによって理想の体型を目指します。
有酸素運動
ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、長時間続けられる運動は、脂肪燃焼効果が高く、心肺機能の向上にもつながります。
週に150分(30分×5日など)を目安に、無理のない範囲で継続しましょう。
筋力トレーニング
スクワット、プッシュアップ(腕立て伏せ)、プランクなど、自分の体重を使った自重トレーニングでも効果は十分にあります。
筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、痩せやすく太りにくい体になります。
週に2〜3回、大きな筋肉(背中の筋肉や下半身の筋肉)を中心に全身をバランス良く鍛えることを目指しましょう。
ストレッチ
運動前後のウォーミングアップ・クールダウンだけでなく、日中の隙間時間にも取り入れることで、柔軟性が高まり、怪我の予防や疲労回復に役立ちます。
※
太りすぎも痩せすぎも、どちらも健康リスクをはらんでいます。大切なのは、自分にとっての「健康的な体重」と「活動レベル」を見つけることです。
数字にとらわれすぎず、体が軽く感じ、ポジティブな気持ちで毎日を過ごせるようなバランスを見つけることが、適切な体型維持の秘訣です。
焦らず、楽しみながら、これらの習慣を日々の生活に取り入れてみてください。
<参考>
・ 厚生労働省「若い女性の『やせ』と健康・栄養問題」
・ 厚生労働省「肥満と健康」
・ 厚生労働省「肥満と肥満症」
・ 厚生労働省「糖尿病」