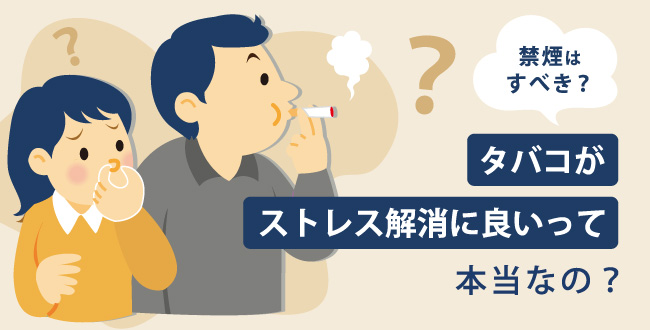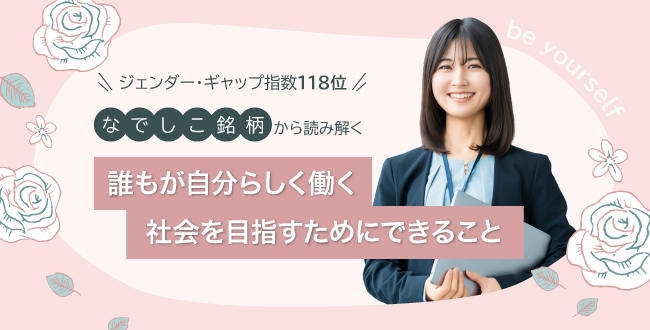
世界経済フォーラムが毎年発表している「ジェンダー・ギャップ指数(GGI)」は、経済、教育、健康、政治の分野毎に男女格差を数値化して表しています。
2024年の日本の総合順位は146か国中、118位と非常に低い順位で、分野ごとの順位で最も低かったのは経済の120位と、日本は国際的に見ても特に経済界において男女格差が大きい国ということがわかります。
そこで経済産業省と東京証券取引所が共同で、女性活躍推進に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力のある銘柄として紹介することで、企業への投資を促進し、各社の取組を加速化していくことを狙いとし、2012年より「なでしこ銘柄」の選定を行っています。
「なでしこ銘柄」は企業・投資家・労働者の三者間でメリットがあり、日本のジェンダー・ギャップ指数の経済分野の順位上昇に好影響を及ぼすことや、日本経済の持続的成長を後押しするため、多様な人材の活躍を推進する「ダイバーシティ経営」の一環の取組として行われています。
令和6年度版「なでしこ銘柄」
令和6年度の「なでしこ銘柄」では「採用から登用まで一貫したキャリア形成支援」と「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」を両論で進めた企業が計210社応募しており、その中から23社選定されました。
今年度は以下の2点が重視されています。
(1)「採用から登用までの一貫したキャリア形成支援」「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」に関する取組・成果が、どちらも優れていること
(2)経営戦略と女性活躍を含む人材戦略との結びつき、それによる企業価値向上が自社独自のストーリーとして語られえていること
また令和5年度版より選定が開始された「Nextなでしこ共働き・共育て支援企業」では「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」が優れた企業が計255社応募し、特に優れた企業として16社が選定されました。
出産・育児などを希望する女性のキャリアの中断は、女性活躍が進まない大きな原因の一つだと経済産業省はしており、これを解消するための取組を重点的に評価するために以下の2点を重視しました。
(1)共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援を推進しているか
(2)共働き・共育てをする従業員に限らず、全ての従業員が自分の望む働き方を選択できる環境作りを推進しているか
令和6年度版「なでしこ銘柄」選定企業の取組事例:株式会社 資生堂
株式会社資生堂(以下、資生堂)は、企業使命に「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)」を掲げており、それを実現する中で最も重要だとしているのが、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)です。
一人ひとりが尊重され、誰もが活躍できる多様性に富んだ社会を目指すため、「あらゆる階層における女性比率50%(対象:国内資生堂グループ)」を2005年に設定しました。
2005年の設定当初は管理者全体で5.3%だったのにも関わらず、2024年には管理者全体で40.0%を達成し、2030年には50%を目標にしています。
また「男性育児休業取得率100%(対象:国内資生堂グループ)」を2021年末に設定をし、設定年である2021年には34.3%であったのが2023年末には100%を達成するなどしています。
資生堂の具体的な取組として「資生堂DE&Iラボ」が挙げられます。
「資生堂DE&Iラボ」とは多様な人財の活躍と企業成長の関係を研究する研究機関であり、2024年に「資生堂DE&Iラボサイト」を開設、多様な人材活躍と企業成長の関係についての実証研究で得た結果を公表しています。
興味深いテーマとしては、東京大学大学院経済学研究科の山口慎太郎教授チームとの共同研究「女性活躍推進から『ジェンダー平等』へ ~ジェンダー不平等を解消するために~」などが挙げられます。
成果を出す能力にジェンダー差はあるかの検証や「役割」の与えられ方にジェンダーによる差はあるのかの検証などがなされています。
令和6年度版「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業選定企業」の取組事例:大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(以下、大阪ガス)では多様な人材の経験や価値観の掛け合わせが、非連続なイノベーションを生み企業価値を高めるとして、2014年にダイバーシティ推進センターを設置したうえでDE&Iを推進しています。
男性従業員の割合が高い大阪ガスでは、女性活躍推進がDE&Iの第一歩と位置付け、女性が「働き続ける」ための制度と限られた時間でも「働きがい」を感じられるような環境設備を整え、また現在では性別を問わず「働きがい」「働きやすさ」を感じる職場環境を目指しています。
具体的な取組として、柔軟な働き方を推進しており、ライフイベントなどに限定せずフレックスや在宅勤務、法定以上の休業期間(子が3歳まで)や、時短勤務制度(子が小3まで)を利用できます。
また、ライフイベントなどの理由で居住地と勤務地が遠隔になる場合にリモートワークでの就労を可能としたり、配偶者の海外勤務を考慮した海外帯同休職を設けたりすることで離職やキャリア断絶を防いでいます。
さらに会社全体で共働き・共育ての理解を深めるために研修や講習会も開催しています。
これらの働きによって、子育て中の女性社員の管理者登用の増加や、2023年度の男性の育児休業取得率が109%、平均取得日数が約1ヵ月であり、全世代に対する仕事や就業環境に対する従業員意識調査でも総合4指標は世間水準よりも高く推移しています。
さいごに
女性活躍というテーマは、単に「女性をもっと働かせよう」という話ではなく、むしろ誰もがライフイベントに縛られず、自分らしく働ける社会をどうつくっていくかという、もっと広く深い問いだと感じます。
今回の「なでしこ銘柄」などの事例からもわかるように、企業が柔軟な働き方や公平なキャリア支援に本気で取り組めば、性別に関係なく多くの人が力を発揮できるようになります。
それは結果的に、企業の成長や日本全体の成長にもつながっていくはずです。
また、性別問わず育児や介護など多様なライフスタイルを選ぶ時代において、職場がそれを支える存在であることは、従業員のエンゲージメントや定着率の向上にも直結します。
人手不足が課題となる中、優秀な人材を惹きつけ、長く活躍してもらうためにも、多様性に配慮した働き方の整備は避けて通れないはずです。
これからの時代、性別にとらわれず、多様な人が当たり前に活躍できる組織がスタンダードになっていくからこそ、女性活躍を「特別なこと」とせず、「当たり前の選択肢」として根付かせていくことが、今の私たちに求められているのではないでしょうか。
<参考>
・ 経済産業省「ダイバーシティ経営の推進」
・ 経済産業省「女性活躍に優れた上場企業を選定「なでしこ銘柄」」
・ 内閣府「男女共同参画に関する国際的な指数」
・ 中西哲「女性活躍推進に向けた我が国の課題」(『跡見学園女子大学マネジメント学部紀要』第31号、57-67頁、2021年)
・ 経済産業省「令和5年度「なでしこ銘柄」レポート(PDF)」
・ 経済産業省「令和6年度「なでしこ銘柄」選定企業事例集(PDF)」
・ 経済産業省「令和6年度「なでしこ銘柄」レポート(PDF)」
・ 経済産業省「令和6年度「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」事例集(PDF)」
・ 株式会社資生堂「女性活躍推進から「ジェンダー平等」へ(前編)~ジェンダー平等を解消するために~」



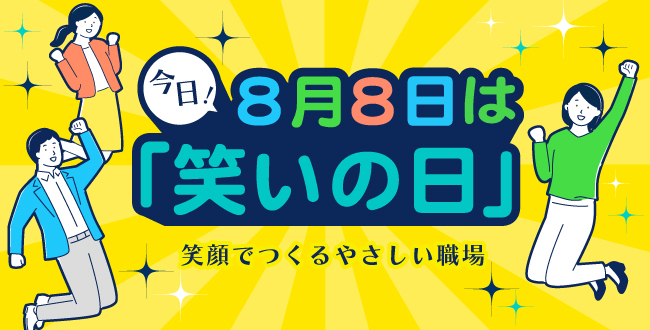


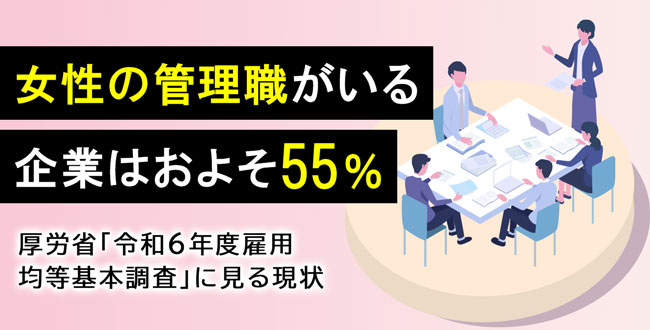




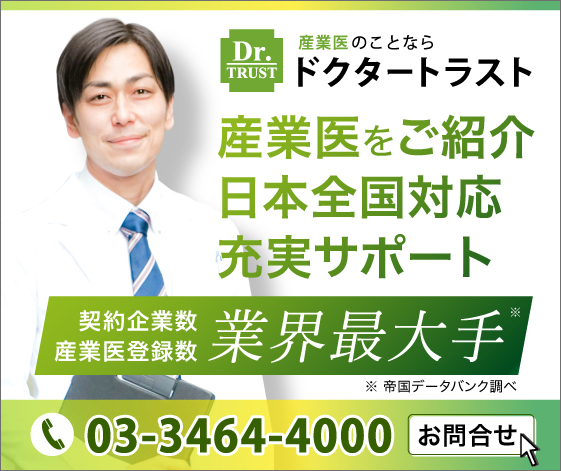


唐澤さん公益通報サムネ.jpg)