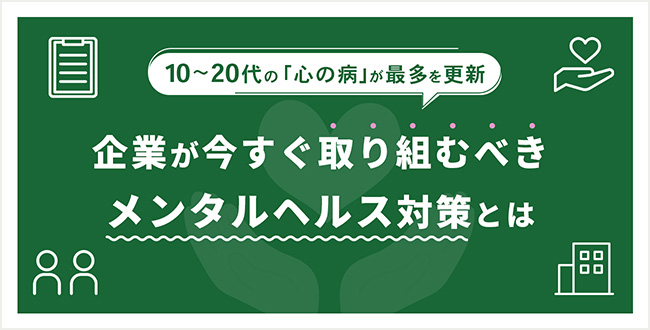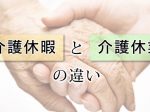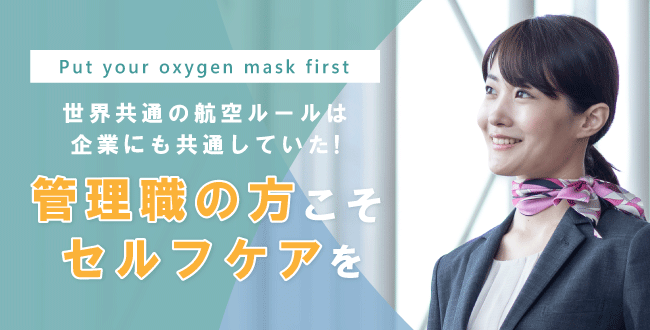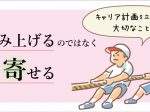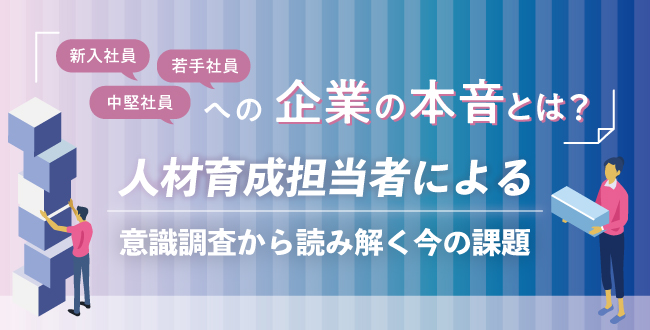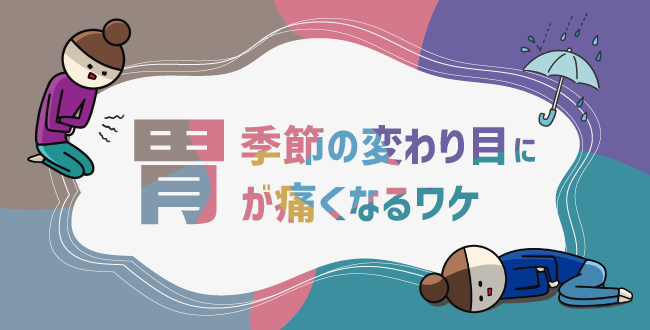- Home
- ワークライフバランス, 人材育成, 健康経営
- 静かなる変化~2025年「静かな退職」の実態と企業の視点~
静かなる変化~2025年「静かな退職」の実態と企業の視点~
- 2025/7/28
- ワークライフバランス, 人材育成, 健康経営
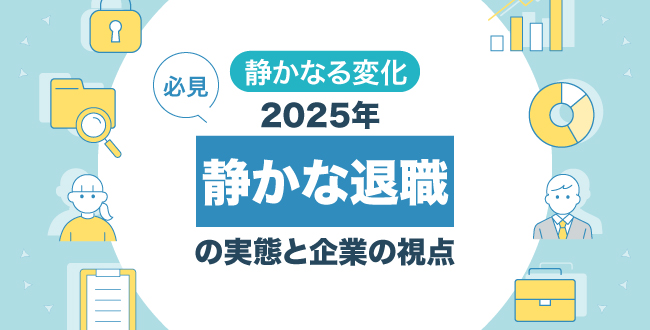
株式会社マイナビが2025年に発表した正社員の「静かな退職」に関する調査により、正社員の働き方に重要な変化が生じている実態が明らかになりました。
4割を超える人々が、従来の積極的な貢献や昇進意欲とは異なる「静かな退職」という働き方を選択しているという結果は、注目に値します。
特に、20代の若い世代が一番多く、ほぼ半数の46.7%がそう感じているそうです。
従来の「バリバリ働いて出世!」という考え方が、新しい世代にはあまり響いてないのかもしれません。
「静かな退職」のリアルと、若い世代の本音
「静かな退職」とは、表面上は会社に在籍しながらも、仕事への関与や貢献意欲を必要最低限に留める働き方を指します。
積極的に転職活動を行うわけではないものの、自身の職務範囲を超える業務を避けたり、改善提案や積極的な活動への参加を控えたりするなどの行動が見られます。
調査によれば、約6割の人が「静かな退職」によって何らかの肯定的な変化があったと回答しており、その内訳としては自分の時間ができたり、気持ちが楽になったりと精神的な安定などが挙げられました。
さらに、7割以上が今後も「静かな退職」を継続したいと回答していることから、これは一時的な現象ではなく、彼らにとっては自分に合った働き方として選んでいるのかもしれません。
それでは、なぜ彼らは「静かな退職」を選択するのでしょうか。
調査を見てみると、その背景には大きく分けて4つの理由がありました。
・仕事内容や職場環境のミスマッチ
・給与などを含めた評価に対する不満
・金銭的な損得やコストパフォーマンスを重視している
・もともとの価値観として変化や上昇を求めていない
日々の業務に意義を見出せない、あるいは職場の人間関係や企業文化に馴染めないといったミスマッチ感が、「静かな退職」という選択を促す原因となっています。
また、自身の貢献度に見合わない報酬や、公正な評価が得られないと感じることも、仕事への意欲低下につながり、「必要最低限の働き方」という選択肢を生み出していると思われます。
会社の人事担当者目線での「静かな退職」への賛成と反対
この「静かな退職」という動きに対して、会社の人事担当者はどう思っているのでしょうか?
調査では、企業の中途採用担当者の約4割がこの現象に対し理解を示す姿勢を示しています。
その理由として、「個々の従業員が持つ働き方への価値観は多様である」「キャリアアップのみが働き方の目的ではない」といった意見が挙げられ、多様な働き方を容認する考え方が一部に浸透していることが伺えます。
特に、労働市場の流動性が高まる現代において、全ての従業員が昇進を志向するわけではないという現実を踏まえ、それぞれの価値観に応じた働き方を許容することも、人材確保の新たな戦略となり得るという認識があるのかもしれません。
一方で、「静かな退職」に否定的な意見も存在します。
反対派の担当者は、周囲の従業員への影響や、組織全体の生産性低下、そして何よりも会社への貢献意欲の低さを懸念しています。
たしかに、チームで仕事をしている場合、「静かな退職」を選択している従業員がいると、他の従業員のモチベーション低下や業務負担の増加につながる可能性も否定できません。
また、企業としては、従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮し、組織全体の目標達成に貢献することを期待しているため、貢献意欲の低い従業員の存在は、組織運営の上で課題となる可能性も考えられます。
この賛否両論の背景には、企業が従業員に求める役割と、従業員個人の働き方に対する価値観の間に存在するギャップが示唆されていると言えるでしょう。
企業としては、積極的に業務に取り組む人材を重視する傾向がありますが、一方で、若い世代を中心に仕事と私生活の調和や個人の充実を重視する方が増加しており、その間で新たにどうバランスを取っていくかが、これからの会社の課題なのかもしれません。
会社と私たちの新しい関係
2025年の調査結果は、「静かな退職」が単なる個人の働き方の選択に留まらず、企業と個人の関係性そのものに変化を促す可能性示しています。
企業は、従来の「積極的に貢献する従業員」という固定的なモデルだけでなく、多様な働き方を許容し、それぞれの社員の力を最大限に引き出せるような、柔軟な組織を作る必要がありそうです。
そのためには、まず「静かな退職」を選択する従業員の背景にある不満などを深く理解することが重要です。
彼らが仕事や職場環境に何を求めているのか、どのような処遇であれば意欲を維持できるのかを探ることで、人事制度や評価制度を見直すきっかけとなるかもしれません。
また、「静かな退職」は、企業にとって必ずしも負の側面ばかりではありません。
離職率の抑制や、経験豊富な人材の維持といった利点も考えられます。
「静かな退職」を選ぶ従業員を単に「意欲の低い人材」と見るのではなく、その能力や経験を活かして組織全体のパフォーマンス向上につなげる、新たなマネジメント戦略の検討が求められます。
「静かな退職」が教えてくれること
結局のところ、「静かな退職」は企業と従業員双方にとって、これまでの働き方やキャリア観を再考する機会を提供していると言えるかもしれません。
企業は、多様な価値観を持つ人材が共存できる、より柔軟で包括的な組織文化を構築していくことが求められます。
そして、個人は、自身のキャリアや人生設計において、何を重視するのかを改めて考え、主体的な働き方を選択していくことが重要となるでしょう。
2025年の調査結果は、そのような新たな時代の到来を告げる静かなメッセージとして受け止めるべきなのかもしれません。
参考文献
・マイナビキャリアリサーチLab「正社員の静かな退職に関する調査2025年」