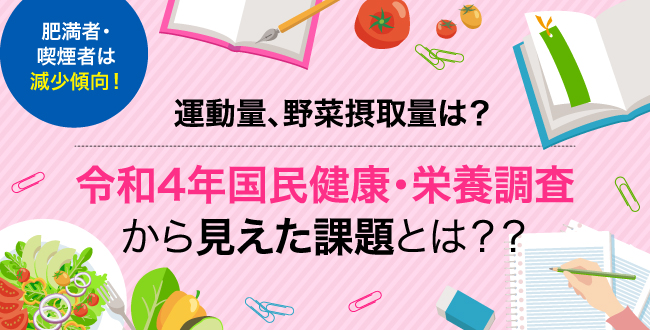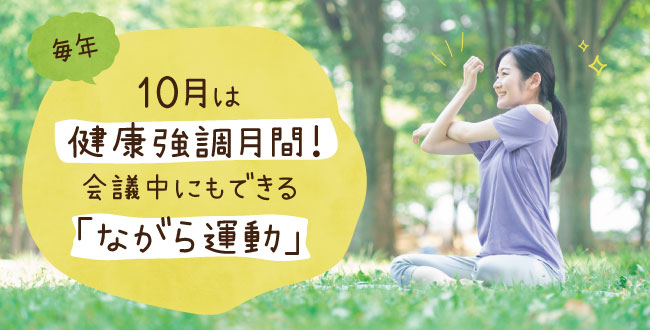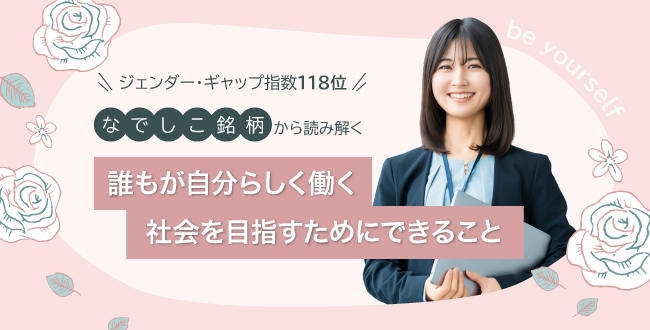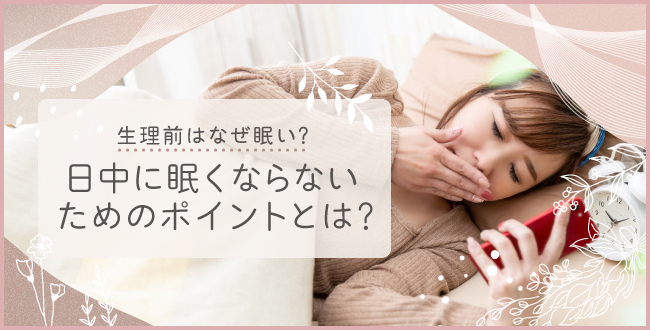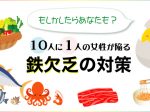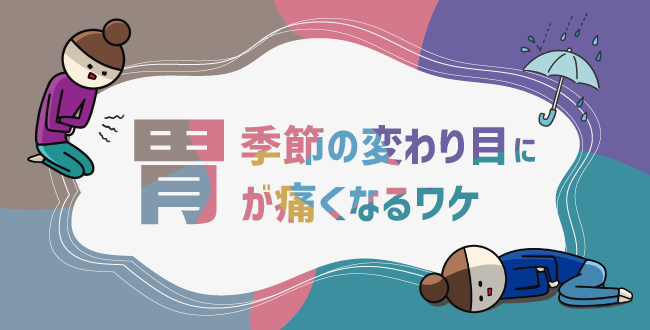不妊治療と仕事の両立~いま、職場に求められる配慮とは~
- 2025/7/25
- WOMAN

晩婚化やライフスタイルの多様化により、不妊治療を受ける人が年々増加しています。
しかし治療と仕事の両立に悩み、離職や治療中断を余儀なくされるケースも少なくありません。
企業や社会に求められる支援のあり方とは何か、考えてみましょう。
不妊の定義
不妊とは、妊娠を希望して避妊をせず一定期間(通常1年以上)性交をしても妊娠に至らない状態を指します。
不妊症の定義は医学的に明確であり、年齢とともにその割合は上昇します。
20代後半で約9%、30代後半では約30%、40代では60%以上が不妊に直面しているとされています。
日本では、不妊を心配したことのある夫婦は約4割、実際に検査や治療を受けた経験のある夫婦は約23%に上ります(厚生労働省調査)。
つまり、4~5組に1組の夫婦が実際に治療を経験しており、不妊治療はもはや一部の人だけの問題ではないといえます。
不妊治療
不妊治療にはタイミング法、人工授精(AIH)、体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)などがあり、患者の状態や年齢、原因によって治療方針が異なります。
一般不妊治療だけでも半年から1年、それ以上に及ぶことも珍しくありません。
加えて、治療は一度で完結するものではなく、何度も通院が必要で、身体的・精神的・経済的に大きな負担を伴います。
治療と仕事の両立は困難が多い
厚生労働省の調査によると、不妊治療と仕事の両立ができず、約16%の人が離職を選択しています。
通院が業務と重なることでのスケジュール調整の困難さや、体調不良・精神的ストレスが原因となり、治療の中断や離職に追い込まれることもあります。
「急な通院指示があるのに、会議や現場対応があり抜けられない」「通院先の待ち時間が長く、職場に迷惑をかけてしまう」といった悩みの声は後を絶ちません。
職場での理解不足が、この問題をさらに深刻にしています。
企業に求められる支援
不妊治療と仕事の両立を可能にするために、企業は以下のような取り組みを検討する必要があります。
柔軟な勤務制度の導入:
フレックスタイム制、時間単位の有給休暇、テレワーク制度など
不妊治療休暇の創設:
治療のための特別休暇制度を設け、安心して通院できる環境づくり
相談窓口の設置:
プライバシーに配慮した社内相談体制や、外部カウンセラーとの連携
啓発と理解促進:
上司や同僚への研修を通じて、職場全体の理解を深める
これらの施策は、従業員の安心感を高めるだけでなく、離職の防止や企業の人材確保にもつながります。
実際に、取り組みを実施している企業では、従業員満足度や定着率の向上が報告されています。
先進企業の取り組み
一部の企業(大手食料品メーカー:オタフクソース株式会社)では、実際に以下のような制度を導入し、働きやすい環境を整えています。
1.月1回のケア休暇(1時間単位)
2.短時間勤務制度(6~7時間)
3.最長1年6か月の休職制度
4.ノーリーズン休暇(連続5日間)
5.不妊治療退職者の再雇用制度
6.在宅勤務・フレックスタイム
制度の整備だけでなく、上司や同僚の理解を促す社内研修や情報共有の取り組みも重要です。
こうした見えにくい支援こそが、当事者の働きやすさを支える鍵となります。
さいごに
不妊治療は外見では分かりにくく、当事者自身が「言いづらい」「理解されにくい」と感じやすい問題です。
だからこそ、職場の理解と支援が不可欠と言えるでしょう。
厚生労働省も企業向けにリーフレットやガイドラインを発行し、不妊治療と仕事の両立支援を推進しています。
制度整備と意識改革の両輪で取り組むことが、従業員一人ひとりのライフプランを支え、企業と社会の持続的な発展につなげていければ誰もが安心して治療と仕事を両立できる社会へとなるでしょう。
<参考>
厚生労働省「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」
厚生労働省「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」
厚生労働省「仕事と不妊治療の両立支援のために」
厚生労働省「不妊治療連絡カード」