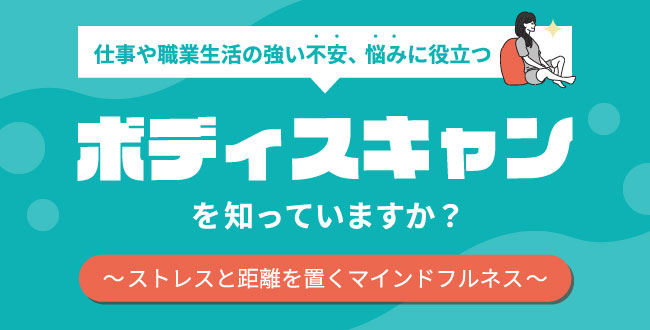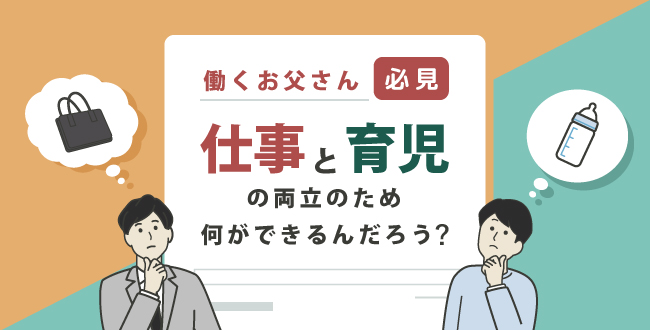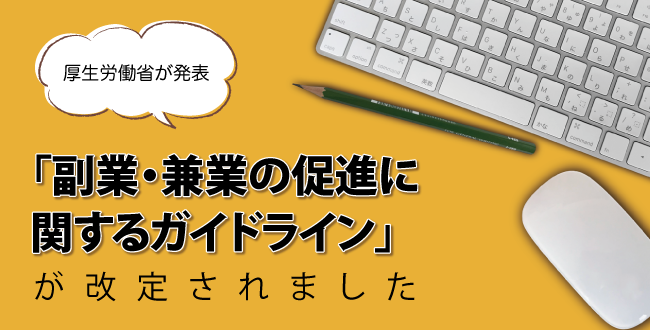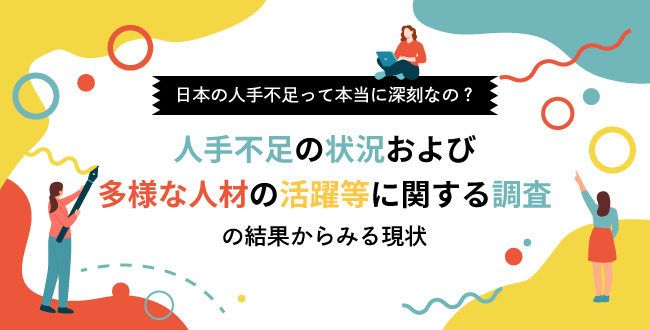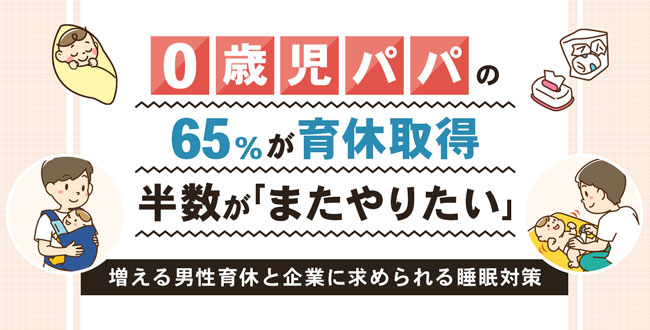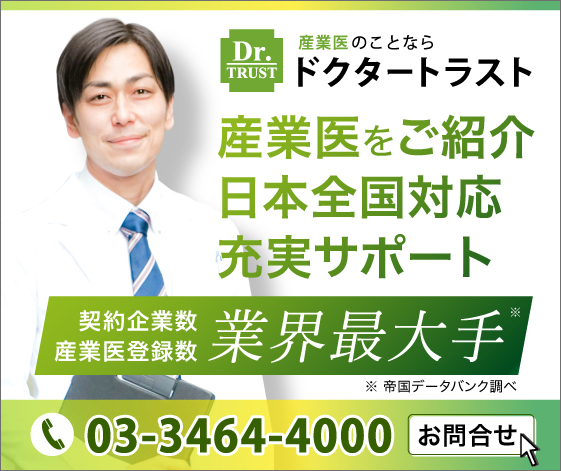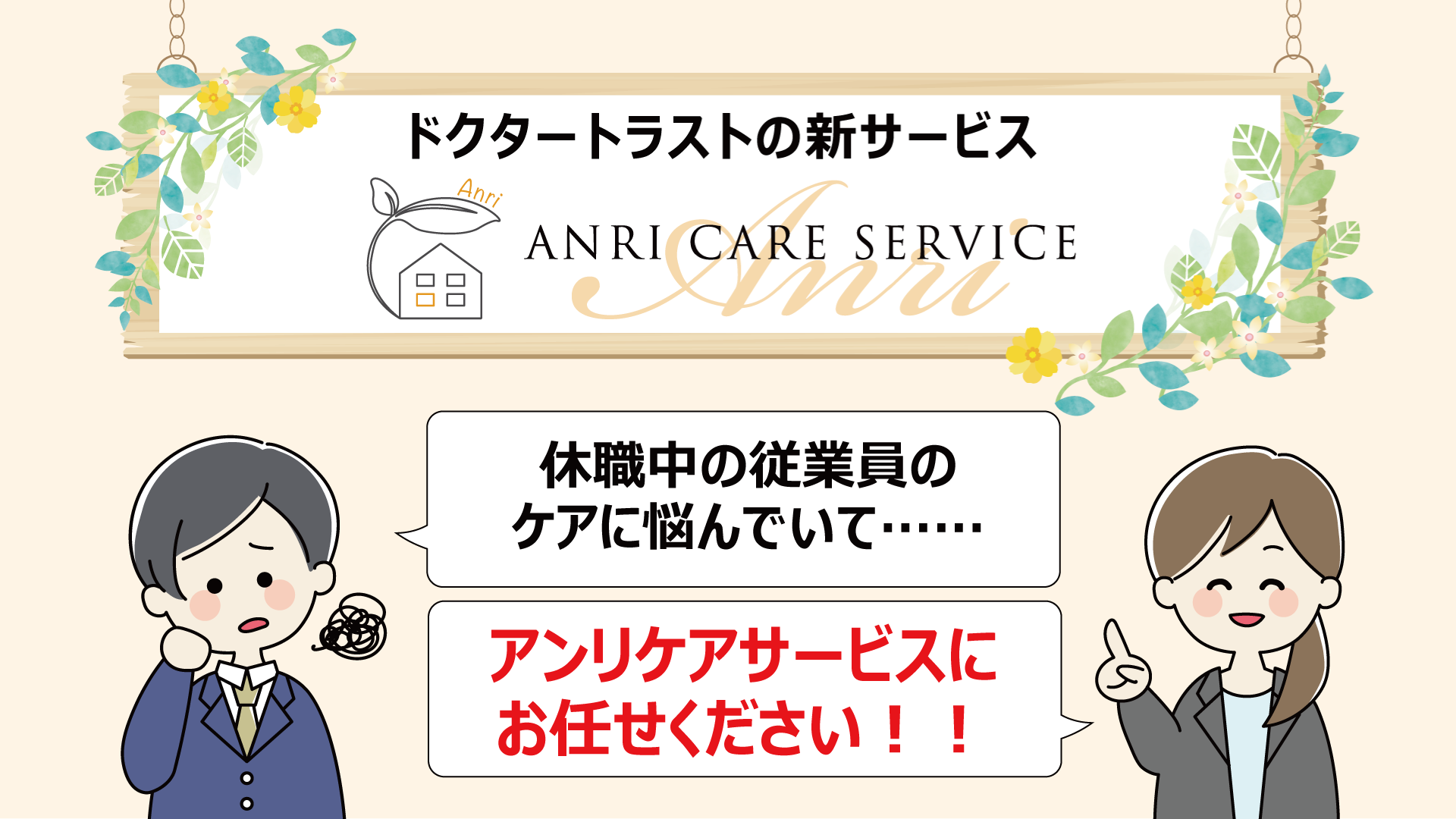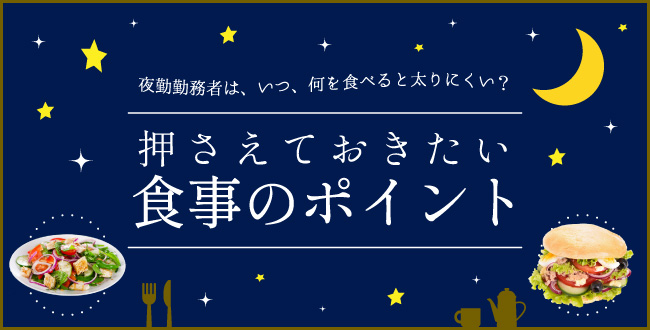- Home
- ダイバーシティ, 外部相談窓口アンリ, 育児
- 男性の「産後うつ」支援に巻き起こる批判~公認心理師が回答します~
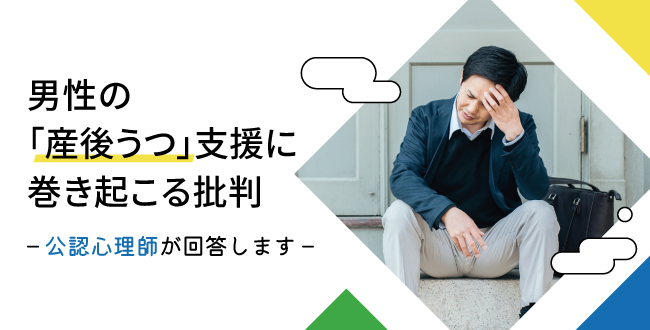
2025年1月19日、国立研究開発法人国立成育医療研究センターが「男性の産後うつ」への自治体向け支援マニュアルを作成しました。
男性の育休取得率が徐々に上昇する中、育児や仕事との両立に不安を抱え、産後うつに陥る男性が増えていることが背景にあります。
日本小児科学会のアンケートによれば、男性の産後うつの有病率は8.5%。しかし「産後」という言葉を男性に使うことへの違和感や、女性の支援が不十分な現状に対する反発もあり、社会全体としての理解はまだ十分とはいえません。
今回は、「男性の産後うつ」について、株式会社ドクタートラストで外部相談窓口相談員を務めていた経験のある、公認心理師の福田築さんにお話を伺いました。
産後うつとは何か?
産後うつとは、産後に起こる抑うつ状態などのことを指します。
抑うつ状態が2週間以内に治まる場合は「マタニティブルース」と呼ばれ、それ以上続く、または症状が重い場合には「産後うつ」と診断されます。
福田さんによると、「諸説ありますが、うつ病と産後うつでは症状自体に大きな違いはなく、発症時期によって名称が分けられていることが多い」とのことです。
産後にうつ病が発症することは多くの国で認められている。産後のうつ病が他のうつ病からかけ離れた疾患であるものではない。うつ病は何らかのストレス状況で発症し、女性の場合にうつ病が発症しやすいストレス状況の1つが妊娠・分娩・育児の時期であるだけのことである。
出所元:北村俊則編集『事例で読み解く周産期メンタルヘルスケアの理論』(医学書院、2007年12月)
ホルモンの変化が女性のメンタルヘルスに影響を与えることは確かですが、診断では「抑うつ状態等の程度」が主な基準となっています。
つまり、男性であっても産後に抑うつ症状があれば「産後うつ」と分類されることがあります。
男性に「産後うつ」という言葉を使うことへの違和感
福田さんによれば、「男性の産後うつ」が注目される前から、子どもが生まれた直後の父親たちからメンタルヘルス不調について相談を受けることはあったそうです。
つまり、男性もこの時期に心が不安定になりやすいのは以前から見られていたことであり、最近になってようやく「男性の産後うつ」として認知されてきたといえます。
ただ、「産後は女性にしかないのでは?」という違和感や批判があるのも事実です。
福田さんは「今は“産後うつ”という言葉が独り歩きしている」と語ります。
もちろん男性に産後はありませんが、出産後の生活環境の変化によってうつ病を発症しやすくなるのは男女問わず同程度とされています。
産後うつの原因は明らかになっていない点も多く、現時点では症状に当てはめて「産後うつ」に分類しているのが実状です。
なぜ男性も産後うつになるのか?
男性が育児に関わる機会が増えている一方で、母親とくらべて、父親の準備を支援する制度や環境が整っているとは言い難い状況です。
出産や育児に対する情報が少ないままスタートしてしまい、心の準備が整わずに不安や責任感からうつ状態に陥るケースがあります。
また、「母親は命がけで出産しているのだから、父親はそれを支えなくてはいけない」という一般的なイメージの中で、父親自身のサポートは後回しにされがちです。
特に、「しっかりしなければ」と感じやすいタイプの人ほど、育児と仕事の板挟みから精神的に追い込まれてしまうのではないかと福田さんは話します。
育休取得推進の裏で見落とされる課題
政府は「こども未来戦略」で、2025年までに男性の育休取得率を50%(公務員85%)、2030年には85%(公務員85%)にする目標を掲げています。
しかし、こうした政府の目標に企業の制度整備はまだ追いついていないのが現状です。
制度整備の遅れで十分な育休を取れないことによって起こる育児と仕事の板挟みが男性の産後うつ増加の一因にあります。
「男性の産後うつ」支援への批判にどう向き合うか
「女性への支援が不十分な今、なぜ男性を支援するのか」という批判の声について福田さんはこう語ります。
福田さん
「どちらかを優先するのではなく、並行して支援しなくてはならないもの。『男性の家庭進出』と『女性の社会進出』はセットでしか達成できません」
男性が安心して育児に関われる環境が整えば、結果として女性が職場復帰しやすくなります。
つまり、男女どちらかだけを支援するのではなく、両輪で支えていくことが社会全体にとっても必要です。
家族や企業にできる支援とは
福田さんは、産後うつには以下の5つの要因が関係していると説明します。
• 出来事(ライフイベント)
• 周囲のサポート
• コーピングスキル(ストレス対処能力)
• 考え方のパターン
• 自身の養育体験
たとえば、業務量の多さがストレス要因となっている場合には、企業側での調整が必要です。
そのほかにも、職場のコミュニケーションを増やすことや気軽に相談できる雰囲気づくりも求められます。
相談しやすい環境づくりとして外部相談窓口の活用も有効でしょう。
一方、考え方やストレス対処力については、医療機関のカウンセリングなど専門的な支援が必要になることもあります。
福田さん
「今の会社で良いと感じるのは、職場に子どもを連れて来られる制度や、子どもの病気で自由に休める制度。親になってそのありがたみがよくわかります」
男性も女性も、育児に悩んでいい
いくら子供をかわいいと感じ、子育ては大事と思っていても、社会との交流が遮断され、ほかの人の手も期待できない孤独な子育ては、おとなの心理安定を阻害するのです。これは母親・女性であっても、父親・男性であっても同じです。
柏木恵子『父親になる、父親をする』(岩波書店、2011年6月8日)
子育ては一人ではできません。
限界を感じたとき、周囲の助けを求められる環境づくりと、親になる準備を支える制度がこれからの社会には求められています。
また、国や行政からの支援を通して、父親になった男性が「父親をする」ための知識を得ていくことが産後うつに苦しむ男性の減少につながるでしょう。
そして、それこそが女性の活躍する社会の実現には必要なのです。
「育児に100点はない」父親・母親へのメッセージ
福田さんが子育てをする父親・母親に伝えたいのは「100点を目指さないこと」だそうです。
SNSなどで情報があふれる現代では、正解がわからないまま「自分はできていない」と感じてしまう人が多くなっています。
福田さん
「育児に100点はありませんし、正解もありません。極端かもしれませんが『生きていればOK』という気持ちでいることも育児には必要なのかもしれませんね」
<参考>
・ 国立研究開発法人国立成育医療研究センター「父親支援マニュアル」
・ 北村俊則編集『事例で読み解く周産期メンタルヘルスケアの理論』(医学書院、2007年12月)
・ 柏木恵子『父親になる、父親をする』(岩波書店、2011年6月8日)
・ 日本小児科学会「男性の産後うつと育児休業に関するアンケート調査」(『日本小児科学会雑誌』127巻1号、2023年)
・ 厚生労働省「こども未来戦略について(雇用環境・均等局関係)」