裁判例から見るメンタルヘルスに関する法律的な解釈①
- 2018/10/23
- 労働安全衛生法

働いている私たちは、知らず知らずのうちに、さまざまな法律によって守られたり、縛られたり…。
使用者、労働者ともにそれは同様です。
日本の法律は労働者の権利を守るためのものが多い印象ですが、一つの事案に対して適用される法律は複数となるケースが多いため、結果的に使用者の味方にも労働者の味方にもなります。
また、働いていくうえでは、大なり小なりストレスを受けています。
もちろん個人の耐性にもよりますが、ハラスメントに限らず人間関係や、公私を問わず大きなストレスを受ける出来事など、さまざまな要因でメンタル不全は起こります。
労働者がメンタル不全となった場合に、調停や示談交渉などでは解決せず、訴訟となったとき、労働者や企業が負うリスクとはどのようなものがあるか具体的にご存知でしょうか?
法律的な観点から、メンタル不全に対する解釈を一部判例を確認しながら考えていきたいと思います。
今回はまず、前提条件としての労災認定と民事訴訟(損害賠償請求)について確認しましょう。
業務上外の違いによる対応とリスク
まず、前提としてメンタル不全となった要因が業務上によるものか、業務外によるものかで対応が大きく変わります。
(1) 業務外の精神疾患の場合
「私病」として扱われるため、通常であれば就業規則の定めに則り以下の措置が取られるケースが一般的です。
- 休業(傷病手当金の支給)
- 休職、復職、解雇(労働契約法16条)、自然退職
(2)業務上の精神疾患の場合
- 労災(労災給付、解雇制限(労働基準法19条1項))
- 損害賠償請求(安全配慮義務違反(労働契約法5条、民法415条))
- 不法行為(民法715条、会社法350条)
- 取締役の責任(会社法429条、(847条))
(2)はリスクとして法的責任を問われる可能性のあるものを羅列したものです。
このすべて、または一部を問われるかは、事案によって異なり、断言することはできません。
ただ、一般的にいわれている通り、労災が認定されると、多くの場合は使用者の過失も認められ、損害賠償責任を負うこととなります。
業務起因性(相当因果関係)の判断
労災の認定は「ストレス脆弱性理論」をもとに考慮されます。
「ストレス脆弱性理論」とは、次の2つをもとに、「業務による心理的負荷が、社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重であるといえる場合に、業務起因性(相当因果関係)を肯定する」という考え方です。
① ストレス(業務上または業務以外の心理的負荷)
② 個体側の反応性、脆弱性(当該労働者の基礎疾患等の身体的要因や、(うつ病等に)親和的な性格等)を総合的に考慮
その上で、厚生労働省平成23年12月26日基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」では、次の3つを認定要件としています。
① 精神障害が労災の対象疾病であること
② 発症前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により発病したとは認められないこと
行政判断と司法判断
労災認定は行政において前述の基準により判断され認定されます。
改めてご説明の必要もないかと思いますが、労災保険として徴収され積み立てられているものが、労災給付金として支払われる制度です。
一方、労災給付だけでは不服として、会社(使用者やハラスメント事案などの場合には加害者となる労働者個人)を相手取り、民事訴訟により請求するものが損害賠償請求です。
こちらは裁判で判決により確定するものなので、司法での判断となります。
司法判断でも、認定基準は労災認定基準に準拠したものになりますが、必ずしも同一の判断とはならず、労災認定がなされなかったケースでも司法判断として改めて労災認定がされ、そのうえで損害賠償請求が認められるものが多くあります。
裁判所は司法判断として、行政よりも広く業務起因性を認める傾向があるといえるでしょう。
「国・大田労基署長(羽田交通)事件 東京地裁平成27年5月28日判決」の判決文のなかで、「(行政の)認定基準は絶対的なものではないから、厳密にいえば認定基準の要件を完全に充足されているとはいえない場合であっても事案の内容や認定基準の基礎となっている医学的知見に照らし、業務起因性を認めるのが相当なこともあるというべき」とはっきりと述べています。
しかし、逆に、労災認定はされていても業務起因性(相当因果関係)が認められないとして損害賠償請求を否定されるケースも比較すれば少ないながら過去に判決としては存在します。
<例>
- 日本政策金融公庫(うつ病・自殺)事件 大阪高裁平成26年7月17日判決
- ヤマダ電機事件 前橋地裁高崎支部平成28年5月19日判決
判断基準は定められていますが、一律に判定するのではなく、事案ごとの背景や使用者や労働者の対応や経過など、全体を通とおしての総合的な判断を行なうことで、裁判所の判断は行政の判断よりも広く業務起因性(相当因果関係)を認める傾向があるといえるでしょう。
裁判所の業務起因性判断でよく問題になる点
業務起因性の司法判断で非常によく問題にあげられる点が以下の3点です。
1. 長時間労働
2. ハラスメント(パワハラ)
3. 職場の支援・協力体制
たとえば、長時間労働については次のように労災認定基準に定めがあります。
基本的には、発症直前の6カ月間を判定期間として、
- 発症直前1カ月におおむね180時間を超えるような、またはこれに満たない期間にこれと同程度の(たとえば3週間におおむね120時間以上)時間外労働を行なった場合 ※手待ち時間が極端に多い場合等、労働密度が特に低い場合は除く
- 発症直前の連続した2カ月間に、1月あたり約120時間以上の時間外労働
- 発症直前の連続した3カ月間に、1月あたり約100時間以上の時間外労働
- 一定の心理的負荷のある出来事の前、後に恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合 など ※ここでいう出来事には異動等も含まれる
しかし、ここでも裁判所では、行政の労災認定基準に必ずしもとらわれず、総合評価する立場で判断をするため、時間外労働が月100時間程度に至らなければ大丈夫と判断するべきではありません。
また、裁判所は、労働時間の他に業務の質的・量的か銃声、サポート体制の有無、恒常的長時間労働の前後の出来事などを考慮して業務起因性を判断します。
そのため、月100時間を下回る時間外労働でも業務起因性を認めているケースは多くあります。
<例>
- 国・中央労基署長(旧旭硝子ビルウォール)事件 東京地裁平成27年3月23日判決
- 国・大田労基署長(羽田交通)事件 東京地裁平成27年5月28日判決
※パワハラが認められる場合には、さらに合わせ技で業務起因性を判断し認定します。
この裁判所の判断の考え方は損害賠償請求事件についても同様です。
判例から見える対策
長時間労働については、労働時間を削減するという明確な数値目標はあるものの、人員不足やマンパワーの問題など、即解決することのできないケースが多いようです。
しかし、だからといってそのままにして良いわけもなく、その状態が恒常化することによって心理的負荷が増大し、メンタル不全(精神障害)を発症するリスクは格段に上がり、これまで見てきたようにその場合の裁判所の判断は使用者にとっては手痛い判決となる可能性が高くなります。
使用者には労働者への安全配慮義務があるため、心理的負荷の高い職場環境や業務、長時間労働などを看過することはリスク以外のなにものでもありません。
数々の判例を見ていくと、職場の支援・協力等(問題への対処等を含む)の欠如が著しい場合は心理的負荷の総合評価を強める要素として考慮する傾向があるため、訴訟リスクを削減するためにも、まずは業務のやり方の見直し改善、応援体制の確立、責任の分担等を検討し、支援・協力体制を構築することが対策の第一歩となります。
職場での支援・協力体制の構築は訴訟リスクの低減や万が一損害賠償請求をなされた時の備えにもなりますが、ラインケアとして労働者のメンタルヘルス対策としての効果も見込めるため、メンタル不全対策としても検討してみることをお勧めします。

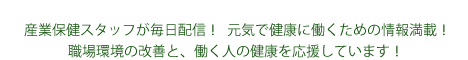

















唐澤さん公益通報サムネ.jpg)

