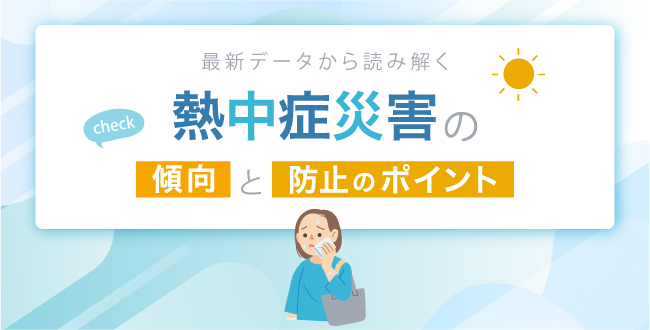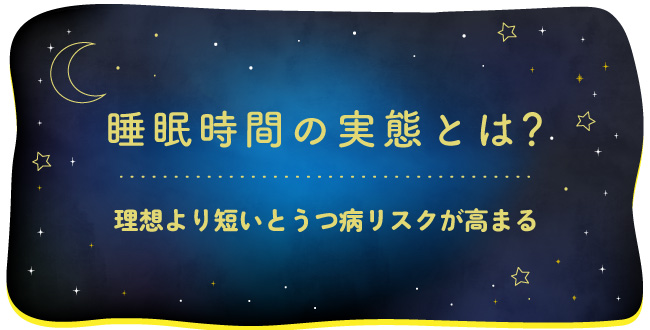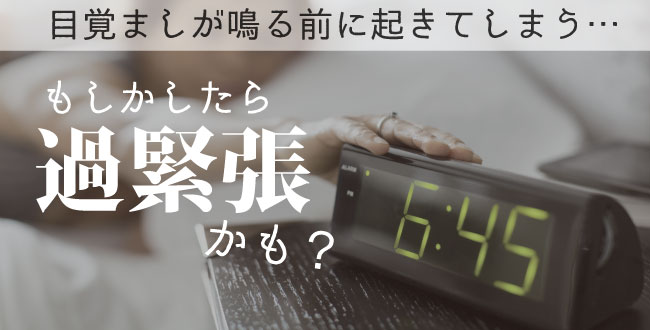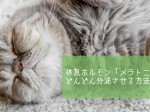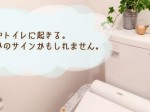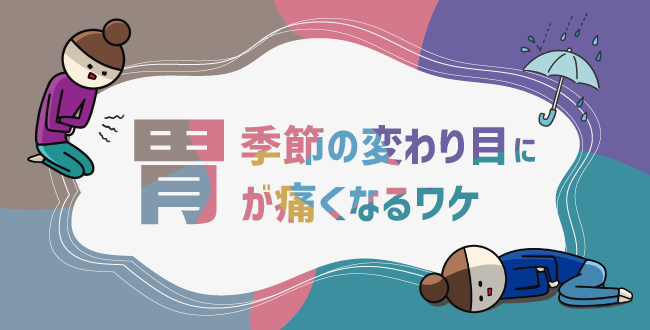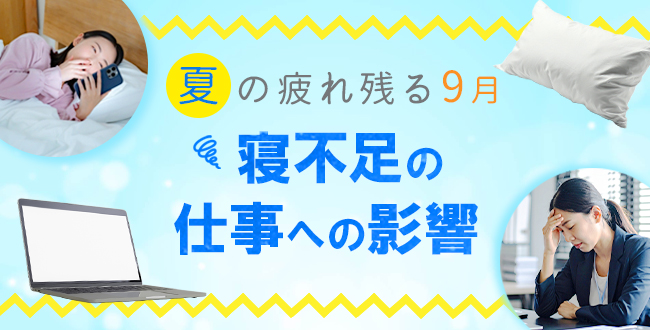
働き盛りのビジネスパーソンにとって、「寝不足」は珍しいものではありません。
夜遅くまで続く業務、スマートフォンでの情報チェック、家庭や育児との両立など、睡眠を削る要因は数多く存在します。
さらに夏の疲れが残る9月は、気温や生活リズムの変化で眠りにくくなる時期でもあります。
ここでいう「寝不足」とは、単に睡眠時間が短いことだけを意味しません。
成人の適正な睡眠時間はおおよそ6~8時間とされていますが(参考※1)、必要な時間は人によって異なります。
日中に強い眠気を感じたり、仕事や生活に支障をきたしたりしている場合は、睡眠時間の不足や睡眠の質の低下が原因となっている可能性があります。
それにもかかわらず、「少しくらい眠らなくても大丈夫」「眠気が残っているけど放っておこう」と考えるのは危険です。
研究データは、睡眠不足が個人の判断力やメンタルなどに深刻な影響を与えるだけでなく、チームや組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼすことを示しています。
本記事では、その実態をデータとともにご紹介します。
睡眠不足で脳の働きはどう変わる?
睡眠不足は、意思決定や思考、集中力、注意力に関わる脳の前頭前野の能力を低下させることがわかっています。(参考※2)
ジューン・C・ローらの研究では、夜間睡眠を1日当たり約5.8時間に制限すると、制限せずに約8.6時間眠らせた場合に比べて眠気が増し、注意力が低下することを示しています。(参考※3)
ビジネスシーンでは、集中力の低下やわずかな判断のずれが大きな影響を及ぼすこともあり、リスク管理の面からも無視できない問題です。
メンタル不調との密接な関係
睡眠とメンタルヘルスの関係についても、多くの研究が行われています。
睡眠時間の短さと、うつ病との関連性を示す研究(参考※4)、また睡眠休養感(朝目覚めたときに感じる休まった感覚)が低い人ほど、抑うつの度合いが強いこと(参考※5)が報告されています。
さらに、寝不足はストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を増やし、心身のバランスを崩す原因となります。(参考※6、7)
職場での休職や離職の背景には、こうした「睡眠の問題」が隠れているケースも少なくありません。
チーム全体への悪影響
睡眠の問題は個人だけでなく、チーム内での対人関係やパフォーマンスにも影響を与える可能性があります。
ウィリアム・DS・キルゴアらの研究では、睡眠不足は共感力や対人スキルの低下と関連していることが示されています。(参考※8)
さらに、E. グリアらの研究によれば、睡眠不足がチーム全体のパフォーマンスや結束力の低下につながることを示しています。(参考※9)
特にチームワークが大切な職場では、メンバー間の協力やコミュニケーションの課題が起こることで、組織全体の働きや成果にも悪影響が及ぶ恐れがあります。
まとめ
寝不足は「個人の健康課題」にとどまらず、「組織全体のリスク」として捉える必要があります。
集中力や注意力の低下、メンタル不調、チームへの悪影響など、いずれも企業にとって深刻な課題です。
その改善策としては、まず社員一人ひとりができるセルフケアの取り組みが大切です。
具体的には、就寝前のスマートフォン利用を控えて脳を休める、夕方以降のカフェイン摂取を避ける、休日も含めて就寝・起床時間を揃えるといった生活習慣の見直しが効果的です。
さらに、軽い運動や入浴で体温リズムを整えることも睡眠の質を高めます。
企業側では、残業時間の削減やフレックスタイム制度の導入に加え、夜遅い時間帯の業務連絡を控える、昼休みに仮眠が取れる休養スペースを設けるなど、多角的な取り組みが社員の睡眠改善につながります。
さらに、社員の理解を深め、実際の行動変容につなげるために有効なのが、睡眠に関する研修やワークショップです。
睡眠の重要性や実践的な改善法を学ぶことで、個人だけでなく組織全体として「睡眠改善の文化」を根付かせることができます。
ドクタートラストでは睡眠研修を提供しております。
職場での睡眠改善に取り組みたいとお考えの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
【ドクタートラスト主催のセミナーはこちら】
<参考>
※1:厚生労働省 健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」
※2:Thomas M et al.「Neural basis of alertness and cognitive performance impairments during sleepiness. I. Effects of 24h of sleep deprivation on waking human regional brain activity」J Sleep Res 2000;9:335–352
※3:Lo JC et al. 「Effects of partial and acute total sleep deprivation on performance across cognitive domains, individuals and circadian phase」PLoS One 2012;7:e45987
※4:内山真ほか「一般成人における睡眠時間の 不足とうつ病の関連について」健康日本21(第2次)に即した睡眠指針への改訂に資するための疫学研究 平成25年度 総括・分担研究報告書(厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)) 、pp. 73-85, 2014.
※5:金板義隆ほか「The relationship between depression and sleep disturbances: a Japanese nationwide general population survey」J Clin Psychiatry 67 2006: 196-203.
※6:本村優希ほか「Sleep debt elicits negative emotional reaction through diminished amygdala-anterior cingulate functional connectivity」 PLoS One 2013; 8: e56578
※7:Leproult R et al「Sleep loss results in an elevation of cortisol levels the next evening」Sleep 1997;20,865–870
※8:William D S Killgore et.al.「Sleep deprivation reduces perceived emotional intelligence and constructive thinking skills」Sleep Med 2008 Jul:517-26.
※9:E Greer et al.「O063 Impact of sleep deprivation on distributed team performance and cohesion」Sleep Adv. 2022 Nov 9:A26–A27.6