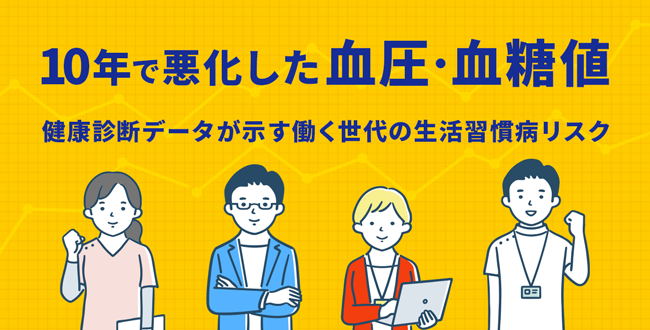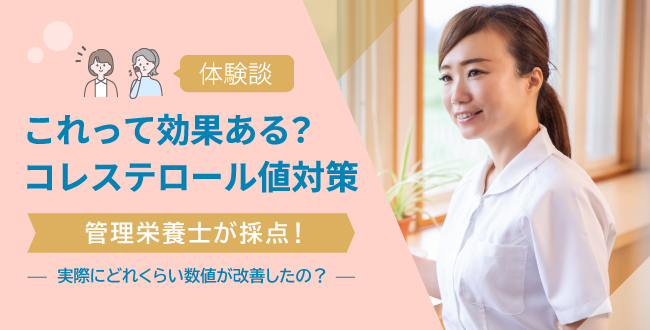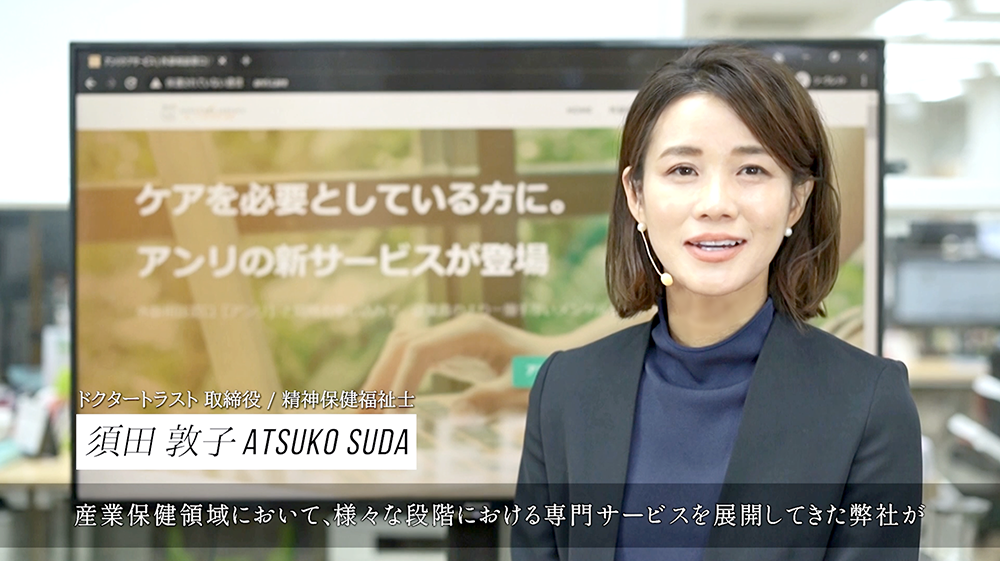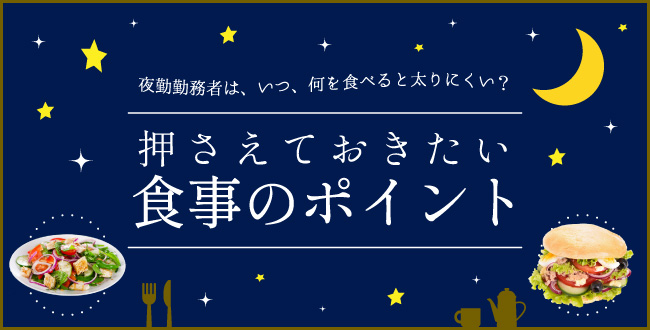定期健診 オプション検査の選び方
- 2014/7/15
- 健康診断

定期健診とオプション検査
会社の定期健診の案内と一緒に、同封されているオプション検査項目のリストを目にしたことはあるだろうか。
定期健診では、労働安全衛生法で「必ず受けなければいけない」と定められている法定項目を含んだ基本健診と、それ以外に個人の判断で項目を選ぶことができるオプション項目とに分けられていることが多く、オプション項目は、金銭面でも自己負担で受ける場合が多い。
しかし、オプション検査は、その項目が多岐に渡る上、一般の人にとっては選び方が解りづらく、「なんとなく必要そうだから」「金額が安いから」「周囲が受けているから」などの理由で選んでいることも多いのが現状である。
一般的な定期健康診断の基本項目には、以下のようなものがある。
≪基本項目≫
1. 医師による問診
2. 身長・体重・腹囲・視力検査 聴力検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・40dB)
3. 胸部X線検査
4. 血圧測定
5. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
6. 貧血検査(赤血球数、血色素量)
7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
9. 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
10. 心電図検査
これらは法律で検査することが決められている項目であるため、受ける側も特別な理由(医師が省略可能と判断した場合など)を除き、項目について増減をすることは不可能である。
逆に、一般的な健診に含まれない検査が、がん検診だ。家族内にがん患者がいる場合や、心配な症状がある場合は、積極的にオプション検査で選ぶと良いだろう。
オプション検査選びに迷ったら
多岐にわたるオプション検査。自分で受診の必要性を判断する方法はないのだろうか。
選ぶ際のポイントとなるのは、「自覚症状、家族歴、年齢、性別」である。
・健診結果や自覚症状から考える方法
過去の定期健診で高血圧や高血糖・高脂血症などを指摘されている場合は、脳・心疾患系の項目を優先して追加した方が良いだろう。
喫煙歴があったり、咳・痰が気になる、家族に肺がん患者がいる場合などは、肺に関するオプション検査を優先して選ぶ。
胃痛や胃もたれの症状があったり、慢性胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍などにかかったことがある人は、胃に関する項目を選ぶようにすると良いだろう。
・年齢や性別などから考える方法
年齢・性別によって死亡率が高いがんが異なるため、よりリスクの高いがん検診を選んで受けると言う方法もある。年齢・性別によるがん死亡率の統計は、最新がん統計のHPに掲載されているので参考にしていただければと思う(http://ganjoho.jp/public/statistics/pub/statistics01.html)。
通常がん検診は50代になってから受ければ良いとされているが、女性が20代など若いうちに罹患することの多い子宮頸がん検診や、家族内で若いうちにがんに罹患した人がいる場合は、早い段階で検査を受けるようにした方が良い。
症状がなければ不要なオプション検査も
オプション検査の中でも、「症状がなければ検査は不要」と言われている検査がある。
その一例が頸動脈エコー検査だ。
頸動脈(首の動脈)を超音波で調べることで、動脈硬化の有無を判断するための検査であるが、偽陽性が多い検査であるため、米国予防医療サービス対策委員会(USPSTF)から「不要※推奨グレードD」と発表されている検査である。
現在何も症状がなく、脳梗塞になったことがなければ、毎年選択する必要はない検査と言える。
わからなければ相談を
過去の健診結果や自覚症状、家族歴などを合わせて考えてみても、どのオプション項目を選べばよいか迷った場合は、企業内の産業医・産業保健師に相談するか、健診機関へ問い合わせてみるとよいだろう。
多くの検診機関は、相談窓口を持っているので、受診項目に関する相談にも対応してもらえるケースが多い。
また、毎年健診機関を変える方も見かけるが、画像検査の結果などは前年度との比較が大切であり、健診の基準値も施設ごとに微妙に異なっているため、出来れば毎年同じ健診機関での受診をお勧めしたい。