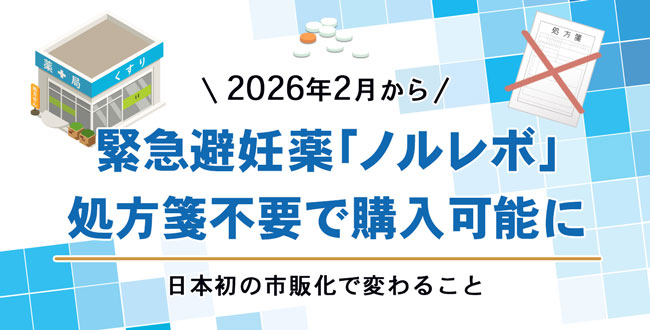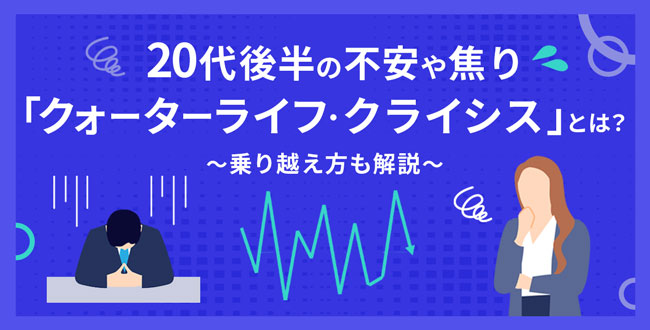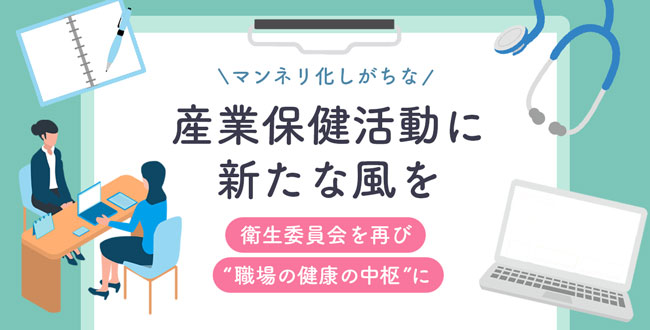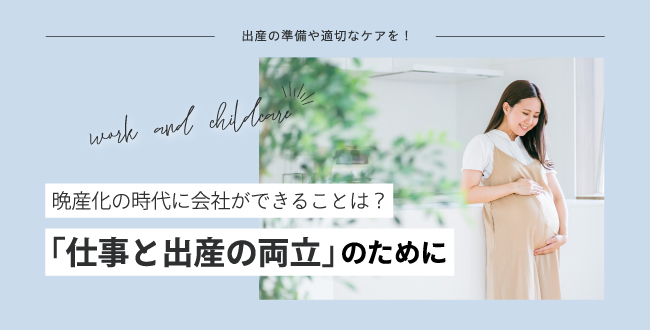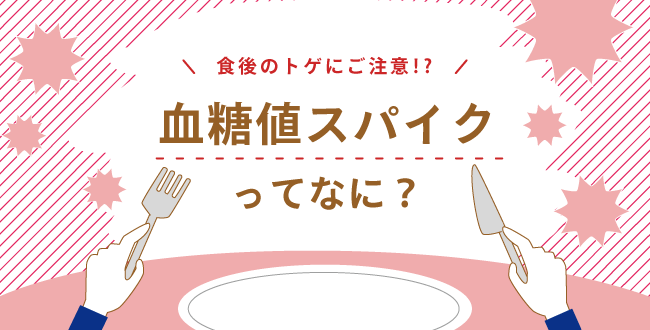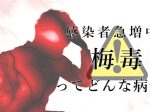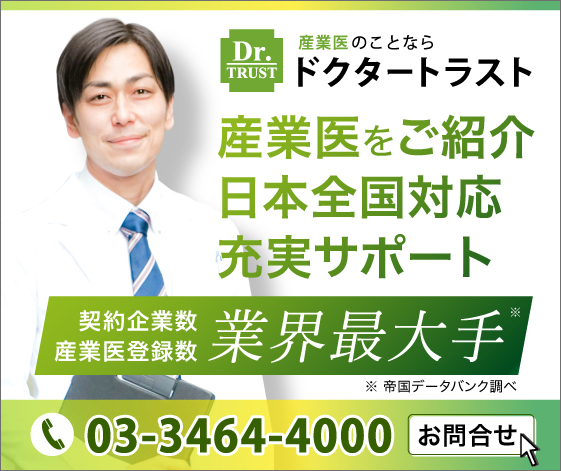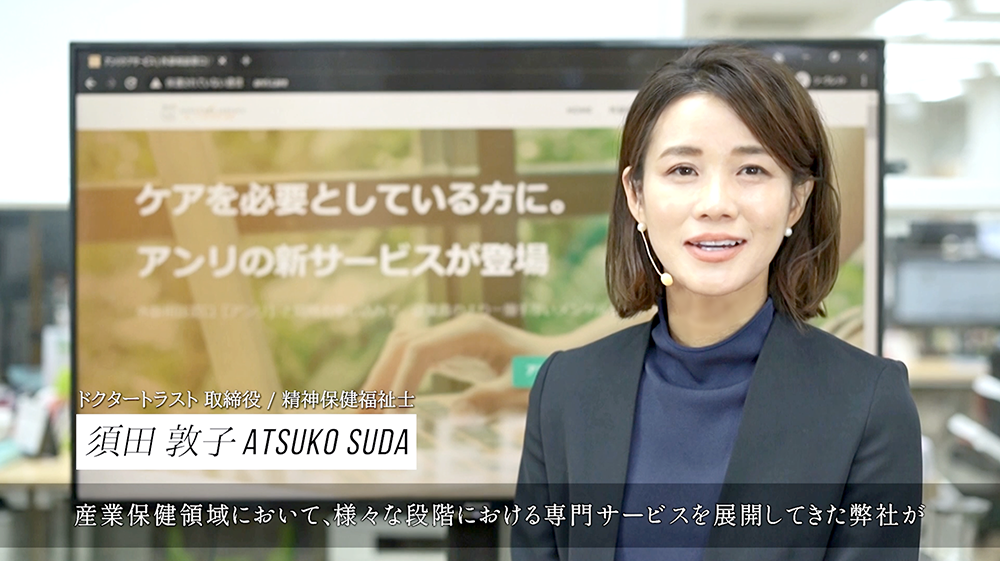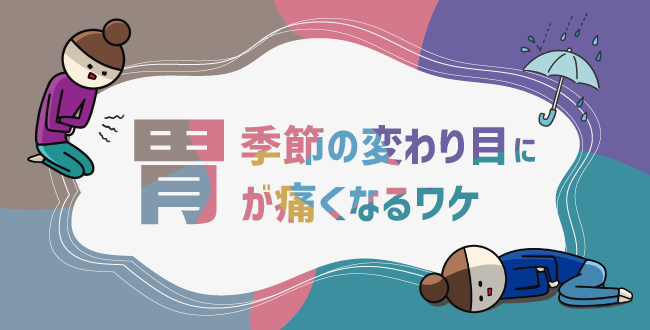- Home
- ドクタートラストニュース, 病状・症状
- 春先から初夏に流行!いま一度おさえておきたい「麻疹・風疹」の基礎知識
春先から初夏に流行!いま一度おさえておきたい「麻疹・風疹」の基礎知識
- 2025/4/22
- ドクタートラストニュース, 病状・症状
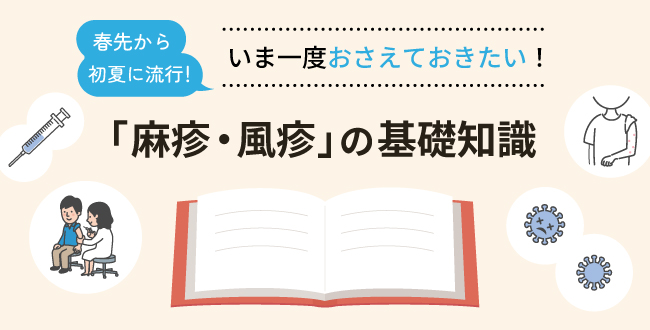
麻疹(はしか)・風疹とは
麻疹ウイルスと風疹ウイルスは、春先から初夏にかけて流行します。
空気感染、飛沫感染、接触感染でヒトからヒトへ感染が伝播します。
麻疹・風疹ウイルスは感染力が非常に強く、手洗いやマスクのみでは予防できません。
麻疹・風疹の臨床経過
麻疹の経過
麻疹ウイルスは、10~12日間の潜伏期間を経て発症します。
〈前駆期、カタル期〉
期間:2~4日間
症状:
発症時は、38度前後の発熱が2~4日間続きます。
発熱に伴い、倦怠感や上気道炎の症状(咳や喉の痛みなど)、結膜炎の症状(目の充血や目やになど)が現れ、次第に症状が増強します。
小児の症状としては、上記の症状と消化器症状(腹痛や下痢など)があります。
〈発疹期〉
期間:3~5日間
症状:
一度下がった発熱が、再び上がり高熱となります。
特有の発疹が出現し、最初は耳後部、頚部、前額部から始まります。
翌日には、顔全体から体幹部、上腕にまで広がっていきます。
2日間後には四肢末端にまで及びます。
〈回復期〉
期間:7~9日間
解熱し、発疹は消失しますが、発疹の色素沈着は残ります。
風疹の経過
風疹ウイルスは、2~3週間の潜伏期間を経て発症します。
症状としては、発熱、発疹、首や後頭部のリンパ節の腫れ、関節痛があります。
感染しても、15~30%程度の方が明らかな症状が出現しない場合もあります。
発症時は首や後頭部、耳の後ろを中心としたリンパ節が腫れます。
解熱後も、数週間持続します。発熱の症状は、微熱が出現して数日後に発疹が出現します。
その後高熱となりますが、数日で速やかに下がり発疹もともに消失していきます。
麻疹・風疹に感染したら、いつまで学校・職場を休む必要があるのか
麻疹・風疹は、学校保健安全法の第二種学校感染症として位置付けられています。
麻疹は解熱後3日を経過するまで、風疹は発疹が消失するまで休む必要があります。
麻疹・風疹ワクチンとは
麻疹・風疹ワクチンは、生涯で計2回のワクチン接種を推奨しています。
2回接種することで、生涯免疫が獲得できるといわれています。
ワクチン1回接種の場合、獲得免疫が不十分となり、潜伏期間が長期化することや症状が出現しにくいなど、軽症ながら発症して、周囲へ感染力は弱いが広げる可能性があります。
年代によっても接種回数が異なるため、母子手帳がありましたら一度幼少期の接種回数を確認してみましょう!
接種歴が不明な場合や不足分がある場合は、抗体検査や追加接種をご検討してみてください。
厚生労働省では、男性向けに風疹の抗体検査と追加接種の、原則無料のクーポン券を配布していることがあります。
またお住いの市区町村でも、男女向けに予防接種のクーポン券を配布しているところがありますので、ぜひチェックしてみてください!
特に、抗体検査や予防接種をお勧めしたい方は、以下の方になります。
出張や赴任で海外に行く方や、プライベートで海外に行く方
予防接種によって、罹患や重症化リスクを下げることができます。
必要な予防接種は、渡航先や期間、渡航目的、渡航者本人の年齢や健康状態、過去の接種歴などによって異なります。
海外では、日本にない病気が発生しています。
渡航先の感染症情報を収集することで、予防接種への意識や自分自身の予防対策の知識もつき、身の安全を守ることにつながります。
今後妊娠、出産を考えている方
妊娠中の方が麻疹に罹患すると、早産や流産のリスクがあります。
また、妊娠した女性(とくに妊娠20週頃まで)が風疹に罹患すると、赤ちゃんに心疾患、難聴、白内障などの障害が出る可能性があります。
妊娠中の方は、麻疹・風疹の予防接種を受けることができません。
妊娠前に予防接種を受けることをお勧めします。
また、妊娠中の方の周囲にいる男性も、影響を及ぼさないためにも予防接種をすることをお勧めします。
子どもが罹患する病気と思われがちですが、近年では大人の罹患者が増えています。
自分自身と周囲を守るためにも、集団免疫効果を上げて社会を守り、ワクチン接種できない方も守っていきましょう!