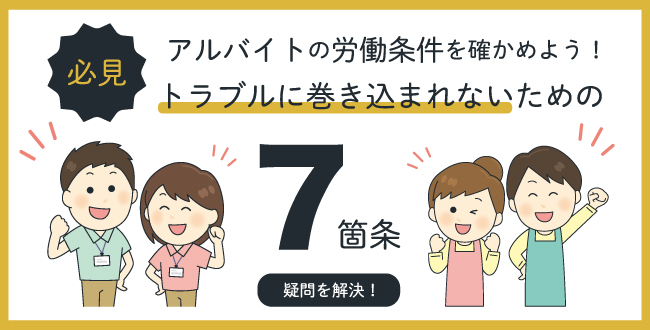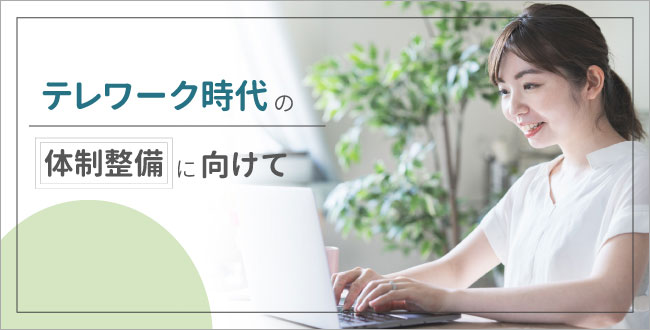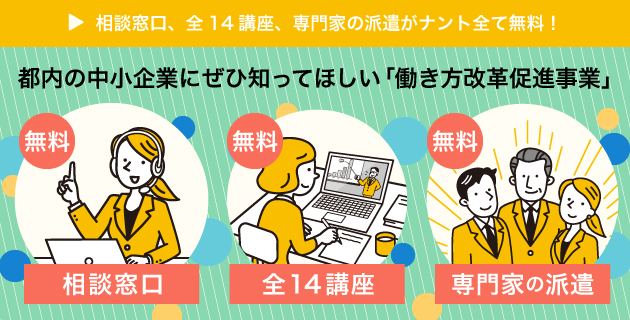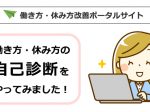毎年11月は、厚生労働省が定める「過労死等防止啓発月間」です。
長時間労働や過重な業務による健康被害、過労死の防止を目的に、全国で啓発活動やキャンペーンが行われます。
働く人の心身の健康を守り、安全で働きやすい職場環境をつくるため、企業・個人ともに働き方の見直しやメンタルヘルス対策が求められます。
本稿では、過労死の概要や予防策、11月に実施されるキャンペーン内容について紹介します。
過労死とは?
過労死は、業務における過重な負担による脳・心臓疾患や、心理的負荷による精神疾患を原因とする死亡を指します。
特に長時間労働や強いストレスは、脳・心臓疾患や精神障害のリスクを高め、場合によっては自殺に至ることもあります。
長時間労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、週40時間を超える時間外・休日労働が月45時間を超える場合、業務との関連性が高いと示されています。
長時間労働の削減策
まず、企業は労働者の労働時間を正確に把握することが重要です。
36協定(時間外・休日労働協定)の内容を周知し、週60時間以上働く労働者をなくす取り組みが求められます。
厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表しています。
ぜひこれを参考に労働時間管理をしましょう。
必要な環境整備
また、法定労働時間を超える労働を行わせる場合・休日労働をさせる場合には、36協定を過半数労働組合と締結し、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
しかし、法令遵守だけでなく、仕事と生活の調和が取れた職場環境の構築が不可欠です。
休暇取得が滞ると、健康や精神状態の悪化につながるため、効率的な働き方と休暇が取りやすい環境の整備が求められます。
合わせてメンタルヘルス対策も重要です。
企業は相談窓口の設置やストレスチェックの実施など、メンタルヘルスケア体制を整える必要があります。
働く人々はストレスチェックを通じて自身の状態を把握し、セルフケアに努めましょう。
職場の上司や同僚も不調のサインに気づき、専門家につなげる支援が求められます。
不調を感じた場合
自身の健康や精神状態に異変を感じた場合、早めに周囲や医師など専門家に相談することが大切です。
国や民間団体には相談窓口が設置されています。
代表的なものとして、産業保健総合支援センター、こころの耳、まもろうよこころ、過労死弁護団全国連絡会議(過労死110番全国ネットワーク)などがあります。
過重労働解消キャンペーン取組概要
11月の1カ月間は「過重労働解消キャンペーン」が以下のように実施されます。
① 労使への協力要請・周知
使用者団体・労働組合に対し、厚労大臣名で長時間労働削減の協力要請。下請け・中小企業へのしわ寄せ防止も呼びかけ。
② 先進企業への職場訪問
都道府県労働局長が「ベストプラクティス企業」を訪問し、事例を紹介・発信
③ 重点監督の実施
月80時間超の長時間労働が疑われる企業や離職率の高い企業を重点的に監督。
36協定遵守、賃金不払残業、労働時間管理、健康確保措置を確認。
悪質な違反は送検・公表、求人受理制限の対象となる可能性あり。
④ 過重労働相談受付集中期間
期間:11月1日(土)~7日(金)
「過重労働解消相談ダイヤル(0120-794-713)」などで相談受付。
過労死や過重労働の防止は、単なる法令遵守に留まらず、働く人の心身の健康を守り、より良い労働環境を作るために不可欠です。11月の啓発月間を契機に、個人も企業も働き方の見直しを進め、健全な職場づくりを目指しましょう。
⑤ 過労死等防止対策推進シンポジウムの実施
全国47都道府県で開催され、過労死遺族の体験談や専門家による講演の実施。
⑥ ポスターの掲示などによる周知・啓発の実施
一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・啓発を行う。
さいごに
過労死や過重労働の防止は、単なる法令遵守に留まらず、働く人の心身の健康を守り、より良い労働環境を作るために不可欠です。
11月の啓発月間をきっかけに、個人も企業も働き方の見直しを進め、健康な職場づくりを目指しましょう。
<参考>
・ 厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」